※日経エンタテインメント! 2025年8月号の記事を再構成
“アジア版グラミー賞”を日本から――音楽業界の主要5団体がタッグを組み、2025年5月に京都で初開催された日本最大級の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。授賞式のために来日した、世界の音楽シーンのキーパーソンが考える、MAJの意義、そして日本の音楽シーンの可能性とは? 複数指標から成る米国で最も権威のある音楽チャートで、近年、日本の音楽チャートでも中心的存在となりつつあるビルボード。MAJでも、エントリー作品の選考においてチャートを提供した。同社のエディター・イン・チーフのハンナ・カープ氏に聞いた。

米ビルボード エディター・イン・チーフ
ハンナ・カープ
米ビルボード エディター・イン・チーフ
2005~12年までウォール・ストリート・ジャーナルで勤務し、4年にわたって音楽業界のコラムを執筆。17年に米ビルボードにニュース・ディレクターとして採用され、18年から現職
――MUSIC AWARDS JAPAN(以下、MAJ)は海外に対してどんな影響を与えると思いますか?
日本の音楽シーンの盛り上がりを可視化できるという意味で、MAJはすごく重要な役割を担うと思います。まず第1に、このような賞が誕生したことで、世界各国の人々が日本の音楽シーンやアーティストを知ったり、学べたりする機会となります。
さらに、グラミーなどもそうなんですが、米国ではこういった授賞式のレッドカーペットの様子やインタビューがニュース記事として取り上げられることが非常に多いのです。ビルボードとしても、MAJを世界中に知らしめるサポートを今後もしていこうと考えています。
また今後、「アジアのグラミー賞」と呼ばれるようになることもそう遠くないのではないかと思います。グラミーは、アーティストがアーティストに投票して決まります。基本米国のアーティストが多いので、そういったアーティストを表彰してきた授賞式でもあるんですけど。それも少しずつ変わってきていて、グローバルなアーティストが受賞することが増えてきています。
そう考えると、アジアにおけるグラミー賞という立ち位置は十分に可能性があると思います。言語の壁も多少はあると思いますが、そこまで大きなハードルだとは感じていないです。
――日本の音楽シーンについてはどう見ていますか?
現在の日本の音楽シーンは、すごくエキサイティングで、ダイナミックだと思います。米国の音楽フェスを見ても、近年「コーチェラ」に日本のアーティストが多数出演していますからね。なかでも、XGは海外でもすごく人気が出てきている印象があります。
また、エイベックスに関しては、米国事業のCEO(再校経営責任者)に、米国の人気アーティストマネジメント会社のトップである、ブランドン・シルバースタイン氏が就任したことで、日本のアーティストの海外展開も加速していくのではと期待しています。
米国のリスナーは、K-POPといえばこういうサウンドというようなイメージを持っていると思いますが、J-POPに関しては、まだふんわりと理解している部分があるのかなと。ただそれは、J-POPが特殊なサウンドかつ、とても実験的で遊び心があることも大きい。個人的にはK-POPよりも聴いていて面白いなと感じています。
なかでもCreepy Nutsは、世界的に見ても誰も作っていないようなユニークなサウンドの楽曲を作っていて驚きました。
他には、ケロ・ケロ・ボニトという英国の音楽ユニットがいるんですが、ボーカルのセーラが日本と英国のハーフで、日本を意識したサウンドの楽曲で注目しています。
J-POPの海外進出には言語戦略も

Creepy Nutsは、2025年の「MUSIC AWARDS JAPAN」で「最優秀楽曲賞」を含む最多9冠に輝いた。授賞式では『Bling-Bang-Bang-Born』を披露した (C)MUSIC AWARDS JAPAN
――日本のアーティストがより海外に出ていくのに必要なことは?
いくつかあると思いますが、まず1つ挙げるなら、海外のビッグなアーティストとコラボレーションすることで、世界のオーディエンスに知ってもらうことではないでしょうか。昨年、ミーガン・ザ・スタリオンと千葉雄喜がコラボレーションした『Mamushi』は、米国でも大ヒットしました。これがいい例ですね。
あと、言語を戦略的に攻めることも1つの手だと思います。BTSが米国で大ブレイクを果たした『Dynamite』は、初の全編英語詞の楽曲でした。そのとき彼らは、「エアプレイ」(ラジオ)も重視し、そこのプロモーションにも注力していた。その結果、ビルボードチャートでも上位に入ることができたんです。
米国のラジオ局は、英語かスペイン語の曲しか掛かりづらいという現状もあるので、日本のアーティストが言語を意識した施策を行うのはありだと思います。
――米国のビルボードチャートの攻略法というのはあるんでしょうか?
多くのアーティストがやっているのは、新曲が出たらその週にファンに「ストリーミングしてね」と呼び掛けて、ファンとのエンゲージメントを高めていくことです。例えば米国で、今それがうまくできているのは、テイラー・スウィフト、サブリナ・カーペンター、バッド・バニーなどですね。彼らは、長期間にわたって曲を聴き続けてくれるファンを多く抱えており、ビルボードチャートの上位常連となっています。とはいえ、その前提条件として、まず良い音楽を作ることにフォーカスし続けることが何よりも大切。そして、それがファンの喜ぶ楽曲であれば、より良い結果を生むのかなと思います。
――世界と日本の音楽ビジネスにおいて違いを感じるところは?
大きく違うのは、ストリーミングのマーケットシェアの部分だと思います。世界市場では約70%ですが、日本は伸びてきているとはいえ、まだ約35%です。
今後の日本のストリーミングとJ-POPの可能性を占ううえで参考になるのが、米国市場における「カントリー」の存在感です。長い間、「カントリーのファンはCDしか買わない」と言われ、どちらかというと古いジャンルの音楽と認識されてきました。ただ、カントリーのアーティストも、数年前から、よりストリーミングへとシフトしてきたんです。
そして、元々はヒップホップ界隈だったポスト・マローンや、R&Bアーティストのビヨンセなどもカントリーだけのアルバムを制作し始めた。それが相乗効果を生んで、今、米国ではカントリーがクールな音楽ジャンルとして認識され、人気が高まってきているんです。
今後、日本のストリーミングへのシフトが進み、J-POPがより世界に発信されていけば、ジャンルとして注目される時代が来る可能性は十分にあると思います。
――今後の日本の音楽シーンには期待してもよさそうですね。
本当に明るいと思います。日本のアーティストの楽曲を聴きたいという需要は年々海外で増えていますからね。世界中のアーティストやリスナーたちは、次のグローバルヒットとなるようなジャンルを待っているんです。例えば、17年の『デスパシート』をきっかけに、レゲトン(レゲエやヒップホップの影響を受けて生まれたラテン音楽)が世界的に盛り上がりました。そして近年では、K-POPがそれにあたると思います。
なので、世界のファンを魅了できる日本のアーティストや楽曲が今後出てくることを、私自身も楽しみにしています。
続き:
J-POPの海外進出には言語戦略も
エンタメのここだけの話をお届け!
日経エンタテインメント! メール
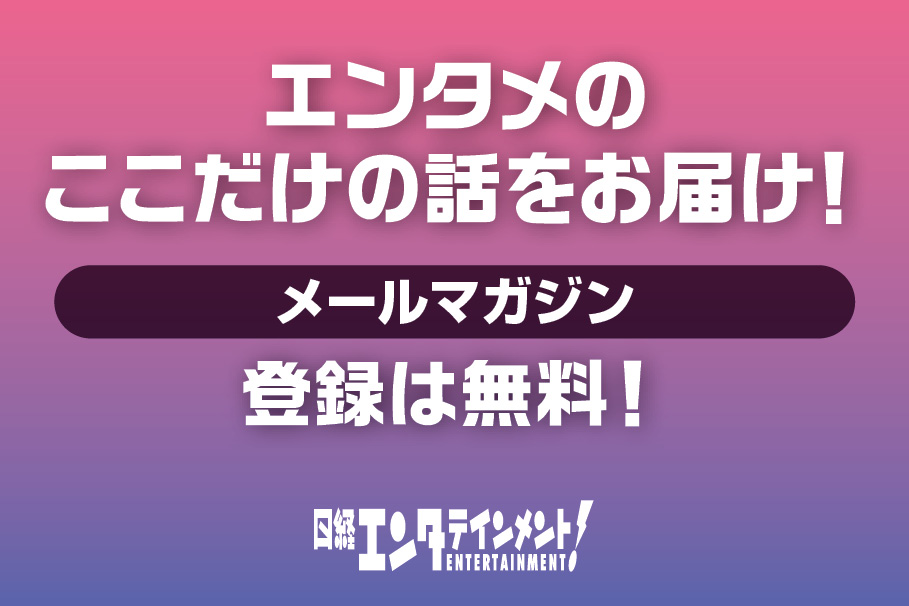
テレビ、音楽、本、映画、アニメ、ゲームなどのエンタテインメント情報を幅広く配信するメールマガジンです。流行に敏感で知的好奇心が強く、トレンドをリードする人たちに役立つ情報を掲載しています。登録は無料!
ぜひ、ご登録ください!

[画像のクリックで別ページへ]

