うちの子、発達障害かも?疑う前に知っておきたいこと|探究TV / 東洋経済education×ICT
【動画の概要】
発達障害とされる子どもが急増している。文部科学省の調査では、2006年には約7000人だった発達障害の児童数は、2021年には10万人を超えた。この15年間で14倍という劇的な増加だ。背景には、発達障害とはいえない「発達障害もどき」の存在があると、小児科医の成田奈緒子先生は指摘する。発達障害もどきとは何なのか?対応方法はあるのか?学校の先生から「お子さんが発達障害かもしれません」と言われたら?具体例を用いて、成田先生がわかりやすく解説。
【プロフィール】
成田奈緒子(なりた・なおこ)
小児科医、医学博士、「子育て科学アクシス」代表
神戸大学医学部を卒業後、小児科医として臨床経験を積んだ後、分子生物学・発生生物学・発達脳科学の研究に従事。米国セントルイスワシントン大学で遺伝子の研究者として勤務した後、2009年より文教大学教育学部教授に
【タイムテーブル】
00:00~ オープニング
00:17~ 「発達障害」と「発達障害もどき」
02:06~ 「発達障害もどき」3つのケース
09:14~ 我が子が「発達障害かも」と言われたら
11:04~ すべての子どもは発達する
ICT #ict #教育 #education #探究TV #探究学習 #東洋経済 #オンライン #成田奈緒子 #発達障害#発達障害もどき #見て聞くだけでわかる経済ニュース #東洋経済新報社
【チャンネル概要】さまざまな業界で活躍する方々への取材を通して、教育に関心を寄せるすべての視聴者に対し、新たな気づきや教育活動へのヒントとなる情報を発信するチャンネルです。教育現場を取り巻く環境は日々、変化しています。こうした流れを把握できると同時に、日本の教育をプラスの方向へ、ひいてはこれからの日本全体をプラスの方向へ導く原動力となる、信頼できる情報提供を行っていきます。
【東洋経済education×ICT】https://toyokeizai.net/feature/ict-edu

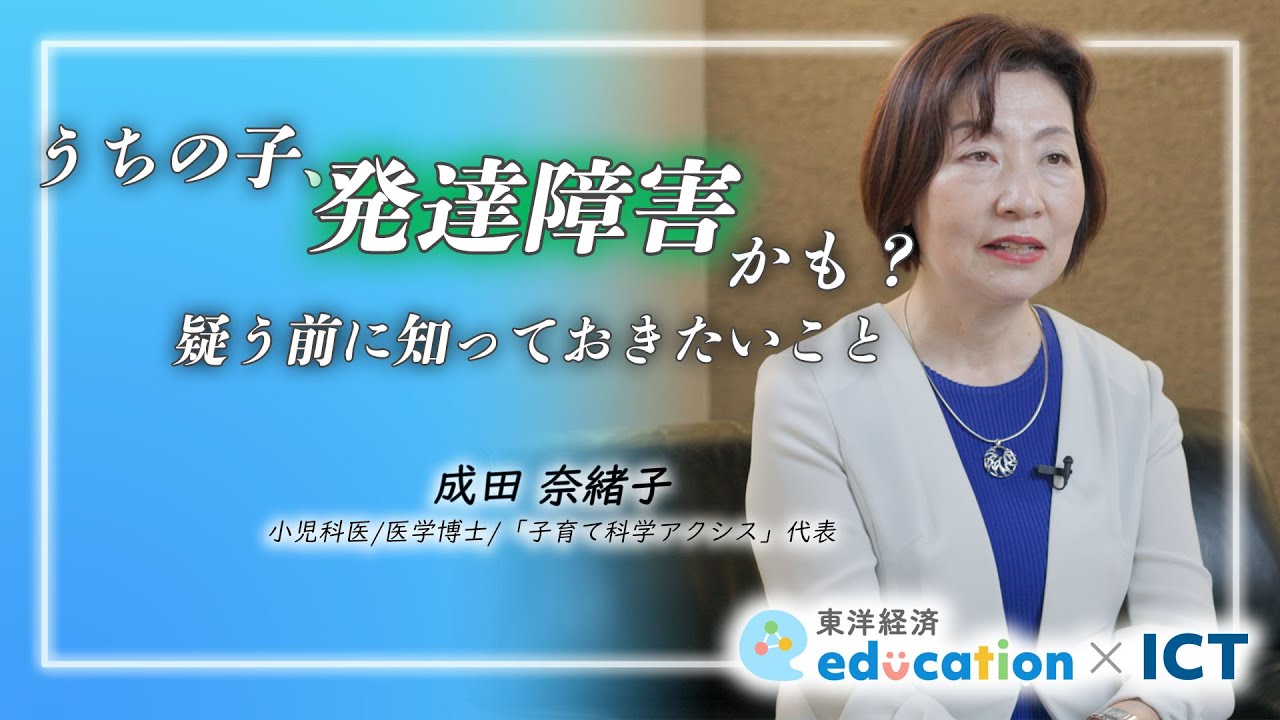
4 Comments
各ステージの教職員は、問題行動のある子供を直ぐに発達障害と決めつけて通院や療育をすすめるのではなく、睡眠や朝食の摂取など生活習慣を養育者に確認することができれば良いのではないかと思いました。
今の教育現場では、神経発達症(発達障害)についての理解が不十分で対応も曖昧なので、成田先生のような児童精神科医の方や専門家の協力のもと、上記のような対応をマニュアル化出来るよう、国が動いていく必要があると思いました。
スクールカウンセラーも、すぐに病院を紹介します。そして何故か、その病院で診断された生徒は、みんな発達障害と診断。コンサータ、エヴィリファイ、ストラテラなどの向精神薬を処方されます。その後、不審なのことは、どの子も問題行動がなくなっていない、ということ。トラブルが増えて酷くなる子もいる。
病院、薬を勧める教員やスクールカウンセラーって、なんなんでしょうね。
赤ちゃんの時から規則正しい生活って、親が身につける大切なことだと思う。子育ての根本的なことが間違っているのに、行われていなくて、子どもが言うことを聞かない、上手く行かないことを、発達障がいだと言ってしまう。とても怖いことだと思う。そして、小さな子どもに、身体に良くないお薬を飲ませてしまう。めちゃくちゃな生活をさせてしまってるように感じた。一番上の子どもが、24才になりますが、赤ちゃんの頃からの、日常生活がいかに大切かがわかります。これは、親が意識しないと身につかないこと。
発達障がいを言う前に、家庭や行政のしてる子育ての集まりや、保育園、幼稚園で指導を受けながら、親も、子育てしていくことが大切かなと、強く思いました。環境、とっても大切。みんな、子育てしながら、この先生が言われてあることを教えてもらったと思います☺️
当たり前ですが発達します
が、ある年齢を超えると特性が強くなる人が多いです。