【朗読】『旅への誘い』織田作之助(読み手:能登麻美子)
のとまみ子の葉ノートは塞学院の教師に似合 [音楽] [音楽] 合わず年中ボロ服同然のもっさりした服を 平気で身につけていた。 自分でも吹き出したいくらいブクブクと 太った彼女がまるで袋のようなそんな ブ細工な服をかぶっているのを見て要塞 学院の生徒たちはだるまさんと呼んでいた 。 しかしき子はそんなあだ名を別断悲しみも せずいかにもだるまさんめいたくリくリし た目でケラケラと笑っていた。 だま面壁苦念やけどうちは3年の辛抱で 住むのや。 3年経てば妹のみ子は東京の女子専門学校 を卒業する。 乾いた雑巾を絞るような学詞の仕送りの 苦しさも3年の辛抱で住むのだとき子は 自分に言い聞かせるのであった。 両親を早く失って他に身りもなく姉妹2人 きりの寂しい暮らしだった。 姉のキはどちらかといえば見にくい料に 生まれ 妹のみ子は生まれつき美しかった。 妹のみ子が女学校を卒業するとき子は 姉ちゃんうちちょっともみたいな上の学校 行きたいことあれへん。 近働くわ というみ子を無理やり東京の女子専門学校 の寄宿者へ入れ。そして自分は行玉神社の 近くにあった家を畳んで北畑の ミスぼらしいアパートへ移り、要塞学院の 先生になったその日から もう自分の若さも青春も忘れた顔であった 。 妹の学は随分の額だのに要塞学院でくれる 給料はお話にならぬくらい少なく 夜間部の授業を受け持ってみても追っつか なかった。 朝、昼、晩の三部教授の受け持ちの時間を すっかり済ませてフル造金のように ミスぼらしいアパートに戻ってくるとき子 は古をちぎって捨てたようにクタクタに 疲れていたが、それでも夜遅くまで要塞の 下手の沈事をした。 月に3度の高級日にも映画1つ見ようとせ ず、お茶1つのみにも行かず、切り詰め、 切り詰めた1人暮らしの中でせっせと内食 のミシンを踏み、急ぎの下手の時には徹夜 した。 徹夜の朝には誰よりも早く出勤した。 そして自分はミスぼらしい服装に甘んじ ながら 妹の卒業の日をまるで泳ぎつくように待っ ているうちにさすがに無理があったのか きみこは水の引くようにみるみる痩せて いった。 こんな痩せただるまさんってあれへんわ。 鏡を見てきこは1人笑ったが、しかし やがてそんな冗談も言っておれぬくらい だんだんに衰弱していった。 み子がやっと女性を卒業して大阪のキ子の 元へ帰ってきたのはやがてアパートの中庭 に桜の花が咲こうとする頃であった。 お姉様、ただいま お会いしたかったわ。 3年の間にみち子はすっかり東京言葉に なっていた。 ひみこは嬉しさに胸が温まってしばらく口 も聞けずじっと妹の顔を見つめていたが やがていきなり妹の手を卒業免除と一緒に 強く握りしめた。 その姉の手の暑さにみ子はドキンとした。 からお姉様の手とっても暑い熱がある みたい。 言いながらみちこはびっくりしたように姉 の顔を覗き込んで それに随分おせになったわね。 うん。何でもあれへん。 せた方がみちちゃんに似てきてええやない の? きみ子はそう言って寂しく笑ったがしかし その晩君子は39°以上の熱を出した。 みち子は制服のまま氷を割ったりタオルを 絞り替えたりした。 朝医者が来た。 幕を犯されているということだった。 医者が帰った後でみち子は薬をもらいに 行った。 粉薬と水薬をくれたが、随分流行らぬ医者 らしく、粉薬など粉がこチコチに乾いて べったりと袋にへりつき、何年も薬局の 引き出しの中に押し込んであったのをその まま取り出してくれたような気がして何か 頼りなかったが、しかしみち子は姉がそれ を飲む時間が来ると どうぞ聞いてくれますようにと密やかに 祈った。 しかし 姉の熱は下がらなかった。 桜の花が中庭に咲き、そして散り やがて嫌な梅が来るとき子の病気はますけ なくなった。 ゆが開けると行玉神社の夏祭りが来る。 ちょうどその読みやの日であった。 君子が教えていた戦士者の未亡人たちが やがて卒業して共同経営の要塞点を開くの だと言ってそのお礼方々見舞いに来た。 いち子がその人たちを玄関まで見送って 部屋へ戻ってくると壁の額の中に入って いるみ子の卒業免除を力のない目で見上げ ていたキ子が急にか細いしがれた声で みっちゃん玉 さんのしまいの林しが聞超えてるわ と言った。 みち子はふっと窓の外に耳を傾けた。 しかし このアパートから随分遠く離れた行玉神社 の形のししまいの稽古の音が聞こえてくる はずもない。 窓にが当たっているのに気がついたので みち子は立ってカーテンを引いた。 そしてふと振り向くとき子は あは [音楽] とかに言って そのまま生き耐えていた。 姉の葬式を済ませて3日目の朝のことだっ た。 この4日手に取って見ることもなく溜まっ ていた古い新聞を その溜まっていることをいかにも自分の 悲しみの印のように思いながら見るとも なく見ていたみ子は急に目を輝かした。 南方派遣日本語教授要因の募集の記事が ふと目に止まったのである。 へ日本語を教えに行く人を募集しているの だわ とつぶやきながら読んでいって 応募資格は男女問わず専門学校卒業または 童貞度以上の学力を有するもの という箇所まで来るとみ子の目は急に輝い た。 子はまるで勝じをなめんばかりにしてその 箇所を繰り返し繰り返し読んだ。 応募四角は男女問わず専門学校。 み子は不の額に入った卒業免所を見上げた 。 姉の青春をいや姉の命を奪ったものはこれ だったかと見る度びチクチクと胸が痛んだ 卒業免除だったが今ふと あ、ちょうどあれが役に立つわ と呟いたとさにみち子の心はりと晴れた。 お姉様がご自分の命と引き換えにもらって くだったあの卒業免許を お国の役に立てることができるのだわ。 そうだ。私は南方へ日本語を教えに行こう 。 み子はそうつきながら、 みち子は 姉の死の悲しい思い出の突きまとう離れて 遠く南の国へ誘う 旅のいないに熱く心を揺ぶられていた。 27の年までお嫁にも行かず、若い娘 らしい喜びも知らず、だるまさんは孤独な 清潔な苦労と睨みっこしながら 若い生涯を終わってしまったのである。 その姉の寂しい生涯を思えば、もはや 月並みな若い娘らしい幸福に甘んずること は許されず、 姉の一生を吹き渡った孤独な冬の風に自分 もまた吹雪と共に吹かれて行こうという み子にとっては 自分の若さや青春を捨てて異境に働 [音楽] 異境に死ぬより他に姉に報いる道はないと 思われた。 [音楽] お姉様もきっと喜んでくださるわ。 南方で日本語を教えるには標準語が話せ なくてはならない。しかし自分は3年間 東京にいたからその点は大丈夫だと。み子 はわざわざ東京の学校へ入れてくれた姉の 心づしが今更のように思い出された。 志願書を出して間もなく先行試験が行わ れる。 その後等門の石場で志願の同機や家庭の 状況を問われた時、 姉妹2人の暮らしでしたが と言いながらみ子は不確にも涙を落とし、 あ、こんなに取り乱したりしてきっと後頭 指紋で跳ねられてしまうわ と心配したが、それからき余り立ったある 朝の新聞の大阪番に合格者の名が出ていて 、その中に田村み子という名が包ましく出 ていた。 み子の生命は田中み子であった。 これが田村み子となっているのは多分新聞 の触であろうとみち子は一応考えたが、 しかしひょっとして同じ大阪から受験した 女の人の中に自分とよく似たの田村み子と いう人がいるのかもしれない。そうだと すれば大変と思ってひたすら 正式の通知を待ち詫びた。 合格の通知が郵便で配達されたのは3日の 朝であった ところがその通知と一緒に田中き子様と 泣き姉に当てた手紙がひょっこり配達され ていた。 アパートの中庭ではもう木星の花が匂って いた。 死んでしまった姉に思いがけなく手紙が 舞い込んでくるなど まるで嘘のような気がした。 が死んだのは忘れもしない。行玉神社のや の暑い日であったが、もう木星の匂う こんな季節になったのかと 姉の死がまた熱く胸に来てみ子は涙を新た にした。 て 涙を吹いて封筒の裏を見ると 佐藤介とある。 思いがけず男の人からの手紙であった。 み子は何か胸が騒いだ。 み子が姉の元へ帰ってからもう半年以上に もなるが、水まで男の人から姉のところへ 見舞いの手紙も、また悔みの手紙も来た ことはなく、それが姉の寂しく清潔な障害 を悲しく裏書きしているようで、み子は ふっと切なかったが、しかし姉が死んで みつも立った今手紙をよしてきたこの 佐藤介という人は一体誰だろうと好奇心が 起こるというより むしろ寂しかった。 [音楽] 随分長らくごぶ沙汰して申し訳ありません 。 僕もいよいよ来年は大学を卒業するという ところまでこぎつけましたが、それに 先立って額と海わを志願し、近く を飛び立つことになりました。 長い間 としての生活を送ってきた僕には泳ぎつく ように待たれた卒業でしたが、しかし今額 と海わとして飛び立つ喜びは卒業以上の 喜びです。 おそらく 生きて帰れないでしょう。 従ってあなたにもお目に書かれぬと思い ます。 いつぞやあなたにおかしした王の即興主人 の書物は 僕の片として受け取ってください。 長い間住所も知らせず手紙も差し上げず 怒っていらっしゃることと思いますがその お詫び方々お便りしました。 僕は今でもあなたが苦学生の僕の洋服の 誇びを塗ってくだったご親切を忘れており ません。 ご試合 拾ります。 その文面だけでは姉のき子とその大学生が どんな付き合いをしていたのかみ子には 分からなかったが、しかし読み終わって姉 の机の引き出しの中を探すと果たして外 の即興主人の文庫本が出てきた。 姉様はなぜこのご本を返さなかったの だろう と呟いたとっさに。あ、そうだわとみ子は 思い当たった。 当時大阪の高等学校の生徒であったその 青年は高等学校を卒業して東京の大学へ 行ってしまうともうそれきり手紙もよさず い所も知らさなかったのではなかろうか。 それゆえ返そうにも返せなかったのだ。 多分2人の中はその生徒よりも3つか4つ 年上の姉が区学生だというその教遇に同場 して洋服の誇びを塗ってやったり靴下の穴 に次を当ててやったりしただけの淡いもの で離れてしまえばそれきり居所を知らせる 義務もないような何でもない中であったの かもしれないとみち子は想像した けれどお姉様が待っていらっしゃったのは やはりこの人の頼りだったのだわ。 [音楽] み子はそうつき、机の引き出しの中に大切 に包ましくしまわれていた即興主人の中に 密かな姉の青春が秘められていたように 思われて ふっと 温かい風を送られたような気がした。 でも 待っていた頼りが死んでしまってから来る なんて。 そんな そう思うとみち子はまた姉がかわいそう だった。 姉の青春の寂しさがこんなことにも悲しく 現れているとポトポト涙を落としながら みち子はペンを取って返事を仕ためた。 妹でございます。 羽き子は今年の7月8日 永遠に帰らぬたに旅立ってしまいました。 長い間ご本をお借りして ありがとうございました。 そこまで書いてみ子はもう後が続けられ なかった。しかし、ただ悲しくなって筆を 止めたのではなかった。 額と海わしとして大しく旅立とうとする人 にこんな悲しい手紙を出してはいけないと 思ったのだ。 これまで姉に手紙をよさなかったのは おそらく学生らしい呑気なズボらさであっ たかもしれず。 そして今再び生きて帰る前と決心したその 日にやはり姉のことを思い出して頼りを くれたその気持ちを思えば 姉の死はあくまで隠しておきたかった。 み子は書きかけた手紙を破ると改めて 姉の名で激例の手紙を書いて 送った。 南方派遣日本語教授要因の連静を受ける ためにみ子が状況したのはそれから1週間 後のことであった。 早朝大阪を立ち、東京駅に着いたのはもう 黄昏れ時きであった。 お電に乗ろうとして姉の異骨を入れたカを 下げたまま駅前の広場を横切ろうとすると 学生が一段となって効果を合唱していた。 み子はふと佇んでそれを見ていた。 効果が済むと3拍子の拍手が始まった。 拍手、拍手といういかにも学生らしい 掛け声に微笑んでいると誰かがいきなり 佐藤し介君万歳 と叫んだ。 元気で行ってこいよ。佐藤し介頑張れ。 聞いたことのあるな。だと思ったとっさに みち子はドキンとした。 あ、佐藤さん。 1週間前姉に手紙をくれたその人ではない か。 もはや事情は明瞭 と海わを志願して航空隊へ入退しようと するその人を見送る 学友たちの一段ではないか。 [音楽] み子はワクワクして人混みの後ろから 背伸びをして覗いてみた。 円形の陣の真ん中に1人照れた顔で硬い 姿勢のままつっているのがその人であろう 。 思わず駆け寄って 妹でございますとみち子は名乗りたかった 。 けれど 神聖な男の方の世界の角手を怪我しては ならない という思いがいきなりみち子の足を救った 。 みち子は思い止まった。 そして どうせ私も南方へ行くのだわ。 としたら どこかでひょっこりあの人に会えるかも しれない。 その時こそ でございます。田中き子の妹でございます と 名乗ろう。 密がにつきながら 教師の音が黄昏れの中に消えていくのを 聞いていた。 [音楽] ごとに暗さのまま増していくのがわかる 晩収の黄昏れだった。 やがて その人が駅の改札口を入っていくその広い 肩幅を密かに見送って 再びその広場へ戻ってくると 辺りはもうすっかり暗く すると夜が落ちていた。 お姉様 みち子はお姉様に変わって お見送りしましたわよ。 みち子はそうつくと姉の異骨の入ったカを 左手に持ち替えてそっと目を吹き そして年上に当てられた 赤坂青山町のお寺へ急ぐために 途電の定流所の方へ 歩いていった。 [音楽]
『能登麻美子 ことのはNOTE』より、朗読パートをお届けします。
■ラジオ全編はこちら
■朗読パ-ト再生リスト
■ハッシュタグ
#ことのはNOTE
■公式X
https://x.com/KOTONOTE0206
#ことのはNOTE #能登麻美子 #朗読 #文学

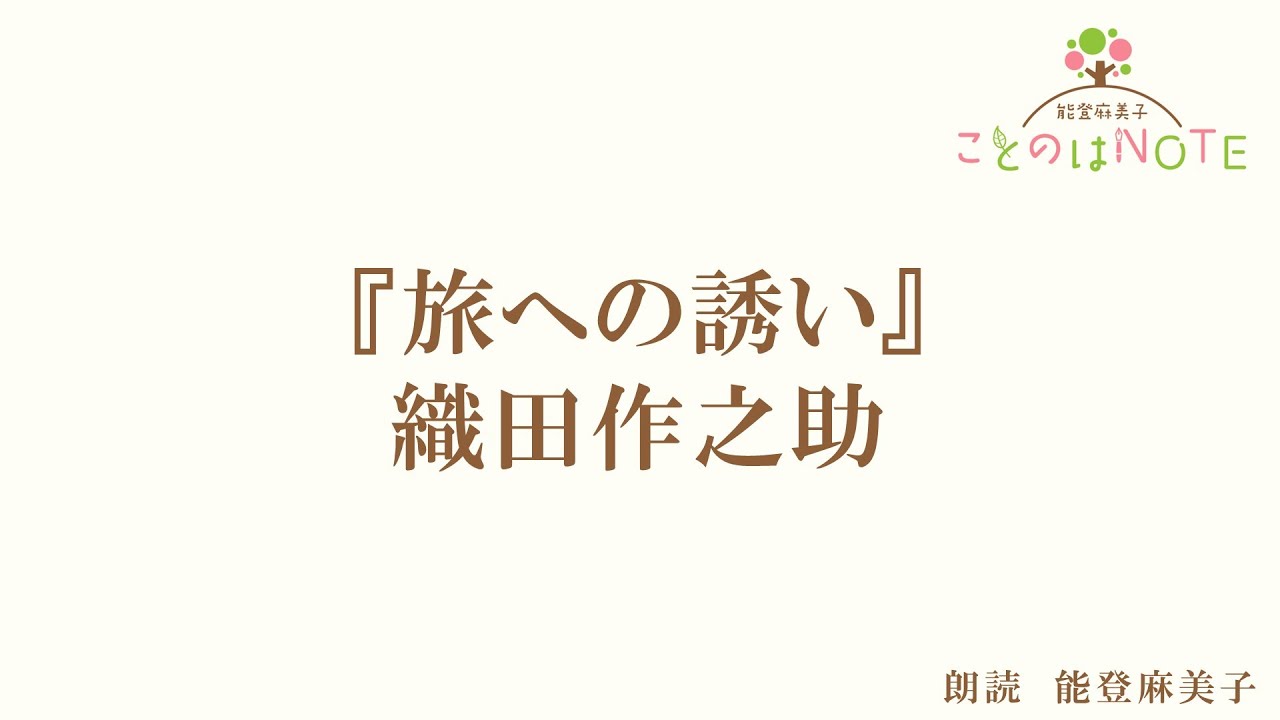
1 Comment
Jun Kazama.