ニュースで語られないウクライナ〜人々の日常になった戦争 ゲスト:ロバート・キャンベル(日本文学研究者 早稲田大学特命教授)MC:近野宏明 上野愛奈 BS11 インサイドOUT 10月13日(月)
2022年のロシアによる進行開始以来。 今も多くの犠牲者が出ているウクライナ。今年 8 月戦が続く町を日本文学研究者ロバートキャンベルさんが訪れました。 すごく深いところまで、え、モグロを通しています。 地下鉄の校内をシェルター代わりにする ウクライナの人々の日常。 激しい戦闘が続く東部から多くの人たちが 避難する西武リビューでは負傷者を支援 するための街ぐるみの取り組みを取材。 そして 主とでは戦場で両手を失った元兵士をまた戦場で息子 2人をなくした母親を 心臓を引きちぎられ、地子宮をもぎ取られ、抜け柄だけが残る。 最前線の町ではアートの捜作に目を輝かせる子供たちを尋ねました。 今や生活の一部となった戦争の中で生で生きる人々の思い。ニュースでは語られない戦下にさらされる人々の日常を伝えたい。キャンベルさんがウクライナを訪問するきっかけとなった [音楽] 1 冊の本があります。ウクライナの人々の言葉をった戦争ご一周です。 [音楽] 2年前に翻訳を手掛けたキャンベルさんに 今日はこの本から2つの物語を朗読して いただきます。 [音楽] おばあちゃん有利在住。 向い側の建物だった2人のおばあちゃんの アパートは破壊されましたけれど、人の ところには行きたくないと言ってよそに 映ることをしぶっていました。ま、その わけでおばあちゃんたちは日が1日玄関前 のベンチに座っていました。で、そこで 破片にあたって死んでしまいました。が 降り注ぐ合間を塗って私たちは中庭に穴を 掘り2人を葬りました。 もう1を、え、紹介させてください。 沈黙ナ リビュー在住。人形劇場が避難シェルタに 変わりました。舞台の上もホールもロビー にもマットレスを引き詰めました。最初の 数日は子供と動物を連れ立っている人が 多かったです。2日間彼らは朝から晩まで マトレスの上でシーンと静まって横たわっ ていました。これほど多くの沈黙する子供 たちと動物が1つの場所にいるところを私 は見たことがありません。そこから少し ずつ彼らは元気を取り戻していきました。 でも私はあの沈黙を忘れることはないでしょう。怖かったですよ。はい。キャンベルさんにごごご朗読いただきましたけれども、まずこ野藤さんおばあちゃんの方ですよね。あ、席におりただいてありがとうございます。ありがとうございます。 [音楽] おばあちゃんの方ね。 ええ、あの はい。 攻撃を受けていながらもやっぱり他のところに行きたくないっていうそのおばあちゃんの言葉があったと思うんですが、なんかあの戦争が起きた時に私そういう光景っていうのを見てつまりやっぱり自分の居場所や家っていうのが 失われるそのもうなんて言うんです心苦しさと同時に うん そのやっぱりそこにい続けたいっていうのってなんかこの千地ならではのなんか思いなのかなんてことを私は感じましたね。 そうね。ま、とにかく生まれ育ってきた町 、あるいは今までその心を通じ合わせてき た人たちと暮らしてきた町っていうのがね 、もう無惨に破壊されていく時に私はその 離れたくないっていう気持ちは、ま、 おばあちゃんの覚悟っていうんでしょうか ね。 だからその様子を見守っていたお迎いのこのこのねストーリー語った方というのはうん おばあちゃんの体を埋葬しているのがま事実なんだけれども埋葬してるのはそういうおばあちゃんの内心というか覚悟というかねそこもお侍いしてるのかなというねあの私はそういう風にも受け取ったんですけども うんうん キャンベルさんこのね語一集っていうのはまずこう全 具体的なこの本に貫かれた特徴っていうのはどういう特徴があります?あの読みましたけど ありがとうございます。いくつかありますけれども 1つは戦争の体験はあの 1人1 人の言葉をまっすごく変えてしまう、もうひん曲げてしまうということが あのこれを読み通して分かることですね。うん。 例えば、えっと、バスターブとても私たちは 1 日仕事終わって落ち着く場所ですけれども、今私も実は経験をしてるんですけれど、空習警報がなると、え、外から壁が 2つある 壁2枚の法則っていうものがありまして、 え、シェルタに行けない人たちは家の中でどこでこう身を寄せればいいかということでバスターブなんですね。 窓がないバスターブ でそこに入って布団とか枕とかこてとにかく自分を守るっていう、 え、バスターブがそういう風に自分がこう非常人の時にその守ってくれるものに変わったりというようなあのことであと体のがある若い女性にこれがロシア兵に見つけられたら自分はま、ウクライナの国水主義者じゃないかと誤解されて自分がま、入れた若い時に入れた自分の体の一分が 自分の命をちょっと奪ってしまう原因になるんじゃないかとか うん。 1つ1 つのものがやっぱり戦争によって大きくこう変わってしまうっていうことを私たちに 1人1 人のそのやっぱり、ま、物語ストーリーを通じて、え、語ってくれてるわけですよね。うん。 戦争によって物の意味が変わってしまうっていうのは これ本当に何か読んでいて、特にあの私もあの我が家という はい。あの、タイトルの死を読んだ時に やっぱりコンディショナーが女性にとって はもう本当にこう心の癒しの存在だったの がやっぱりそれが放射性物質なんかがこう 紙につく原因になるからそれが使えなく なったんだっていうようなものが書いて あったんですけれどもやっぱり自分たちが そういう風に癒しを求めていたものが急に こう恐怖を感じる対象にな るっていうところがこの本の表紙もえっと 大きなこうカトリアのまゆりが描かれてる わけですけどこれも実 は、あの、避難した女性がアーティストが書いたものを彼女の家で見つけて、あの、ま、お借りをして、写真をお借りして掲げてるんですけれども、あの、え、あの、村がちょうど奪還されてそこにたとまっていかないおばあちゃんたちのように 60代の女性が、 え、音と一緒にずっと育てて花畑がて、そこから離れたくないということで、家は壊れたけれど花はすごく綺麗に咲かせて というところに、ま、ボランティアとしてアーティストが行って写真を撮ってそれを後で絵に描いたということなんですね。ですからこういう 1つ1 つお花であるとかコンディショナーであるとか 鍵束であるとかいろんなものがやっぱりま、記憶やいろんな他の意味をですね、ま、ま、戦争の当事者たちの中にあのすごくやっぱこういろんなイメージをですね、不安や、ま、恐怖をうん。 あるいは安心をあの蘇らせるわけですね。 うん。うん。 今、あの、安心っていうね、あの、言葉が出たり、あるいはその戦争といえば当然恐怖であるとか、あるいはそのなんて言うんでしょう。憎しみであったりとかね。その形のないもの、抽象的なものって言うんでしょうかね。形のないものでこう括られる場合が結構多いと思うんですけど、これがここで語られている言葉というのはかなりそうじゃないと本当にあの形あるもの。しかも私たちにとって なんて言うんでしょう?身なというね。 はい。いや、このさん、そこで1番私が 最初にこの目に入って読んだ時にこの胸を 打たれたんですけれどもなんかこう逃れて もう木の木のままもう24時間ぐらい電車 鉄道に乗ってリビューに降り立った人たち がなぜかこう手の中にこのカ鍵束を持っ てるんですね。例えばその鍵の1枚1枚の 鍵は誰の鍵なのか。 その鍵が今家が破壊されてないのかどこに行ったのかっていうことを見ながら、ま、語ってるわけですよね。 ですから向き出しの像をあの暴力をこう振われた敵に対するあそういうなんて言うんですか?そういうこうもう荒いも気持ちとか言葉というよりも本当に自分が生きてる 1 番こうベースにある基本にある基盤にあるものを 思い出して今おっしゃったように愚傷的に具体的なものとしてそれやっぱり現れてるっていうかそれって戦争だなっていう風にうん。 あの、戦争映画とか時代劇とか色々こう ずっと今読んで見てきた自分にとってはあ 、戦争ってま、爆弾が飛んだりがあの 当たったり人が本当にそ目の前 で亡くなったりすることだけが戦争ないと いうことはすごくま、経験を通して、ま、 知ることはできたわけですね。うん。 としてもう1 つ沈黙というタイトルの死朗読していただきましたが、その舞台となった人形劇場の方、キャミルさん、今回もこの再開ができたんでしょうかね。 はい。あの、ちょっと1年半ぶりに、あの 、会いましたけれども、え、売ナさんが、 あの、え、人形劇、あ、こちらはですね、 マテレスを敷き詰めて子供たち、大人たち が60人ぐらいがですね、この100年 以上前に経った立派なあの旧ソ連それぞれ の国であの人形劇が大人のためにもとても 大切な芸能だったわけで、今も非常に坂に 新作がたくさん作られて、私も2つ3つ ぐらい今回も見ることできたわけです。 けれどもシェルタとして解放したんですね。これ日本やメリカであればまず劇場のこの機能を止めてシェルターに専すると思うんですがそれはせず劇団がそこに身を寄せてる人たちのケアをする一方新しい芝居を作ってリハーソルをしたり実際にそこで演をしたりするていうことをとてもこれはやっぱりこうなんて言うんでしょう?どうしてこういうことができるのかっていうように うん。 あの、非常にこう、やっぱり強く何かを表現しないといけない。その、その時でなければ自分たちの経験ということをストーリーと整理をしたり、理解をしたり、とめるっていうことはできないということはここでも感じましたね。 でもこの劇場があるリビューっていう街が、ま、先ほど地図ありましたけれども、 1 番こうウクライナの中の西に近いこのポーランドの国境から比較的近いところで、私たちこのメディアの多くもですね、この現地の取材に行く時には、ま、大体このポーランド呼境を超えてリビューにまず入るというのがあの多いわけですけれども このね、その町どういう今状況にあるという風に見ればいいんですか? うん。ま、世界3 人もあの登録されてて中世代から交通の要少ですけれども人々が常にこう生きしているあの場所なんですよね。 で、ま、そういうこともあって、避難者たちがここを、ま、 1つの通路にして 大量にヨーロッパに逃れていたけれども、今は比較的安定したミサイルはそれほど毎日のように、え、飛んでこないということで全国、全国民でもう 30万人以上の人たちが障害が残るような 怪我をしてるわけですね。 全国民を受け入れ、え、繋がっていてその人たちの傷を直し、そして社会復帰をさせるために街ぐるみでこう 1つのシステムを作ってるわけですね。 そう。そのシステムはアンブロークンというこれあえて英語っていう名前をつけてるんですけれども壊れていない。うん。 傷ついてはいるけれど壊れていないというあのものです。 うん。これは非常に私がここにあの2日間 3日間ほどあのま、中に入って負傷した 兵隊、え、市民たち、それから彼らの 手当てをしている学療報士や アートセルピーに関わってる方々の取材を することができましたけれども、本当に 街ぐるみで1つのエコシステムとしてうん 、えっと、このと多くの人たち歩いる と本当偽則や義種をあのつけた方々とても 多いですね。 で、彼らは彼らであの、ま、何かそのやはり病 9 世紀から例えば偽則をつける、訓練をするもう長い過程を経てあの社会に戻っていくわけですけれどもそれを受ける社会 も変えないといけないということが同時にあるわけで、ま、そういうこともあって町の中にできるだけ交われるようにいわゆる健状者と一緒に、えっと、ま、貸化させていくっていう本当最のリハビリプログラムう いうものをそこで作ってるわけですね。うん。 確かにこの社会が受け入れてくれるかどうかってやっぱりこうった人たちにとってはもう本当に重要なことで立ち直るためにはどうしても必要なことだと思いますよね。 そうです。ね、この町のま、 1 番徴的なのがリビューがそうまさにその命の回路っていうんでしょうかね。命をつぐためのそのルートにある。 でも実はそのキャンベルさんが訪れた、今回訪れた地域というのは地図改めて見ると春級ってね、もう逆に 1番こうロシアに近いこの春九州の第 2 の年でしたかね。クライナにおけるこなんか、ま、なかなかですね、足踏みれること自体もあの、特に外からめられるかと思うんですけども、それでもやっぱり現場に行きたいと はい。ま、あの、おっしゃるように非常に対象的な町ですね。 で、あの、はるはとっても人口が、ま、多いわけですけれども、え、最初洗面戦争が始まった時にもう、もうガクンとこう、あの、ま、人口が減り、そしてその春の周りからこれは本当に見て分かるように前線ですよね。そこから逃れてくる人たちが街の中に入ってきまして、 [音楽] そうですね。人口が実はあまり変わってないんですね。あの、で、ま、そこにはあの、なかなか、ま、日本人はあの、ない。 うん。 己責というか、外務省も韓国がていまして、できるだけそこに行く、行く前というか行くべきではないと思いますが、ただ私があの、えっと、立ち止まって避難せず、え、その場所に残って、あ、特に表現ですね、ま、アートをこう作ることを通じて、ま、戦争が日常状態の中にある人々び、ま、町風景、え、人々 1人1人をどういう風 [音楽] 見て聞いて 匂いを嗅いで あの実際に見ないとわからないということを分かりましたので 1週間ほどあるにあの行ってきました。 ちょっとなかなか行けない場所なのでちょっとあえてお聞きしますけれどもそれはやっぱりすんなり行くっていうことはできたんですか?ウクライナに中に入っていくっていうことは可能だ。 はい。 えと、ウクライナには私は先ほどこ野さんがおっしゃったように今回もリビューから入り、えっと安ブローのあの施設をあの市長にも会っていただいてたくさんの方々の協力であの深いところまであの見ることはできましてそこからに鉄道で 6 時間ぐらい移りは油であのアーティストや学芸それからま傷した方々のお会いをしてそしてそこからまた今度は車であの同時通訳を 2人常ににあのさせることにしたんですね 。それから動画を今日お見せしてる動画を 作ってくれる春球出身の大変優れた カメラマンに依頼をして一緒に動いたわけ ですけれども春球まではやっぱり男性女性 はなかなかまけないということで車で移動 してま男性で4人であの行ったわけですね 。 シェルタがしっかりしたホテルにあのまって 1 週間ほどアーティストのコミュニティはとても、ま、タイトいましょうか、結束がとても強くてある場所、ま、これはカフェですけれども行きますとほとんど全ての人に通じるということがあり、うん。 とにかく日本から誰かがあの来る、会いに来るていうことだけでとっても歓迎されたので はい。 はい。 あの、方々に普通、ま、多分平和であれば、あの、お、会いすることはできない、ま、国民的な本当にアーティストであったり、音楽であったり、そういう方々と実は春級で 1番、ま、真層ですね、 1 番ディープなあの取材をすることができました。 うん。 ウクライナでは戦争によって町が傷つけられ、人々と心の体、心と体が傷つけられ、そして今なおその傷は深く残っています。 まずはキャンベルさんが首都有郊外で出会った心を傷つけられた人についてです。 首都に到着したキャンベルさんが向かったのは戦争で 2人の息子をなくしたある女性の元。 彼女は都会を離れ、息子たちが育ったキ子が大切にしていた犬と一緒に暮らしていました。 進行が始まった3 年前に次難を戦場でなくし、今年の 2 月には長男も戦してしまったスびトラーナさん。 心臓を引きちぎられ、地球をもぎ取られ、抜け柄だけが残る。でも選択肢はない。生きるしかないのよ。 息子が軍に入退した時、無事に帰ってくる ことを願って、彼女はこんな約束をしまし た。 戦場から無事に帰ったら誕生日に何でも 買ってあげるわよと息子に言ったら、息子 は犬でもいいと言ったの。私は像でもキリ でもワニでも好きなものを買ってああげる と答えたの。 しかし再び戦場へと戻った息子は帰らぬ人 となったのです。 そしてこの犬だけが残ったの。この子は今 では私たちにとって結び目のない愛のよう な存在なの。 すびトラーナさんは亡くなった息子へ 捧げる死を読んでいます。 ロマンに捧げる歌。君は夏を求めた。夏 みたいな熱血で蜂蜜にdəと鋭いマ差しで 求めに行った。狂器じみた優しい賢い野生 的で盲目で欲しいものを全てを集めをへと つき進んだ。突然去った君は全てを持って いた。そして神の毛に砂、ポケットに夏酒 、私の鍵、野生のサラんぼを持って 忍び寄る秋と肺の中の空気さのうちなる 戦いを抱えて突然戻ってきた。 手がくば私は物げなこの闇を君から引き剥がし原始にまで引き裂きそのかけらから君を再び塊に組み立てたい。 はい。 キャメラさん朗読ありがとうございました。 本当にこのお母さんのね 時合というかねというにはま、あまりにもちょっと悲想ですし、ま、特にその終盤の方うん。 息子のことをこう原子にまで引き裂いて原子ってあれでしょ。あの原子文書の原子 にまで引き裂のかけらから君を再び魂に組み立てたい。 うん。 非常にこうね、深い意味がありますよね。 うん。 あ、やっぱりいらっしゃるというとこは特になんか印象的だったんですけれどもキャメルさんこのすナさんのお話をこの方の戦争ご一集に載せるとしたらそのタイトルキャメルさんどんな風につけますか? なるほど。わかりました。はい。 これでしょうかとかけらけ ていうものだと思います。ま、死の中にもかけという言葉があります。ま、泣き柄となってこれは 6月に亡くなってるので夏ですね。 え、母の元に戻ってきた彼の本当にいろんな闇、包まれて闇をかけらと見なしてるわけですけれども、 ウクライナは実際に断片壊れかけた町人の心言葉自体が本当にかけらになってるわけですね。実は私はスエラナさんに会した時にあるこういうこにありますけれども、ま、文字取りかけらを託されて日本に帰ってきました。 あ、これがその託された現物ということですね。 え、はい。これ何かと言いますと、え、ウクライナの南マリポリという町がありますけれども、これはもう大変な戦いがありまして、今ロシアに潜入されているわけですが、ま、国民的なあの画家ですね、女性の方がそこに大きな素晴らしいモザイクを、え、描いているんですね。鳥を描いた本当に自由なあの、あの、もうイメージでこの鳥がこう空を飛ぶ。 [音楽] うん。これがその そうです。 はい。で、で、これがですね、破壊され まして、今誰も近づくことはできません けれども、再現をしていまして、1つ1つ のピースを、つまりかけらをですね、作っ て、今は誰もがあの、そこに近づくことは できませんけれど、そのピースを全部 200数十人に、ま、こういう形で分配を しまして、え、この町が戻った時に解放さ れた時に全員がこれを持ち寄ってこの作品 を作 ということで託されたわけですね。多分 1番遠いところに今あの日本に シャベルさんもなので参加してこの絵を完成させる 1人になるっていう。 あの、ま、その責任と言いますか、ま、私にとってはそれ嬉しいあの義務と言いますか、そういうことになったわけですけれども、是非これは日本に持ち替えてこのかけらの意味をですね、日本の方々に伝えてほしいというあのことを言われましたね。 うん。 実際にそのお母さんですね、すトラナさん。ま、これを託されてで、先ほどのあの取材されたというかお話を聞かれた時の映像を拝見するに うん。 うーん。 表向きは少しこうね、落ち着いて淡々とし ているようにも見受けられはしたんです けれども、そこから紡ぎ出される言葉と いうのはやっぱり所々にね、その激しさと いうか うーん、 割りきれなさというか何か何かこう表情 から読み取れないみのが感じられたんです けど、実際お聞きになってどうですか? あの国民的作家である人でもいらっしゃる わけですね。是非お会いしたいと思って、 えっと、ま、友人を通してあの申したん ですけど、最初に断られたんですね。もう 本当にあ、今年2月にあの、え、長男が なくなっていて、それ以降はもうほとんど 社会からもう一方引いて、え、ディニプロ 側の向こう側にあの別荘があって、そこに もう身を、ま、寄せている。 誰とも会っていないということで、でも、ま、せっかく日本から、え、ま、人が来るので来てもらうことができれば、来てもらえれば会いますということで、 え、街から2 時間ぐらいあのかけて訪ねてそこで本当に半日大変実は温かい鑑定艦隊を受けたんですけれども、こ野さんがおっしゃるように大変深い傷を心にあの、追ってることは、ま、今ちょっと元気な毛なげな表情を見せてると思います。 ますけれどもやっぱり ずっと一緒にいると言葉がこう止まったり犬をこうやっぱりこう眺めるこのままざしがとても悲しげでその犬自体がちょっと今あのあまり健康状態が良くないのでもう 1 日でも早くまくあの犬と一緒にいたいということでした。 うん。だからお母さんとしては 2人の息子なくした。そしてその 2人の息子の思い出と繋がる犬 今はその命の危きにも うん。胸を痛めてる可能性があって うん。ま、子供たちのそのに命の子として犬をずっと買ってて、そもそも犬を買いたくなくとお母さんが忙しくて、あの犬はダめよっていう風に言われて、でもじゃ、じゃあでも買いますっていう風に先ほど紹介がありましたように飼ってあげたら皮肉なことにあの犬が残っていて息子たちがこの世にいないという [音楽] ことなんですね。 でも彼女はとってもあの活動あの本当に毎談革命 2014 年の時からずっと市民活動して自由にこの国が平等であの民主主義的になっていくっていうの家族ぐるみで活動をしていたので [音楽] うん。 ただやっぱりこうま、静かにあのこう静かな暮らしを送るだけでなくてやはり何かこの息子たちのために 基金を作ったりことをですね、ま、これからは活動していくっていう風におっしゃってました。 では続いては戦争によって体を傷つけられた人の日常をご紹介します。 キャンベルさんは首都にあるショッピングモールを尋ねました。ここは私たちの文化芸術スペースです。 案内してくれたのは戦場で大けどして両手 より先を失った 元兵士のエゴールさんです。 彼は国境警備隊の兵士でしたが、以前から セラピーやカウンセリングをする仕事をし ていました。 そのためこのリハビリセンターで彼自身もリハビリをしながら怪我をした後輩たちの治療やビリをサポートしています。エゴールさんが負傷した時の様子を語ってくれました。 部屋で勤務前の休憩を取っていたところ建物の隣で爆発が起き、私がいた部屋に火が移ったんです。 何かが起こったと気づいた瞬間、銃声のような音がしました。目を開けるとせやは煙と炎に包まれていて、呼吸も困難で方向感覚も失ってしまいました。それで火傷を追ったのです。 負傷者が社会復帰するためにこのリハビリセンターで特に力を入れているのがアートセラピーです。 [音楽] Aや峠や学などを学ぶことができます。 [音楽] エゴールさんは粘土を使ってユニバーサルなデザインのお皿を作っています。この施設の最大の特徴は一般の人々が訪れるショッピングモールの中にあえて作られているところです。 [音楽] しかもモール内には自分たちが作った作品 を売る店もあります。 自分たちが店頭に立ち売ることによって 社会との接点を保っているのです。 彼がここで学んだ1番大きなことは人と人 、人と社会の関わりだと言います。 人間は非常に社会的な生き物です。 のには外部世界の人々とわる必要があると思います。しかしただ手をこいて人生に何かが起こるのを待ってるだけではいけない。重要なのは全身行き続け目標を追い求めることだと思います。本当にねゴールさんは大変な傷を追っていながら人と人と社会が繋がってそこでやっぱり自分が目標を持ってやることが大事なんだ。 だっておっしゃっていて、非常に前向きな姿が印象的だったんですが、この前向きさってキャンベルさんから見るとどういうところから来るものな。 いや、あの、重症を追っているわけですね。子供が見て本当に怖がるような、ま、その要望に変わってしまったわけですけれども、彼は私を迎えるために大通りに出て私が来るのをもう待ってた。たがりの中で待ってくれてたんですね。 [音楽] 彼らはやっぱり辛いきついあの、ま、訓練 いろんなリハビリを、ま、耐える一方では 実はこの施設の中でポドキャストを作っ たり、ま、写真を自分たちで撮っていたり できるだけこう社会に発信をするような ことをもう半ば自分のあのリアベリーの 一環としてやってるわけです。社会を彼ら 多く受け入れるために変えないといけない ということを彼らは、ま、身を持って 分かってるわけですね。 本当に頭が下がるあの活動をずっとしていて、私がちょうどあのそこで買ったあの T シャツをあの今日持ってき、あの来てきましたけれども本当に素晴らしいあの活動ティノびというあのあの施設ですけれども はい。 [音楽] ウクライナ北東部の最前線にある第 2の都市。 この町はロシア軍の進行投く傷つけられてきました。 [拍手] 歩道の脇に大きな穴が 開いてえます。私が今のが春集合住宅だったわけですけれども、 [音楽] 攻撃で破壊された建物は板で簡単に修繕して再建の目度が立つまで放置されています。 [音楽] その壁や窓、橋などに絵を描き続ける アーティストがいます。 ガムレット人キブスキーさん。 ギャラリーでの展覧会よりも好きな時に 好きな場所でかけるストーリートアートの 方が市民の傷ついた心にとって重要だと ガムレットさんは考えています。 こちらの作品にはリラックスするには家に いることが大切と書かれてあります。 [音楽] 鏡を眼鏡のレンズとして使ったこちらの 作品には 真実を見ようとしているという言葉が添え られています。 [音楽] 戦争は街の姿を変えてしまうけど、私が手 を加えることでさらに違う形に作り替えて いるんだよ。 建物が解体されるとガムレットさんの作品 も消えてしまいます。 しかし町が再生するまで人々に希望を与え 続けます。 主報がなり始めました。え、私がここへ来 てまだ24時間経ってないんですけれど、 え、3度目の、え、空習警報。 そんな中、キャンベルさんはシェルターと して使われていた地下のアトリエで子供 たちに絵を教えている 芸術家の元を尋ねました [音楽] 地下室の壁という壁はミコラ先生のアート や子供たちが書いた絵でいっぱいです。 ロシアの攻撃のせいで学校に行けない子供 たちにとってここは大切な居場所となって います。 また1 人と子供たがやってきます。各々が書きかけた絵を取り出し、自由に政策に取りかかります。 5 年間通い続けて美大生顔まけの生徒もいれば言葉は発しませんが懸命に色を重ねる自兵症の子供や障害を持った子供もいます。 僕は私にとって天国のようなものです。なぜなら本当に幸せな出来事がたくさん起きているからです。子供にとって全身の一歩となるような仕事。そしてその中で子供が成長していく姿を見られる。私にとっても生命力が見なる感動が得られます。 [音楽] 彼女はミコラさんが素晴らしいアーティストと太鼓板をすこの教室のスターです。地下という安全な場所に立っていることが大好き。そして自由なところも大好き。先生や他の生徒たちと一緒に絵を描くことでる知識も大好きなの。 [音楽] 芸術は人々の心のシェルターとなっているのでしょうかね。非常に激しい攻撃にさらされたまハの様子っていうもの今映させていただいたんですが、あのキャンベルさんからウクライナの方々にお土産を持っていかれたということなんですが そうですね。 あの、ま、ここにありますけれども、えっと、野半島の地震で、ま、まさに傷ついた、あの、割れてしまった焼きの破片が、ちょっと裏返すと分かりますけれども、こう [音楽] 1つ1 つこう別々のものからこれは金次ではなく呼び継ぎなるあの部分からこう 1 つのもの、こう形、形づるものなんですね。 これを、え、数枚あの職人たちに作って いただいて、あの、ま、日本からの連帯感 やあの、レジリアンツのそのシンボルとし て差し上げました。それからかけらがこう 入った、え、橋置きをですね、たくさん 持っていて会う人、会う人に差し上げたん ですけど、とっても感動されたんです。 ま、すごくこう通じるものを感じましたね。 やっぱりその破壊されたもの、バラバラになったものがもう 1 回そのなんて言うんですか?ユナイトするというか、こう連帯するということが 象徴されているからこそ伝わると。 実は私の知人であの小説家有名な小説家がいるんですけど、彼は数年前に金杉っていうその名のあの短編小説を書いてて、ウクライナがもう金の国家だっていう風に、ま、書いてて、こう傷がこうたくさんがあって、その傷をこう隠さずに これからちょっと生きていこうということで、まさに金の精神 のようなものでウクライナになってるわけですね。え うん。 あの、金っていうとこの半島でこの傷ついた方々の思いっていうのもなんかその一緒に届けるようなことがそれは とても嬉しかったんです。はい。 それにあの、ま、とめることなくできれば、えっと、彼らの経験や思いを、ま、日本に持ち帰りたいっていうことで、私の友人で、あの、報道写真家でアーティストの女性の方が 7 月の31 日にあの、勇で大希望な、ま、空習があったんです。 くの方くなったわけですけれども、その、え、一見の集合住宅に彼女が命、ま、足を踏みれ、ま、そこでもう破壊された生活の現場からたくさんのあのお皿割我れたこういうかけをですね、あの回収をして私に託くしたんですね。ま、その一部をですね、今ここにお持ちしました。 このウクライナのあの伝統的なあの花の衣装ですとか本当にこう庶民が使うあのお皿の一部ティポットですとかこれからあのま和島のえあの職人たちにえ持っていきましてちょっとこのエジをちょっと柔らけるように金を施こうしてま日本で展住をした後にウクライナに返すていうちょっとそういうサイクルと言いますかをま流の 1つのやっぱりまきっかけを ま、破壊されかかった傷ついてはいるけれども実は壊れていないアンブロークなこういうものを通して、ま、深めていきたいなという風に思ってます。 今日これお話聞いていてですね、私この本 をこう読んでた時にあのアートのね、ま、 今あのVTRご覧いただいたところは まさにそのアートの力の象徴なんだけれど も一方でここ読んでいくとこの戦争のと いう状況の中でこのアートが必要なものは 人はどこにいるのかこの状況でその アーティストである私に何ができるのかと いった疑問をねそのうん 口にしている方もいらっしゃっただの ところはまその あとや、そうじゃない。やっぱり必要なんだってことになるわけですけども、実際にそのキャンベルさんがウクライナされて うん。 分かったことというか気づいたことってどんなことですか? いや、まあ、あの、もちろん移植中や、あの、ま、医療の薬品ですとかそれそのように、ま、そういうものに並ぶわけではありませんけれども、ただ人々の心のですね、の安寧 均衡を取り戻したり、特に負傷した人、トラウマを、えっと、おった人たちが自分に何が起きたかっていうことを整理するために絵に描いたり、あの、自分で語を作ったり書いたり [音楽] 戦士の声っていう実は文学のシリーズがですね、え、あの怪我をした人たちの自分たちの物語を書くように今あのワークショップが全国であの起きてるわけですね。絵もそうだし先ほどエゴールさんのようにま、運動能力ですとかえっとま知能機能ですね。 そういうものを回復させるためにもアートセラピーっていうことは非常に重要ですが、子供たち今あの見ていただいてるように子供たちが今対面で教育ができないんです。コロナからずっと教育を小学生、中学生がわけですね。 そうするとこのま、ミコライさんが子供たちが集まるこれは地下にあるので安全なシャルターという場所ですけれども、え、集まってこの思い思いの絵を自由にかけるっていうことが実はこのアウトがこの子供たちのためにとってはですね、とってもこれ多分これはもうご飯の次に大事なものじゃないかなっていうことをあの感じました。 うん。 うん。 本当にあの戦争のですね、傷ついたその心や体にその何を私たちができるのかって言った時にやっぱり何か最初食べ物だったり切るだったり日用品だったりっていうところはもちろん必要なんだけれどもうん 結局のところ心にそれがねどれぐらい届くかっていう意味ではやっぱりアートの持つ意味ってのはすごく大きいんですね。 思いますね。あのガムさんがえっという壁にもう今もう絵を描き文字を書きつけてるわけですね。 もう数十 枚をもう中にま、ベニアンの上に書いたりそれがなくなる実は解体したらもう彼のアートがもう消え消えちゃう [音楽] 消えちゃうていうことを分かった上で今それが 地域の人たちに記憶をとめるそれを換起するそれから自分たちは 1人ではない1人1 人が味をとめとめて語り合うきっかけが自分のアートだっていうまさにソーシャルですね。 インフラとしてアがウクライナで動いてる。我々は今平和幸が世の中ですけれどもそのことをやっぱりあり方ということを あのもちろん共容としての芸術文芸ということは重要だと思いますけれども 一層こう根源的なやっぱり力をこう発揮できるものだっていうことをやっぱり知るそういう告きっかけになれるんじゃないかなていう風に思います。 今日はね、この戦争ご一周というこの 1冊をうん。 翻訳されたロバートキャンベルさんにお話を伺いましたけど、上野さんいかがでした? はい。あの、戦争が日常になるっていうことが、ま、この死の中でもよく分かったんですが、私はその戦争が日常になる、つまりそれに人間が慣れてしまうのって逆に言うととっても怖いことだなと思ったんです。 うん。 だけどなんだかロートさんのお話を聞いてるとそのもちろんそういう怖さもあるんだけれどもその中で社会をきちんと立て直して 心の傷と向き合って社会全体がそれをこうなんていう包み込んで再生していこうっていう前向きな気持ちっていうのが皆さんになんかあるんだなっていうこれがとっても希望だなと思ったんですよね。 このアンブロー君っていう言葉ありましたけどね。 傷ついて本当に痛みをみさんが大将 こう体に心に覚えているんだけれどもそれでも決してえ うん。倒れることはないというか はい。そしてもう1 つがあのなんて言うんですかけらということをですねキーワードとして出していただいたんですけれども バラバラになったものがもう 1回1 つになるってそこをやっぱり最終的には うん。 目指していると言いますか、目標に持ってるウクライナの方々のこの強さっていうのがまた非常に印象的でうん。 あの、ウクライナ戦争始まった時からウクライナの方々ってすごくこの式が高いっていうのって言われていましたよね。なんかその式の高さと今回そのかけらが 1つ1 つまた集まっていく気持ちの強さっていうのが私は重なって 非常に強いなという風に感じました。 なるほど。ま、あの、私たちどうしてもね 、その戦争の記録って国と国の記録ね、 政府と政府の記録、そういうのが多くなっ てしまうんですけども、この本はですね、 戦争の本質、市民にとっての戦争ってのを 知る本当に貴重な1冊だと私も独僚して 感じました。うん。はい。是非見ください 。ください。さて明日 は自民党小林高幸成長会長にお話を伺っていきます。 また明日もご覧ください。 [音楽]
2年前、戦時の人々の言葉を集めた「語彙集」に着目してウクライナを訪れた日本文学者ロバート・キャンベル氏。このほど2年ぶりにウクライナを再訪。ロシア軍の侵攻から3年7カ月余り。戦争は、多くの人と物を破壊したが、日常と化した戦火の下、人々の逞しい生活の営みがあった。2人の息子を失った母が詩に託した祈り。両手を失いながらも再起を目指す人々。壊れた建物に絵を描くアーティストや地下で学ぶ子供たち等。戦争が生活の一部となったウクライナの人々…。空襲警報が鳴る最前線の都市をキャンベル氏はウクライナで見た。
ゲストは、今年8月にウクライナを再訪したロバート・キャンベルさん。戦争が”日常”となったウクライナに生きる普通の人々と、アートが癒しになっている生活、ニュースでは語られることのないウクライナに目を向ける。
#ニュース #ウクライナ #日常 #戦争 #ロバート・キャンベル #日本文学研究者 #早稲田大学 #近野宏明 #上野愛奈 #10月13日 #語彙集 #ロシア軍 #侵攻 #戦火 #生活 #営み #息子 #詩 #母 #アーティスト #戦争 #空襲警報 #最前線 #インサイドOUT #BS11

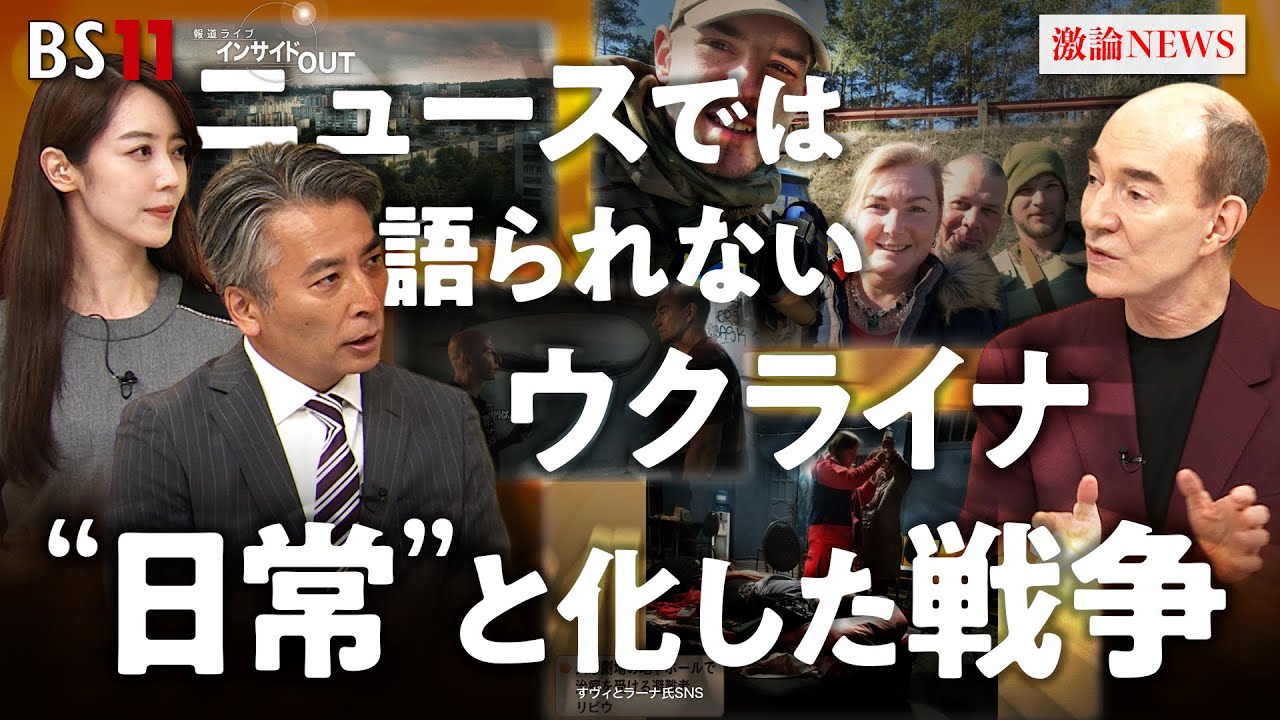
4 Comments
この想いプーチンに届けよう。
イスラエルとパレスチナに和平を実現させたトランプ大統領にウクライナにも平和を実現させてほしいな。
なんで戦争の現実もそこそこにアートの話ばっかしてるの?
とても良い放送でした❤❤
キャンベルさんの仰る言葉の変容にしばらく考え込んでいます。
高齢者の土地への愛情や女性にとって大切な髪に使うリンスが放射線吸収剤となってしまう話。
一人の人間の個人で抒情的な語りに、民族集団としての理性的な行動への意志を双方に感じます。
コロス(合唱)が反響しているように思えるのです。
老人は自分の身体的な無力を知っています。お金も新たに生きる能力にも欠けています。
もし言葉の変容を感じるとすれば、そんな二重性にでしょうか。