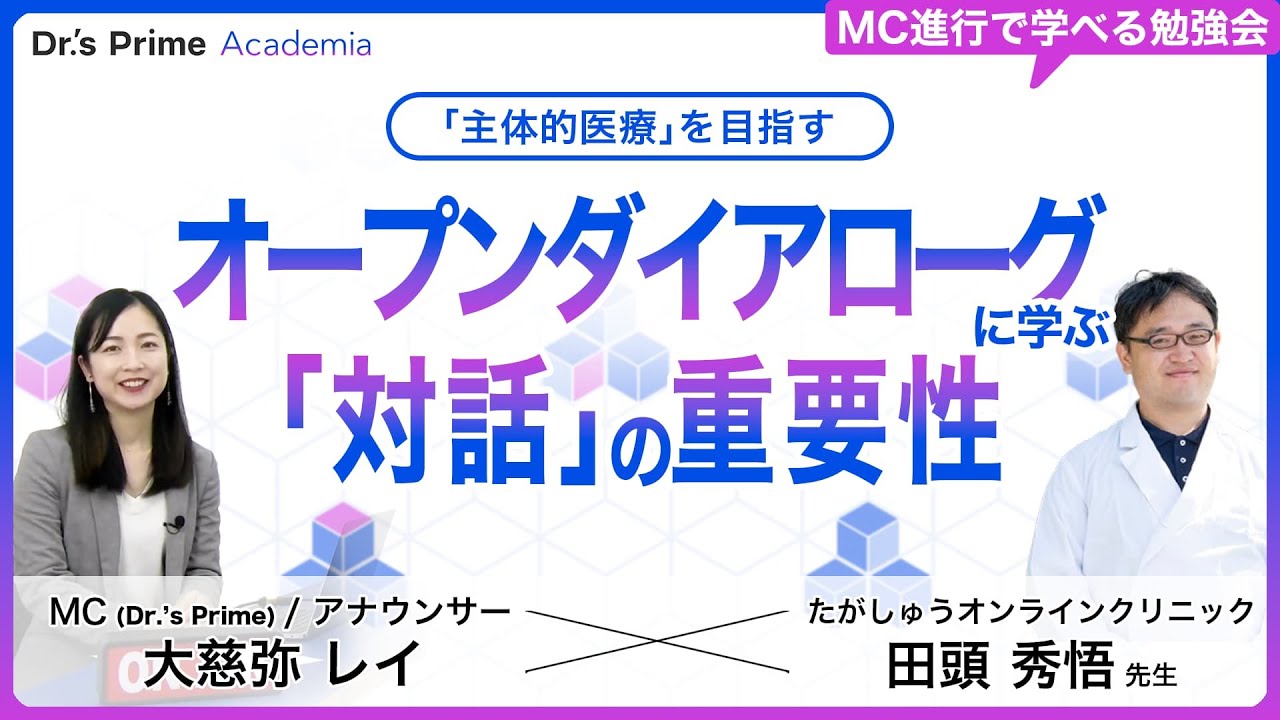「主体的医療」を目指すーオープンダイアローグに学ぶ対話の重要性ー
もう一言で言うと患者さんが主体的になりにくい文化だなと。 実際にどうですか?そのオンライン診療を始めてみて うん。 漫画やってみたくなるオープンダイヤローグというね。 [音楽] おお。 そうです。あの これは医療の現場ではどういう感じになるんですか? はい。不確実な状況に耐えましょうっていうのは、 あの愛に結論出さないってことですね。 ある意味治療しないっていうのも患者さんの選択ですもんね。 うん。そうなんですよ。 うん。 治療しないも選択肢ですし、また治療したくなった時に受け入れるも選択肢なんで。 なるほど。 [音楽] 皆さんこんにちは。ドクターズプライムアカデミア MC の王子レイです。今日は田頭先生にお話いただきます。よろしくお願いいたします。 はい、今日もよろしくお願いいたします。 お願いします。 はい。主体的医療シリーズの第 2 回ということでお話しいただきたいと思います。 ま、先生は主体的医療という言葉は、ま、ご自身で うん。 訴えられているということなんですけれども、 改めてこの主体的医療についてお話しいただけますか? はい。 体的医療っていうのは私の造合なんですけれども、 え、既存の医療が、ま、ちょっとお医者様にお任せになりやすい医療であることに対する、 ま、カウンターパートというか、 ちょっとそれに対する大義後のような位置づけで、 え、作りました。 うん。なるほど。先生から見てこの日本の医療っていうのはどういう文化だと捉えていらっしゃいますか? うん。 もう一言で言うと患者さんが主体的になりにくい文化だなと。 うん。 うん。そういう医療がすごくあるなと思ってますよ。 これどうしたら患者さんが死体の医療っていうのが実現するんですかね? うん。これ難しいですよね。あの、じゃあ今からあなた体的になってくださいって言ったらもうそれなったとしたら受的ですからね。それは そうですね。なでって言われてしまった。 分かりました。なりましたって言っ言ったらもう自動的ですから。 これ意外と難しいですね。私も実はあの [音楽] すごい今でもあのこれといった正解があるという状況ではないんですけれども え、ま、色々ね、こうヒントになる言葉はあのあるんです。 はい。 え、例えばあの中国の 思想家で純というはい。 え、方がいいけれども、その方の有名な言葉があるんですよ。はい。 うん。 あの、聞いたことは忘れる。 はい。 見たことは覚える。 え、そしてやったことは分かるっていうね。 ほう。 うん。つまりこう何かを患者さんにやって欲しいなと思った時にですね、それをこうじゃあ伝えますと。 うん。 え、伝えたらですね、そのまま患者さんすぐやると思いきですね。 うん。 ま、大抵の場合は忘れるんですね。それで なるほど。聞いて家に帰ると忘れてしまう。 もう忘れてるっていうね。え、よくね、思い当たることもあるかもしれませんけど。 はい。 え、じゃあそこからどうすればね、あの、主体的になるのかっていうのはやっぱり本人に委ねられてるんですよ。 うん。 そこからあ、聞いたなと聞いてで、例えば同じ話がまた違う場面でもう 1 回入ってきて、あ、そういえばなんか見覚えのある話だなと。 うん。 ああ。で、だんだん記憶に定着してきて、で、そしてちょっとやってみようかなと。 うん。 やって初めてですね。 ああ、これはいいかもしれないって思い出して自分の中で定着していくっていう、そういう流れがあるよっていうことを、ま、純子さんは言ってるんですよね。 え、そこでですね、私があの注目したのがあのオンライン診療という はい。 このやり方です。 ま、高州先生は実際に高州オンラインクリニックを開されていらっしゃいますよね。 はい。そうなんですね。なんでオンライン診療で開業しようかなと思ったかと言いますとですね。 はい。 まずその病院だとこう普通はそれがメリットだと思われるんですけど、この主体性の観点で言うとですね、受け身になりやすいんです。やっぱり こう目の前にお医者さんがいて でなんかこうやっぱり難しそうなこと言ってで患者さんはもうそれね信頼してますから ね。そこでじゃあお任せしますっていう感じになりやすいんですけどうん。 オンライン診療の場合は効果不効価この距離感があります。 はい。直接触ることもできません。 で、色々こっちから言うわけですけれども、その言ったことを、ま、あの、その恩恵を受けるためにはですね、やっぱり患者さん自身が頑張ってもらわないといけないという、そういうちょっとある種依存心を減らすようなですね、 そういうところがオンライン診療という診療形式自体にあるんじゃないかなと思いまして、 ま、わば普通の人が、えっと、デメリットだと思うとこう、私はメリットなんじゃないかなという逆手に思ったわけです。 はい。 ま、確かにこう病院の診察室って密室ですから、こうそこで迫られる判断と、ま、自宅とかこう慣れた環境でこうね、迫られる判断ってまた気持ち的に患者さんも違いますしね。 うん。そうなんです。うん。 それの場所っていうのもすごい大事で、あの、在宅診療の時とかも同じ発想がありまして、え、 あの、い、家のね、自分の住み慣れた環境の中で考えることと、あ、もう白い壁だらけのね、その白来たお医者さんがね、こうといるような状況で考えることはやっぱり違います。 なので、あの、そういう、ま、自分が主導権を持ちやすい、え、環境で診療することができれば主体性が育まれるやすいのではないかなと。 うん。 思いましたね。 うん。 実際にどうですか?そのオンライン診療を始めてみて。 うん。うん。 これがね、あの、うまくいくかなと思ったんですけど、残念ながらなかなかあの、主体性が育まれるという私な、私からの手応えがあまりなかったなかったというか、まだ今もやってますけれども はい。 ま、今のところまだないなっていうとこですね。 うん。どういう点が難しいんですかね。 はい。 まずはあのなかなか続かないっていう、 あの最初はあの物珍しさもあってあるいはどうしてもそのえっとその都合がね、つかないからオンライン診療だったら受信できますみたいな人がこうオンライン診療を使うはいいんですけども はい。 やっぱり、あの、さっきの聞いたことは忘れるじゃないですけれども、あの、 1 回だけであの、終わってしまって、ま、やっぱりつものタイ面新料に戻るとかいうパターンの人が多いっていう、 つまりその何回かね、こう主体性に発展していくためにはこうそこで思考錯誤をしなきゃいけないんですけど、そもそもそういうステージまであの、いかないと うん。うん。 あるいはあの、ま、そん大半は 1 回で終わる人ばっかりなんですが、中にはあの何回もオンライン診療してくれる方もいるんですが、 その方はその方で、あの、結局、あの、いつものお薬をくださいというか、 あの、ま、病院でやってることとなんら変わらないと言いましょうかね。そういう感じで うん。 うん。 私が思ったほどあの主体性が育まれる現場にはなってないなっていうのが正直なとこですね。 [音楽] なるほど。 ま、それね、こうオンライン診療っていうのはこう全身的な取り組みなので難しいところも色々あるかとは思うんですが、 こう乗り越えるために何かこうトライしていることだったりっていうのはあるんですかね? はい。色々ね、あの情報をそういうこそ集めるんですよね。 あの、もう哲学の話から、心理学からね、全然関係ないとこにヒントがあることもありますから。うん。 そうやっていろんな本を当たってる中でですね、 1つあの、いい本に出会いまして はい。ええ。 うん。これはね、あの、ちょっと出してもらおうかな。この、え、漫画やってみたくなるオープンダイアローグというね。 はい。お、 この本なんですよね。 オープンダイヤローグ。 うん。聞いたことありますか? あの、ダイアログっていうのはこう、それこそう 会社の中で対話しましょうみたいな営業のところでちょっとお話聞いたことがあったりするんですけど。 うん。そうです。あの、 これは医療の現場ではどういう感じになるんですかね? はい。あの、そうですね、ダログっていうのが今おっしゃったように対話という意味でね。 で、オープンダログは直約すると開かれた対話になりますが はい。 これはですね、あの、え、医療の文脈で言うと、え、ま、精神化の領域で、あの、ある種取り組まれてる、あの、 え、ま、ケアの技法と言いましょうかね。あの、 はい。 え、これはですね、フィンランドという国であの生まれたやり方なんですけれども、 あ、 え、ま、 3人以上の、え、メンバーが集まって で、ま、患者さんと医療者と、ま、患者さんの家族の場合もありますし、医療者と、え、看護師さんとか、ま、別のスタッフっていうこともありますけど、とにかく 3 人以上でやりましょうっていう試みで、そこで、 ま、それこそろんなことを対等な立場で、え、ま、話 え、ま、ちょっとね、一言で言うとすごく難しいんですけども、あの、すごく穏やかな雰囲気で、 え、なんていうか、今までだったら、あの、え、あんまり話せなかったようなことが話せるようにする工夫が、ま、たくさん施されてる、ま、そういうあの営みなんですね。オープンダログっていうのは。 はあ。 で、このオープンダイヤログにすごい主体性をについて考えさせる ヒントが、あの、やっぱり図一緒にあったんですよ。 ええ。 うん。 で、この、ま、まずそもそもね、これ漫画 の本でとっても読みやすいんですけれども 、その漫画の中にあの解説文章みたいなの もあって、そのある文章に私はすごくこう 、あの、引かれ、引かれたというか、ハッ とさせられたんですけど、2社というのは 非常に人口的で、え、不自然な関係だって 書いてたんですね。え、そしてまず化し やすい、それから教存になりやすいんです よ。ああ、2者関係っていうのはもう1対 1で合っているっていうことですよね。 うん。そうです。そうです。病院だとそれ当たり前じゃないですか?医者と診察室 診察室の状況ですよね。 まししてあのオンライン診療の場合は さらに密室空間というかそのオンライン空間でね、あの誰も他の人が聞かれないような状況でやりますからもう密室なんですよね。 うん。そうですね。 ではつまりあの密室をより作ってたんじゃないかと。オンライン診療やっててですね。 [音楽] うくいかなかったのは、え、むしろその密室空間においてですね、 2 者関係のこの特別さで、え、より上下の換気が強化されてしまうことに、え、規制してなってしまってたんじゃないかなっていうことをちょっと [音楽] 考えさせられてなるほど。 [音楽] じゃ、そのオープンダイアローグっていうのをオンラインの中でこうトライしていったようなイメージなんですか? そうなんですけど、あの、今のオンライン診療ではやっぱりできないですよ。その要はあの、 そんなにたくさんね、あの、一緒に患者さんと誰か他に一緒にいてくれるとは限りませんし、私の方も私の方であの、 [音楽] 1 人しかスタッフがいないんです、実はね。 うん。 オンライン診療のはできないので、 あの、あ、別の あの、仕組みを作りました。 あの、自分でそのオンラインでやるんですけど、オープンダイヤログをやりますよって私があの、え、イベントを計画してですね。 で、そこに、ま、集まっていただいた、ま、あるし、ちょっと不特定の うん。 うん。方々に集まって、私の活動に興持ってくれてる方に集まってもらって、ちょっと練習のような感じで はい。 はい。あの、患者ってわけじゃないんですけれども、ま、ちょっと自分の軽い悩み事みたいなのを題材にしながらちょっとオープンダイヤログ的にやってみようよって。 へえ。 いうことを何回か繰り返してましたね。 それをえっとオンライン上でたんです。 オン。はい。 へえ。 すけのべ300回ぐらいやりました。 あ、そんなにたくさん開かれてるんですか? はい。はい。 それやっていく上でのポイントっていうのはどんなところなんですか? あのこの本にも書かれてて、あのよく 7つの原則というのがあるんですけれども うん。 ま、ちょっとそれぞれ結構大事なんですけど、あの、もうその触りだけちょっと今日は紹介しますが、 まず1つ目は即自援助。 え、困った人が出てきたらもう即集まりましょうっていう、そういう発想ですよね。 それから2 つ目がソーシャルネットワークの視点。 うん。 え、これは、え、患者さんからしたら家族とか、ま、仕事が絡んでそうだったら仕事の関係者とか、ま、あの、この 2 人だけで話の話にこう関わるネットワークみんな巻き込みましょうっていう発想。 それから3つ目が柔軟性と起動性。 え、ま、あんまりそういうこと常識にあの、あのこらず、あの、なんて言うんでしょう?あの、囚われずにですね。そう、そう、そう、そう。 [音楽] 囚われずにこう柔軟な発想で、ま、例えばあの家でオープンダイヤログやりたいったらあのそこに向かうとか、あ、これはだからオンラインの話じゃなくてフィンランドで実際の現場でやってるパターンですけどね。お家でオープンダイヤログすることもあれば、ま、患者さんが病院に来るパターンもあるし、全然違う市役所みたいなとこでやるってこともあるしてっていう。うん。 ま、柔軟にやりましょうねと。 それから4つ目が責任を持つっていう。 これはあの、ま、私たちの練習の場では、ま、誰が来るか分からないので毎回メンバーが変わりますが、ま、本場のフィンランドの場合はあのスタッフがね、 1 度関わったらあの落ち着くところまでずっと関わり続けますよっていうその連続性を、あの、あ、それは 5 番目の心理的連続性ってとこにも繋がるんですけど、責任を持って、 え、連続的に関わることで、ま、そこにいる人たちみんなが安心できるような状況を作る。 うん。 そして6番目と7 番目が私的には大事だと思ってるんですが、 6 番目が不確実性への体制と ほう。 これあんまり聞き慣れない言葉かもしれませんし、聞いたことある人もいるかもしれませんが、え、不確実な状況に耐えましょうっていうのは [音楽] うん。 あの、安易に結論出さないってことですね。 ああ、これは絶対こうだみたいな結論を 急がないっていうことですね。 うん。そうですね。うん。 例えば、あの、こうつ、うつ病で悩んでるみたいな人がいた時に はい。 え、それはもうエビデンス的に薬を飲んだ方がいいからもうとにかく薬を飲み始めましょうみたいな。 うん。 簡単なんですね。 そうするとこう一応根拠もあるしみたいなことでそういう決断になりがちなんですけどやいやちょっと一旦それは置いといてその選択肢もいいですけれども他に選択肢ないでしょうかみたいなことで、 [音楽] ま、色々こういろんな人たちの意見を聞きながらあの、ま、ちょっとゆっくり考えていくみたいな感じですね。この視点がですね、主体性を育むのには すごい大事なことだと思ってます。 うん。 うん。 そして7つ目の原則が対話主義と はい。 これがね、対話っていうのが、ま、今もまだ分かりきってないとこもあるんですけども うん。 ま、1 番は対等な立場で、え、医者と患者がこう同じ目線でと言いましょうかね、え、エビデンスで押え付けるみたいな感じじゃなくて、あの、患者さんが持ってる情報も、あの、引き出してで、同じ素上に載せてですね。 で、その中でどれがいいかなをこうみんなであの常識に囚われずに考えていくみたいな感じなんですね。 うん。 だから世間でもこうダアログとか対話って言葉はあのよく言われてるとこだと思うんですけど [音楽] うん。で、それがいいよとも言うんですけど、ま、ここで言うダイヤログはなんていうか、もうちょっとこう、え、本質的となんて言うのかな。こう深いというか うん。 うん。 あの、人間の生き方そのものみたいなこういう生き方をするとみんなあの、こう固定観念に縛られずに、ま、あの、苦しんでる人にしてみればですね、あの、 ちょっと自由に 発想を、ま、それこそ主体的に選んでいくことができやすくなるっていう。そう、そういう場作りというか、 うん。 それが対話主義の意味するところかなって思ってますけどね。 なるほど。うん。 ま、あるこう心理的安全性が保たれた上でこういんな発言をしたりとか考え方を共したりできる場が、ま、オープンダイヤログの場みたいな感じなんですかね。 はい。そうです。そうです。そういう場でこう出てきた意見ですね。 そしてそれがなおかつあの自分からその患者さん苦しんでる患者さんからこうしてみようかながもし出た日にはですね うん。 うん。あの、それはさっきの純の話じゃないけど、あの、身についていくっていう うん。 そういう流れ。ま、つまり主体性の目があの、生まれていくっていうね、 こういうことを、ま、 ただ難しいのはそれをあの、あの、導いてはいけないんですよね、またね。 うん。 それそこが不実性の体制になってきまして、 結局そういう風に 誘導してはいけなくて うん。 え、ま、仮にね、その悩んでる人の中で何のアイデアも生まれなかったとしてもずっとあの付き合い続けるんですね。 うん。 で、今日はもう疲れたってなったらもう明日でもいいしで、その明日付き合うかどうかも本人と一緒に決めていくって感じでうん。 ま、気の長い話なんですね。 うん。 で、このままずっと続けて答えが出ないかもしれないんですね。 だけど一緒に付き合っていくようなこの心理的な 連続性であり安全性がうん。 ま、ある時突然こう、あの、その人の主体性をバッとこう育組むのにいいんじゃないかという、そういう考え方ですね。 うん。 ま、今のお話伺っていると、ま、いろんな患者さんがいらっしゃるとは思うんですけど、こう精神疾患の方だったりとか、ま、そういった方にもこの対話っていうのは有効だったりするんですかね。 うん。はい。ま、本場のフィンランドでは、 あ、あの、精神疾患の中でもかなり重症だと言われて、あの、統合失張症という病気 はい。この病気の方にも試されて はい。 で、え、普通の統合視聴症って病気はあの、あれなんですよ。あの、なかなか感知するのが難しくて、 あの、基本ずっと薬を飲み続けた方が社会復帰いですよっていう、そういう難しい病気なんですけど、 なんとね、その統合視聴書にの方にオープンダイヤログで関わっていくことで薬をやめることができたとかね。 へえ。 え、あの、続けたとしてもぐっと減らすことができたとか、そういうすごいいい治療成績が出たっていうことでも有名になったんですね。 これなぜ対話がオープンダイヤログが統合症の方の、ま、改善につかったんですかね? うん。 これはね、あの、いろんなあの考え方があると思うんですけど、ま、大きく 3つあるかなと思ってて、 1 つはですね、あの、従来の医療だとその統合書の患者さんっていう前提で始まりますけど はい。 このラベルと言いましょうかね。病名っていうのがあの、外される、え、 あ、ダイヤログの場では 患者として見ないみたいな感じ。 そうですね。 あの、なんとかさんという呼び方もね、ま、あの、お医者さんが先生と呼ばれるのもやめましょうと。 はい。 なんとか3 同士で行くっていう、ま、細かいルールもあるんですけれども うん。みんなが対等な立場ということですよね。 はい。その中で両名もあの、こだわらないというか うん。うん。 え、一体あなたの中で何が起こってたのかっていうのをね、もう周りの人たちがこう本当に関心を持って聞くっていう うん。 逆に言うとそれはあの東合市聴症と相手をみなすことによる弊害があの要はあの普通の医療にはあるんじゃないかなっていううん。 うん。私は統合症なんだ。だからこの薬を飲まなければならないんだ。 はい。 え、だから、え、治らないんだとかね。そういうこの価値観をある種病院の現場が植えつけてしまってるかもしれないっていうね。 うん。うん。うん。 で、オープン大力はそれ全部っ払うので、 それで治るということはですよ、 その弊害が決めつけることの弊害が 存在したっていうことではないのかなと思いますね。 うん。なるほど。 で、それはあの大きく捉えると、え、症状というものも、え、同じことが言えて はい。 例えば東視聴の方、幻格っていう症状が出るんですね。 そのものがないのに、え、ものが見えてしまうとか、 誰も何もないのに音が聞こえるとか、自分に悪口を言ってるとか、そういう現長とかあるんですけど、普通の医療ではそれは、え、消すべき症状であると、あの、つまり異常であると、 その異常は直ちに是正しなければならないっていう発想で、 え、薬を使うっていうことだと思うんですけど、それも、え、オープンダイオログではしない。 うん。 え、ま、あの、ヒアリングボイスっていう言葉がありますけど、あの、それは患者さんの声の一部ですと。 はい。あ、何が見えるんですかと。え、精神医学の教科書ではね、その現長についてそういう風なアプローチをしてはいけないっていうぐらいあの常識外れなやり方なんですけどうん。 その常識に囚われずにね、あの、それも患者さんの声の一部っていうことで、むしろ教えて欲しいですと。 うん。どんな声が聞こえたんですかとか、なんて言ってましたかとか、それがあったんですかとかいう感じで、 こう丁寧にね、その声の一を聞いていくと うん。 だんだんその患者さんも、あの、ま、人によりますけど心を許してきたりとか うん。 え、また違うことを教えてくれてたりとか うん。 どんどん世界が広がっていくんですね。なので症状というものを異常と見なすこともこれまた弊害があるということです。 はい。 ま、もちろん症状として、ま、あるものではあると思うんですけど、こう捉え方が、ま、すぐにこう見えてしまったとか 聞いてしまったっていうネガティブなワードに変えるんではなくって、ま、その自象自体を受け入れるじゃないですけど、あるしそんな向き合い方なんですかね。 そうですね。なんか、あの、全ての患者さんが言うことは、あの、ただ正しいっていうか、あの、あの、ちゃんとした、あの、ありのままの声なんですよね。 うん。 それを異常だとか視聴の症状だとかっていうラベリングすることが、ま、もう対当じゃないというか、あの、 うん。上から見てるっていうことで、そう、その関係性で何をやってもですね、あの、患者さんはやっぱり負のループから抜けにくくなるっていう、 そういうことかなと。 うん。 あともう1つあの はい。 ポイントがあってですね。 はい。 あの、余白なんですね、ポイントは。 余白。 うん。 と、あの、オープンダイヤログではですね、あの、沈黙を良しとします。 うん。 あの、要は、あの、考える時間ね、なんか沈黙が、今も、今はこの場で沈黙ったら、あの、放送事故になってしまいますけども、あの、オープンダイアログの場ではですね、 [音楽] うん。 例えば、あの、患者さんがちょっとあの、何か質問されてすぐパッと答え出ない時にこう沈黙してしまいますけれども、そん時にあの待ちますね。 そういうそのちょっとその余白時間というかこれはあの時間的な意味もそうだしなんていうかあの空間的な意味でもそうです。なんか圧迫された場所でやる片方が白来てて片方がね普段着っていうそんななんちょっと上下が意識されるような状況じゃなくってうん。 え、もっとあの開かれた空間で落ち着いた場所でなんか飲み物かなんか飲みながらみたいな そういう状況でやるとま、少しこうゆりができるんですよね。 うん。 そういう状況であってこそ主体性があの育まれ、え、そして自分の地由力みたいなものも生み出され、え、東市聴書が治っていくっていうそういうことの可能性があるんじゃないかなと。 うん。それは、ま、3 つはあくまで私の意見ですけど、 他にもいろんな理由があってのことなのかもしれないけど、ま、少なくともそういうことを思いましたね。 なるほど。うん。 いうことだけでも何かこう 1つ前に進むような感じがしますし、 こう主体的に生きるみたいな、こう医療だけに関わらず主体的になんか生きるみたいなところにもつがりそうだなっていう風にはお話を伺っていて思ったんですけれども、ま、先生はこれまでもそのオンライン診療に挑戦されたりですとか こんなことを学んでいらした中で患者さんの死体性を育むためにうん。 これが必要だと思われることってどういうことになりますか? うん。はい。ま、ちょっと今の現実点での私の考えっていうことにはなってしまいますけども、 ま、オープンダイヤルにやっぱり色々ヒントがあったんですよね。 うん。 で、ま、私がここで、ま、 5つあげるならばですね、1 つはあの、今ここにいることに集中するっていうことは、 あの、大事ですね。なんか、あの、えっと 、ま、ま、病気の概念に縛られるとか、 あとこの病気だったら、え、数年後なって しまうかもしれないみたいな、ま、特に それが難しい病気であればあるほどですね 。 患者さんは悪い見通しを考えて不安がすごくよぎってその不安がまた自立神経を通じてね うん。うん。 体悪くしたりっていうそういう悪循環が生まれやすいんですけど、ま、そういう話も一旦あるかもしれないけど置いといて今、 [音楽] え、この場でより良い状況にするためには何ができるかなっていうこのこの今ここをに注目するっていうのは 1つ主体性 ま、患金さんをまあなんていうか前向きにする 1つのポイントかなと。 うん。 今この瞬間をよりよく生きるためにていう感じですね。 そうです。できることを考える。 はい。そして2 つ目はですね、あの互いに尊重し合うことですね。 うん。 うん。 これもさっきの対当っていうのもそうなんですけれども、やっぱりあの上から目線じゃないようにしないとあの患者さんは自分の本当に思ってることが言えなかったりしますのでうん。 でもその自分の本当に思ってることの中の方があ、それこそ自分としてはずっとやっていきたいことがあるかもしれませんよね。 うん。 え、それをこうちゃんと素直に出してもらえるような形にするためにも、え、お互いにね、こう尊重し合うようなそういう、え、コミュニケーションが必要かなと思いますね。 うん。 あと3 つ目はですね、あの、決して押し付けられないことですね。ま、この散々今の、今までの話でも それ伝わってるかどうか分かりませんけども、 私なるべく押し付けないようにあの、 心がけてるんですね。 あの、ま、前回のね、糖質制限色の時も言いましたけども、 あの、あれは私はすごくいいと思ってるけど、だからとして絶対押し付けないっていうあくまでもこうお盆の上に乗せるって言い方をしますけど、もうポっとここに置くだけです。で、もう使ってもらうかどうかはもう患者さん次第ていうそのなんていうか、押し付けなさ具合をいかに表現できるかが患者さんの主体性を損ねない [音楽] 1つのポイントかなとも思ってます。 うん。 あくまでこう意思の立場として選択肢を増やして差し上げるみたいなイメージですよね。 そうですね。で、それをしかもあの、えっと、医療側の都合の選択肢だけにしないというかね。 ちょっとその常識を外すとかさっきのね、その統合症っていうラベルをしないとかいう話も医療の教科書見てもどこにも書いてないんですよ。 うん。だからちょっとその選択肢は いろんな世界から持ってこないとですね。 うん。 あの、本当の患者さんの体性は育まれないとも思ってますね。 なるほど。 だから4 つ目はあの余白ですね。さっきの余白はやっぱりあのオープンダログの中に限らずいろんなとこで大臣されるべきかなと。 うん。 ま、それはさっきのその常識から離れるってことも余白だと思っててですね。 この医療の教科書的というかエビデンスの中だけで考えてると予弱くないと思います。私は だってもう決まってますから。うん。 答えがあるっていう感じです。 そう。もうこのこの答えがあって結論ありきで、え、この治療を受けさせるために患者さんをどうあのすればいいかみたいな話になっちゃうんですよ。 それはもう全然柔動的な医療ですから。 はい。 ま、これは選択肢として置くのはいいですけど、 あのね、だけどあのここに誘導するような医療にはしてはいけないっていう意味で余白を大事にするっていうことです。うん。 ある意味治療をしないっていうのも患者さんの選択ですもんね。 うん。そうなんですよ。 うん。 治療しないも選択肢ですし、また治療したくなった時に受け入れるも選択肢なんで。 あ、なるほど。 あの、不確実践に耐えるの話とすごい通じるんですけど、一旦患者さんが私から見るとすごい非常識なことやってんなって思ったとしてもですね。 うん。 え、決して見さないというか、あ、じゃあまず一旦あなたの言う通りでやってもいいと思いますけど、なんかあったら私はあなたと絶対にあの、あのコンタクト取りますからと いう感じのコミュニケーションを取っておけば 決して、え、もし非常識だと私が正直思うようなことをやってたとしてもですね。うん。 え、ま、患者さんとしては取材的に行けれますよね。 うん。やりたくないわけですから。うん。 確かに医療業界全体でその雰囲気とか上土が気づかれるとそれこそこうセカンドオピニオンのお話とかも患者さんの立場からするとやっぱり死体的に選択をしていろんなお医者さんの意見を聞いてうん。 改めて選択するみたいなところもやりやすくはなりますよね。 そうそうですね。あの患者さんからするとあのなんて言うかな、え、絶対的な正解を求めてる患者さんもいるはいると思うんですね。 [音楽] そのたにセカンドオピニを受するていう人もいますけれども、 ま、そんなことよりももっと重要なことは、ま、あの、自分の思ってることが大事にされるってことですね。 [音楽] うん。 セカンドオピニオンとかにこう行って、え、結構同じ答えが出てね、結局その屋さんとしてはもうそれに納得せたら得ないみたいな状況になることも多いんですけれども、 [音楽] え、それはね、あの、ま、ある種やっぱり結論ありきの世界の [音楽] 話なので、あの、もう本当に大事なことは、あの、いろんな意見が認められるっていうか、 あの、 あるし、それがね、あの、すごく真逆の意見だったとしても、それでも私はあ あなたの味方で続けますってとこだけはあの捨てないというか、そういうことが大事かなと思いますね。 うん。なるほど。 あと最後にこれもポイントだと思うんですけど、こう分かりやすい正解に飛びつかないっていう はい。うん。 うん。 あの、あの、やっぱりガイドラインとかね、あるんでね。 医療の世界がこうね、散々医学論文で研究されてはい。 この治療方針になってますよっていう分かりやすい正解があるんですけど、ちょっと一旦脇に置いていただいて、 え、違うね、統制限色しかり、いろんな他の選択肢、オープンダイヤルしかりというようなことも見ていただいてですね、その中で、え、考えるっていう だからやっぱこれも不確実性に耐えるていうねことの大差を表現してると思います。 [音楽] はい。ま、1 つのこう分かりやすい正解にすぐにこう行ってしまう方がね、簡単だったりする時はありますけど、やっぱりこう広い視野を持って 受け入れるというか、そういった姿勢も大事ですよね。 うん。そうですね。あの、ついついそう、ま、ある種ね、医療はその分かりやすさを追求してきた問と言えるかもしれませんね。 うん。うん。 うん。 ま、今日のお話の中ではこの主体的医療をキーワードに、ま、かなりこう倫理的なお話というか、そういったところもお伺いしてきたんですけれども、この主体的医療を日本の医学会の中に広めていくにあたって先生が大事だと思うこと改めて教えていただけますか? はい、ありがとうございます。もう今日はね、本当に初体的医療をね、こう伝える機会いただいてありがたいと思ってまして。 こちらこそありがとうございます。 もう相まとめのようなことをちょっと最後にね、言わせていただくんですけど はい。 え、まずはやっぱ常識から離れてみるね。 え、常識の中に答えがあるとは限りませんということで、うん、 ま、私はすごくそれを統制限を通じて学びましたし、オープンダイアログもその 1 つだと思います。え、それからあの仲間と一緒に学び合うですね。 はい。 ええ、あの、やっぱりですね、これはあの、ま、当たり前だと思うかもしれませんけど、え、専門を突き詰めていく、ま、お医者さんの中ではですね、あの、やっぱりこう、あの、価値観が、あの、すごくこう狭くなっていくところもあるんですね。タコツ型と言ったりもしますけども、 え、はい。 あの、それは、ま、みんなで学ぶというよりはちょっとあの、 1 つの価値観に縛られるっていう意味であの違うとここで私が言ってる仲間っていうのはやっぱり違う価値観を持った人と一緒にそれでも考えてきるような学び方っていうのがやっぱり自分の枠を外してくれるという意味でいいんじゃないかなと。 うん。あとは、ま、1 人で患者さんが悩んでるような状況もよろしくないと思ってるので、あの、気軽にね、医者と相談できるような、あの、体制も必要だと思います。え、 3 つ目は、え、なぜそうなったっていう原因をしっかり考えるんじゃなくって、それはそれで大事なんだけど、どうすれば良くなるの方も忘れずに考えて欲しいっていうことですね。 うん。うん。うん。 あの、例えばさっきのオープンダログの例で言うと、こう今までね、統合市聴省という病気はあの何が原因かわからない。未だに原因は解明されてないんです。遺伝子が関わってるんじゃないか、生活習慣じゃないだろうかとか、 あ、住金属が原因なんじゃないかとか色々言われてるんですが、 え、それをね、突き詰めて、え、良くなりましたかと。 うん。 良くならないこともあるわけです。良くなることもあるけどね。 だけど、え、オープンダイヤログはそういう原因は一旦横に置いといてどうすれば私たちはより良くなれますかねを、ま、それを話し続けてる糸波だと言えるわけなので、 [音楽] それで実際に統合症というものが良くなってる現実を見るならば、 え、ここのどうすれば良くなるかを考えることは、え、すごく意味があるんじゃないかなと。 うん。 こういうことも主体的給医療を広げるために大事だなと思います。 ま、ついついこうね、過去を掘り下げていく方に重きを置いてしまいますけど、やっぱ未来どう良くなるかっていうのは考えたいところですよね。 へえ。このやっぱり変えられる部分に注目するというかね。 はい。 過去はもうどうしても変えられないわけなので、ま、過去の解釈は変えることができますんでね。え、え、 それをもう未来だという意味で言うと、これからできることをやっていきましょうっていう そこの目線を患金さんや医療者もみんながそこに目を向ける。 はい。 で、最後にだからと言って現代医療は否定しないと うん。 うん。これも大事でね。 はい。 現代医療は救急を中心にすごく価値のあるところもいっぱいありますから、あの、ただ常識に凝り固まりすぎてちょっともしかしたら大切なところを見失ってた部分もあるかもしれないと。 一旦離れて現代医療というものをこうもっと少し俯瞰で見直してで色々対等な状態にして、え、じゃあどうしようかということを考えるということが、ま、初体的医療を広げてるため、こ、あ、初体的医療を広げていくための、あの、なんか重要なスタンスだと思いますので、ま、視聴者の先生方にもですね、ちょっとそこの、え、スタンスを共有できれば嬉しいなと思います。はい。 うん。 ありがとうございます。今日は非常にこう大事な人と人との向き合い方みたいなところを教わったかなと思うんですけれども先生またこの死体性医療を普及する取り組みをなさってるんですよね。 はい。あのオンライン診療がうまくいかなかったもんでですね。私もどうすればいいんかなってずっと悩み続けてる今まさにまだ途中なんですけども はい。 あの、さっき言った仲間と学び合うの意味合いでね、あの、私 [音楽] 1 人じゃなくて、え、今このオンラインのコミュニティを作ってるんですよね。 [音楽] ええ、 で、これはあの、え、ま、ダイアロジカルスクールって名付けてるんですが、え、ま、もう平等なあの立場でね、え、そしてあの常識に囚われずにね、いろんなことを日々考えてるっていうそういうあのコミュニティなんですよ。 で、医者はまだ私1 人だけっていうことで、 え、ま、他にもね、お医者さんで興味ある方がいらっしゃればちょっと是非と思ったりもするんですけど、 あの、2 分間の簡単な紹介動画を作ってますので、あの、ちょっとこう出てますかね? QRコードで 見れますんで、ちょっともしよかったら、あの、ちらっと覗いていただけると。で、泡欲場参加して、ま、それはちょっとあの、選択肢として僕だけにしときますけど。はい。 あくまで選択。 あまでも選択して ま、でもね、是非こうオープンダイアログっていうものに今日初めて触れたという先生方もいらっしゃるかもしれませんから興味を思ったり考えるきっかけになったらいいですよね。あ、今日は貴重なお話ありがとうございました。 え、本日は高田頭先生に主体的医療シリーズ第 2 弾ということでオープンダログから学ぶ台湾による死体性の育組み方お話だけました。ありがとうございました。 はい、どうもありがとうございました。 [音楽]
※本動画は、医師・医学生専門の動画学習サイト
「Dr.’s Prime Academia」にて作成された、たがしゅうの関わった動画を
許可を得て一般公開したものです。
開催数No.1の医師勉強会
「Dr.’s Prime Academia」
https://drsprime.com/service/academia
——————————————————-
主体的医療を学び合うオンラインコミュニティ
「主体的医療ダイアロジカルスクール(月額2,980円)」
に興味がある方はこちら
(※2024年10月より料金改訂)
https://yoor.jp/door/tagashuu
主体的医療とは「お医者様にお任せ」ではなく、
患者主導で考えて実践していくための医療のことです。
「主体的医療ダイアロジカルスクール」の簡単な紹介動画(2分程度)
主体的医療ダイアロジカルスクールの理念を詳しく説明した動画(38分程度)
——————————————————-
「たがしゅうブログ」
https://tagashuu.jp
患者が自分で病気を治すためのエッセンシャルな情報メルマガ
たがしゅう公式メルマガ「健康セルフケアの極意」(登録は無料です!)
https://www.reservestock.jp/subscribe/118555
——————————————————-
たがしゅうチャンネルへようこそ。
総合診療医のスタンスでネットを通じて健康情報を発信するオンラインドクター「たがしゅう」と申します。
私のもともとの専門は脳神経内科ですが、今は専門の枠にとらわれず、幅広く病気を診ていきたいと考えています。
西洋医学一辺倒の現代医療に限界を感じ、漢方や鍼灸といった東洋医学、インド古代医学のアーユルヴェーダ、ヨガやピラティスなどの心身統合整体アプローチ、ドイツ発症の医療であるホメオパシー、アロマテラピー、精神療法(森田療法、認知行動療法、Compassion Focused Therapyなど)、世界に存在している様々な医療に興味を持ち学びを続けています。
私の理念は「病の根源は食事とストレスにあり。食事療法とストレスマネジメントを主体的に実践していくことで、病からの根治が目指せる」というもので、「医者に病気を治してもらう」から「患者が医師の助けを借りながら自分で病気を治す」の構造へ切り替えることによって医療はもっと良くなると考えています。
そんな患者が自分で治すための行動を取る時のサポートを行う自由診療でのオンライン診療を行っています。
たがしゅうオンラインクリニック:
https://www.tagashuuonlineclinic.com
興味のある方は是非たがしゅうをフォローアップして頂ければ、最新情報を随時更新して参ります。
何卒宜しくお願い申し上げます。