【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話047「オノマトペが奏でる、J-POP/J-ROCKの魅力」
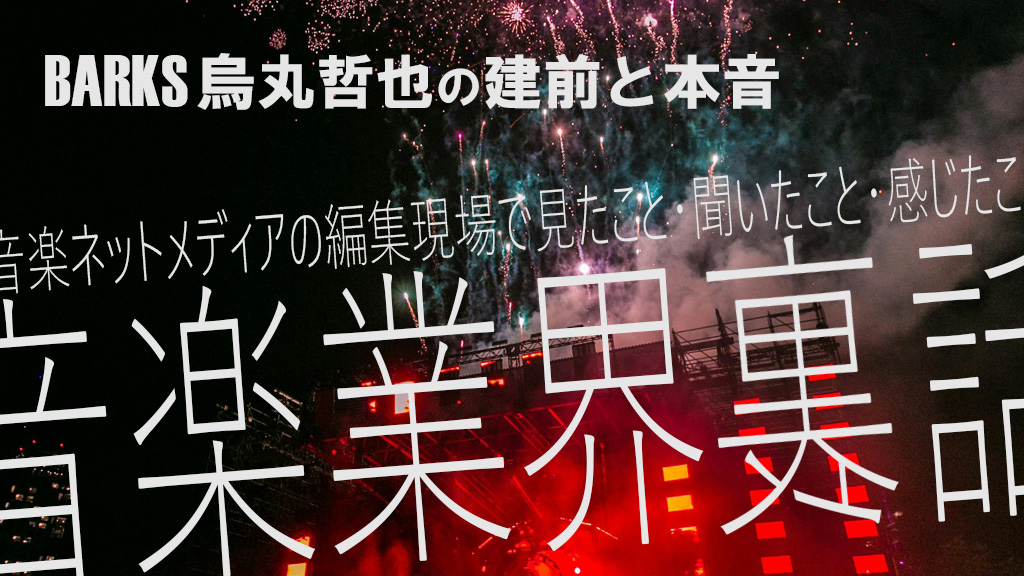
日本語には、オノマトペ(擬音語・擬態語)が豊かに存在する。「サラサラ」「ベタベタ」「ツルツル」「ネチョネチョ」といった言葉は、触感や質感を直接的に伝え、言語を介さず感覚を共有できる力を持つ。こうした表現は「音象徴」と呼ばれ、音そのものが意味を帯びる仕組みとされるが、日本語は特にその語彙が豊富であり、世界的にも特徴的な言語体系を形作っていると言われている。
その背景には、日本人の自然観があるという。風のそよぎを「サラサラ」、小川のせせらぎを「チョロチョロ」、雪の降り積もる静けさを「しんしん」と言い表してきた。四季の変化に富む自然の「音」を人間の言葉へと取り込むことで、日常の感覚を精緻に表現できるようにした。言語人類学者の指摘によれば、西洋の言語が抽象的な概念や論理を重視して発展してきたのに対し、日本語は感覚的・直観的な表現を重視し「感じたままを音にする」方向に進化したのだとか。
当然ながらこの特性は、日本のポップス文化にも大きな影響を与えてきた。J-POPの歌詞に頻出する「ドキドキ」「キラキラ」「ふわふわ」といった語は、恋愛や情緒を論理的に説明するのではなく、響きそのものによって感情を伝える。英語の「heartbeat」や「excited」が意味を理解して共感に至るのに対し、日本語のオノマトペは瞬時に身体感覚へ届く。結果として聴き手との距離を縮め、共感の回路を強固にする。
そもそもオノマトペはリズムや旋律との相性も良い。たとえば「ワクワク」「ニコニコ」といった反復音型は、その韻律的特性ゆえに旋律やリズムと親和性が高く、楽曲のフックとして機能する。子どもから大人まで口ずさみやすい大衆的受容を支える要素となり、「国民的ポップス」を生み出してきた背景には、この韻律的効果も見逃せない。AKB48「ヘビーローテーション」の歌詞に登場する「ガンガン」「ドンドン」「ジャンジャン」「ダンダン」「ビンビン」もその典型であり、単純な反復が恋愛の高鳴りを共有させるエンジンになっている。
英語にも「boom」や「tick-tock」「bang」のような擬音語は存在するものの、それらは限定的であり歌詞全体を感覚的に彩るほど多用されることは少ない。むしろ洋楽では「love」「forever」「freedom」といった抽象的・理念的な言葉が繰り返される傾向が強い。たとえばザ・ビートルズの「ラヴ・ミー・ドゥ」やワンリパブリックの「カウンティング・スターズ」などは、愛や希望といった抽象概念をシンボリックに提示するけれど、その過程で身体感覚に訴えるオノマトペはほとんど使われない。
さらに言ってしまえば、日本のミュージシャンやエンジニアは、音色を「シャリシャリ」「モコモコ」「キラキラ」「キンキン」…といった擬態語で語ることが多い。プロの音楽制作の現場ですらtimbre(音色)をスペクトル的・物理的に捉えるのではなく、触覚や質感に変換してサウンドを理解し共有する。まさに日本的な音響感覚の表れであり、「音の質感を言葉で共有する文化」がシティポップやJ-POP/J-ROCK特有の緻密なサウンド作りを生み出してきた。
オノマトペは単なる言語現象ではなく、自然と感覚を音で結びつけ人間同士の共感を直感的に呼び起こすツールとして機能している。サラサラと流れる旋律、ドキドキと弾むリズム、ふわふわと漂うボーカル…日本の音楽の魅力が世界唯一の輝きを持っている一端には、そんな言語体系もあるのではないか。

文◎BARKS 烏丸哲也
◆【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話まとめ

