地方の未来、あなたはどう考える?「保険会社」と「まちづくりのプロ」が挑む新たな地方創生のカタチとは【NewsPicks/東京海上/大木 優紀/山崎 亮/渡部 真吾/地方創生/官民連携/人口減少社会】
あなたたちの町をあなたたち自身が良くしようと思わないなら一体誰が良くするんすか? 地域の企業でやっぱり地域の住民の方々が死体性を持って動くような形にこうしていかないとま、このような目標もどうしてもこう長続きしない。 どうすればこのサステナブルな地域創生というのが実現できるのか。 大人とくのやめます。 で、子供たちと一緒に計画作りたいって言ったら地域に対する愛着や地域が未来もいつか戻ってきたいと思ってますっていう意見がすごい出てきたので、これをあなたたちが 10 年かけて実現しないなら私たち全員で島に戻ってこないって決めますって言って渡したんですよ。 へえ。 答えはやっぱ地域の中にある地域にこう産業を作っていこうという形で最初はもう 6 社近いなかったコンソーシムだったんですけども今時点ではもう 80 社以上の方々がこちらじゃ一緒にやっていこうということで何かあってもこういう風に安心してできるんだといったような形が我々のあの保険会社のま、新たな役割かなとは思って 渡辺さんの業務上の KPI とか目標地って世界平和と健康みたいなんですけどつまりヒーローで [音楽] こんにちは。大ゆきです。この番組はこの ままの未来か作り出す未来かをコンセプト に東京会場グループの提供でお送りします 。さて、今回のテーマなんですが、地域 から持続可能な未来を作る地方創生2.0 の実践論と、ま、日本経済最高の鍵を握る 地方をテーマにクリエイターと保険会社と いう移植の組み合わせで未来について考え てまいります。え、それではゲストをご 紹介しましょう。住民参加型の街づり や地域のデザインを手掛けるコミュニティ の山崎りさんです。よろしくお願いいたし ます。よろしくお願いします。 今回は地方創生がテーマになるんですが、まずこのコミュニティデザイナーという山崎さんのお仕事について伺ってもよろしいですか? はい。多分聞き慣れない言葉だろうと思うんですよね。 コミュニティデザイナー自分たちの地域の課題をなんかこう話し合いながら自分たちで整理したり発見してじゃこれをどうやって乗り越えればいいのかこれをまた自分たちの関係性の中で解決策を生み出したりそれからそれを実行したりするでこの 1 連のプロセスを外側から少しこう支援していくがコミュニティデザインという仕事と説明してもなお分かりにくいなとは自覚しております。 え、続きまして、東京会場日火災保険株式会社で地方創生に取り組むマーケット戦略部地域連携室マネージャーの渡辺部慎吾さんです。お願いいたします。 はい、よろしくお願いします。 所属するこのマーケット戦略部地域連携室っていうのは保険会社の中でどんなお仕事をされてるんでしょうか? 地域を1 つのマーケットと捉えまして、ま、そこに関係する自治体ですとか商産団体、ま、地方の銀行であったり、マスコミであったり、地域の企業様だったり地域の課題を解決するようなそんなこうデザインをするようなことをあの企画し実行してるようなそんな部隊でございます。 なんでそもそもその保険会社がこの地方創生に取り組んでいるんでしょうか? 地域の様々なこう挑戦しようとしている事業者様であったりプレイヤーの方々個人も含めてですけども挑戦する新しいことをやろうとするそこのこう黒逆な形で我々が存在しておりまして挑戦するとリスクが生まれてでリスクが生まれるとそれをマネージするのが我々保険会社の役割かなという風に続けてます。 確かに朝鮮からのリスク、リスクからの保険っていうとこの繋がりはなるほどなというところがありますよね。さて、ま、地方創生って言いますと移住支援とかで、ま、地方地域のこう人口を増やそうというところの取り組みっていうのはよく分かるところではあるんですが、ただこう人の取り合いを地域ごとにしていてもこれも限りがあるなっていうのは見えてるところだと思うんですよね。 ま、そんな背景の中で地方創生 2.0 というものが何を求められてるのか。 自分たちが現場に呼んでいただいてやろうと思うことで言うと 1 つは関係性の問題をどういう風に解いていくお手伝いができるか 地域には当然そのこれまでの人間関係があってあそことあそこはすごい仲良しねあそことあそこはなかなか難しい関係であるこをちょっと調整すれば新しいことが生まれるかもしれない切な関係性の中であれば課題をちゃんと見つけることもできる関係 の適正化のようなことっていうのは 地方創生にとっては大切なんだと思うんですね。 うん。うん。 スとなるような部分はお互いにこう作ってお互いにこう使えるで上に乗っかってくる競争領域だけでここであの企業感で競争していくようなそういったようなこう最適化を図っていくことであの人口現象の中でもあの鍵である資源の最適化をできればという話はいろんな方々と飛ばしております。 うん。基本になるところっていうのは やっぱり関係性っていう意味ではすごい 大事で、で、しかも安心して挑戦したりと かいろんなことができたり、あるいは地域 の目線を揃えたり、価値観をこう共有して いくみたいな部分があり、その上に 乗っかってちょっとそれぞれの独自性だっ たり、ま、少し競い合ってみるみたいな ことがあってもいいんだろうという風に 思うんですが、そんなにきっちり僕はあの 概念が整理できてなかったんですが、 ちょっとずるいかなことやってます。はい 。早速最初のテーマに参りたいと思います 。地方創生の現実というのが最初のテーマ になっております。ま、石総理なんです けれども、初代地方創生担当大臣で いらっしゃいましたので、その際に成立し たのが町人仕事創生法です。その目的が こちらでございます。少子高齢化に対応し 、人口減少に歯止めをかけるとともに、 東京県への過度な人口集中を是正し、 住良い地域環境を確保し、活力ある日本 社会を維持することと。で、この法律が 制定されたのがもう2014年ですでに 10年以上が経っているというところなん ですが、この10年の人口増加率というの がこちらなんですね。ま、10 年で人口が増加しているのは沖縄県を除くと首都県崎さん、この、ま、現状並びに課題っていうのはどういう風にご覧になってますか? この10 年でこういう状態になってきてる。で、次の 10 年で多分このまま行くと東京以外の大都市から東京へ人口が流出していくと、それをもちろん歯止めをかけたいというのは地方創生がやらなきゃいけないという風に思っていることでもあるだろうと。 日本の総人のうちで都市部以外の出身の人たち、その人たちにちょっとこう可能性を感じているんですね。 自分の故里故郷でなくてもいいので都市以外の地域の活動に何らかの形で貢献したいっていう風に思える人たち地中央創生の中では結構重要になってくるんじゃないかなという気がしてますね。 とある自治体の方とお話面白いなと思ったのがですね、例えば仙台であれば東北 6 件から、え、大学の進学の時に仙台に集まってきて、で、そこで仙台就職するもしくは東京に出てってしまうみたいなことに対して集まりよりこう出ていくこうダム機能がこう なされてると言いますか、そういったところが 入ってくるように出る方が多くなってしまって、それはどうなんだっていうのがこの 10 年ぐらい話されていたんですけども、今後はそれをこ を止めるのではなくて、東京もちろんですけども、世界各国に広がっていくことで、で、関係人口がもうどんどんどんどん世界中に広がっていくさ農なんかもありますけども、ま、それ以外でも今オンラインでどこでもこう仕事もできますし、えっと、価値提供もできるような時代なので、新しいコミュニティ、そういったようなことを目指しているんだっていうような自治体さも出てきてまして、企業側もそれを企業版の故郷農税とかだけではなくて、やっぱ授業でう うん。 政府が5月に今後10 年で取り組む政策をまとめた市案というのがこちらで、ま、数値目標を掲げる主な項目の 1 つにこの関係人口というところが入っているんですが それぞれの地域の中にもこの関係人口と呼んでいい人がいる。ま、関係人口って提承している人たちとディスカッションしたことがあって はい。 僕はちょっとその似た言葉で、あの、活動人口っていうことをかつて本に書いたことがあったんですよ。で、これは地域にお住まいの方々の中でね、あの、地域の街づりに参加して、ま、何か活動している人たちの人口というのを 1 回活動人口と呼んでみようと。その中に街づり活動に参加している活動人口っていう比率が めちゃくちゃ低い地域がいい街って言えるかどうかみたいなことが見えてくるかなと思ったんですね。うん。うん。 やっぱり活動人口が増えると関係人口もこう自然と増えていくみたいなうん。 関係性があるのかな。 そんな気がしますね。 外から応援したいと思う人たちも増えるだろうし、中で活動している人たちがその地域の外の人たちに助けを求めたりとか、 あるいは応援してもらったらアドバイスもらったりするっていうようなこの関係が結局活動人口の周りに関係人口結構いっぱいいるっていうことになっていくだろうと思うので地域における活動人口比率を高めていくことが関係人口を増やしていくっていうことにつがるのかもしれないですね。 うん。 ま、一方ね、これ完全に、ま、東京の論理で作られた政策なのかな、方針なのかなっていうところもあるんですが、その辺の観点から渡辺さんはこの政府が掲げた試案っていうのはどういう風にご覧になってますか? ま、もちろんこういったことをきっかけにこの地域の方々にこう一緒にこうやろうよとまさにあの関係人口から活動人口の方にこう一緒にやっていこうよていうような形で巻き込んで地域の企業であり地域の住民の方々がう 体制を持って動くような形にこうしていかないと、ま、このような目標もどうしてもこう長続きしないんだろうなという風にはあの感じては 地方にまさにある活動人口なんだよ。この質の部分なんだよって視点がやっぱりこう政府がまとめた試案と現場を知ってるお 2 人のこう視点の違いだなって非常に感じたのでここからさらにちょっと具体的なお話を 2 人に伺っていきたいと思います。え、続いてのトークテーマはこちらです。 答えは地域の中にあるとどうすればこのサステナブルな地域創生というのが実現できるのか、その事例をまずえっと山崎さんに伺いたいと思います。 1 つ目がこちらです。カ音寺中再生計画というものなんですが、どんな取り組みだったんでしょうか?うん。 香川県のカ音地という、ま、町がありまして、ここが、ま、いわゆる商店街というかな、中心市街地と呼ばれることも多いんですけれども、ま、ちょっとずつ人が来なくなって衰退してると言われていたわけですね。で、ここをどうしたらその元気にさせられるかということで呼んでいただいたというのが、ま、仕事の発端だったんです。なので地域の方々と一緒に、あの、まず商店街歩かしていただいた。で、そうすると下着屋さんの中にもっと違うお店が入ってきた。 景屋さんが入り野菜も売るようになってきた。で、地域の人たとしてはこれは、ま、恥ずかしいからあまり言いたくない話だったんですよ。我々としてはこれはとても素晴らしいというか、誇らしいことだと思ったんですね。ショップインショップ、ま、店の中にもう 1 個店があるということで、ま、ショップインショップをどんどん広げていくっていうことにしたらどうだろうと。 うん。 元々地元でやってたんだからそれを恥ずかしいって思わなくてクリエイティブだって思うっていうその意識だけ変えちゃえば これは結構もうできることなんじゃないかなと思ったんですよ。 うん。うん。 そしたら結構他の商店の人たちも うん。 それでいいのって言ってあ あ、なるほど。 それでいいならこのスカスカの棚寄せるけどって言ってみんな寄せてくれてスペース作ってくれたんですね。 うん。はい。 どんな今組み合わせのお店あるんですか? 竹内さんの補聴機の店が、ま、ショップインショップやってもいいぞと。 ま、これカウンジってあの瀬戸内会なので瀬戸内ちのタコですね。新鮮なタコを料理するタコのやーちゃんっていうタコ料理のお店が視点を出したいと思ってたみたいなんですよ。 食べられるのは本当にいいのかなと思ったんですけど地域の人たちは結構なんかね喜んで耳にタコができた [音楽] うまいこと言うやないか なんか僕らが何かを答えを持っていったり業種がいいとかなんとかって言ったんではなくてむしろこっちに可能性あるんじゃないですかって言って見え方が変わるとすごく動いたなというのを実感したんでまさに答えはやっぱり地域の中にあ うん。渡辺さん、どうですか?この取り組み。 いや、これ本と素晴らしいなと思ってまして、行政だったりとか、東京のこうモデルロジックで持ってたら多分こうはならないかなと思ってまして、元々やってるところをあ、素晴らしいっていうこう外部の方からもこう見てでそれをあのショップインショップっていう形でこうネービングをすることによってもうそれをこう真似しやすくなる気かしさがこうなくなるような地域にこうね指したこう取り組みでどこでもできそうだなとは思いました。 続いては岡山子供笠岡諸首党進行計画というものなんですが、どんな取り組みなんでしょうか? 笠岡諸島という、ま、岡山県の瀬戸内会にあのつかの島がこう分れてあるこの島の進行計画を作ってほしいという風に笠岡市役所から頼まれたんですね。 これは、ま、もちろん人口現象にも悩んでるだろうし、経済についても悩んでるだろうから、まずは島の方々の話を聞こうということで、 6 つの島を渡り歩いて大人たちの話をずっと聞いてもらったんですよ。大人たちがですね、ほとんど危機意識を持ってなかったんですよ。 ええ、 まあ、なんか進行計画作ってくれるんやったら作ってくれと。ただ私らは忙しいからちょっと参加とかはできないみたいなことで、 あなたの町をあなたたち自身が良くしようと思わないなら一体誰が良くするんすかみたいな気持ちがむくいてきた。 てで子供たちと一緒に計画作りたいって言ったら子供たちの方が地域に対する愛着や地域が未来もやっぱり楽しい場所であってほしいしつか戻ってきたいと思ってますっていう意見がすごい出てきたのでじゃあどんな未来の町になっていたら自分たちは戻るかっていう計画を作ってそのままとめた 冊を大人に 渡したんですよ。 うん。 私たちがこうなってなきゃ嫌だっていう未来をここに書きましたね。 これをあなたたちが10 年かけて実現しないなら私たち全員で島に戻ってこないって決めますって言って渡したんですよ。 へえ。 あの、ここにいる小学生たちが全員戻ってこないってことは 10 年後人口がゼロになるっていうことは確定しちゃうんで、で、さすがにちょっとそれはまずいねということで、で、大人たちがその後、あの、子供たちが言ったことをどうやって実現するかっていう会議を本気でやり始めるっていうことになると いうのが、 あ、ありました。 具体的にこの子供たちの提案っていうのはどんな内容だったんですか? 島がどんどんどんどんコンクリートで追われていっているので、そういうのをやめてちゃんと普通のものにしてくれとかですね。 島の物産だけで作るお店を作ってくれと。 6 個か7 個ぐらい子供たちは実現して欲しい未来みたいなのを大人たちに伝えてましたね。うん。続いて東京会場日童火災保険の取り組みというのをご紹介いただきましょう。それがこちらです。 愛知デジタルヘルスープロジェクトというものなんですが、部さん、これどういった取り組みなんでしょうか? え、東京会場日であの様々な地域の自治体さんだったりとか企業であったり、ま、団体の方々と対話しながら課題をこう見つけてその課題を一緒になって解決するような事業やっておるんですけども、愛系のも実はもう 2019 年ピークに人口現象にも転じているんですよね。 ま、そんな中で、ま、高齢者の方々が どんどん増えていき、2040年頃には、 あの、医療であったり介護だったりで、 こう支援が必要な方々に対してこう支える 側がもう足りなくなるような時代が愛知で も聞きますと、もう愛知のデジタルヘルス ではですね、3間額が連携し合って地域の こう高齢者の方々に対していろんな コミュニティにも参角いただき、自分の こう健康を把握して必要なサービスを受け ていただく ようなそんなプロジェクトを一緒にやって作っていこうよと。 元々あの愛知県の方から東京会場日の方にこんなこと考えてるんだけども東京会場さんの一緒にやりませんかみたいなその誘いをですね、 頂いたんですけれども話の中からうん。 ここでやっぱ産業を作っていこうと地域の高齢者の方々もお支えするっていうのはもちろんなんですけども 健康増するようなサービスがもうどんどんどんどんこう地域発で生まれるようなそんなこうプロジェクトにしていきたいよねっていうのが愛知県さんと一緒に話しながら出てきた中でいろんなこう事業者さんと元々あの東京会場に一度はお取引ある中で ある電力会社さんはこんなヘルスケア金の授業やりたい交通事業者さんは高齢者の健康増役立た こう話をしてる中でじゃあ一緒にやり ましょうよっていう形で入っていったのが あのこのプロジェクトのきっかけであっ たりあの我々の役割りで始めてました。 東京会場の保険に入ったら健康になるですとか病気になったとしても再発しないようなそういったような世界観を描きたいなということでヘルスキア事業も今取り組んでまして例えばま誰しもがこうだんだん高齢化になってくると足越しが弱っていってまと呼ばれるような巨弱段階になってくるのでまそこをなるべくこう抑えていこうとあの送らせていこうといったような取り組みとあとは生きがいがあることによって地域とのコミュニケーション他とのコミュニケーションを取ることによ やっぱ家から出ていって活動してやっぱりその話したり取ることがものすごい重要でであとは最終的には支援要介護の状態になっていきますけれどもその時にも自宅にこうお住まいただきながら地域のこうコミュニティとサービスによってお支えするようなそんなこうパッケージをここにこう触れれば何かしらはこう自分に必要なサービスが届くもしくは自分のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに必要なサービスが手に入るようなそんなこうコミュニティを作っていこうて地域にこう 産業作っていこうという形で最初はもう 6 社かいなかったコンソーシムだったんですけども、 今時点ではもう80社以上のあの3 間額のあのプレイヤーの方々がこうじゃ一緒にやっていこうっていうことであの手を上げていただいておりましてある程度こう形になってきたかなとは思います。うん。 東京会場さんが声かけたんだったら 300 車ぐらいいきなりやろうって言ったのかと思ったら まず6車だった。 うん。 なんかちょっとね金感は来ました。 さあ、それではその他の取り組みも色々あるようなので見せていただきましょう。地域防災力レジリエンスの向上に貢献。これは具体どんな取り組みだったんでしょうか? あ、はい。東京会場日保険会社でありますので、この防災であったり減っていうのは、ま、 1丁目1 番地でやっているような取り組みでありますと。 ま、昨年の正月にあの野半島地震が発生しまして、やっぱり野みたいにこう地震が起きた時にどうやってやっていこうかと話している中でやっぱり大きなこうブメントを起こしていかないとやっぱりあの一言感があったりですとかあの危機感がなかなか生まれない中で自治体さんとまさ団体もあの商候会議者とか商候会さんとかと連携しながら地域一眼となってこう守っていこうというところに東京会場がこうハブとなって うん。こちらの地域レジンスの場の話ですかね。 とにかくやっぱり保険の支払いを求める時って困った助けてじゃないですか?基本にあるのがね。この困った助けてをさんは少しでもま、減らす仕事 っていうところなんだな。 世の中の健康と平和をこう推進する仕事が保険会社の一部として行ってるんだっていうのはちょっと私も考えた考えが及んだこともなかったですしごく新しい 学びだったなと思うんです。 いつも抑えさせるためにこの今のこう事業環境であったりこの各地域で起きていることもしくその課題をして見ていって何が変動要素なのかリスクなのかっていったところを見えることによって事業者様も市民の方々もあかもこういう風に安心してできるのねといったような形が我々のあの保険会社のま、新たな役割かなとは思ってまいろんな地域で活動はさせていただいて ちょっと興味があるので渡辺さんの業務上 のKPI とか目標地って世界平和と健康みたいなところが入ってくるんじゃないかなと思ったんですけど。 つまりヒーローと KP どういう目標地KPI売ってるんですか? いろんなこう社会課題を解決するためのビジネスモデルの方をたくさん作っていくことが 1つのKPI でありまして、ま、全てはお役には立てないんですけども、この領域だったらできるっていうところを 少しでもこう増やしていきたいとは思っております。うん。 その保険会社がになってその地域をより安全で安心で自分たちが保険のお世話にならなくていい状態リスクをこうちょっとずつみんなで繋がって減らしていく結果起きなければ払わなくていい保険会社もちゃんと助かってるのであれば すげえうまくできていて いやうまくできすぎていて本当すか この山崎さんのご指摘いかがですか? そうですね、個人の方々 日常生活、ま、運転も含めてされる中でそこの行動を動かすことて、ま、全然できないわけじゃないですか。なのでそこをどうやったら動くのかなていうことやっぱ自分のごとであったりコミュニティの中でこう作っていきお互いにこう注意し合うような形 で結果的にはま、事故が少なくなれば我々のこう保険教らせる保険金も少なくなり保険金が少なくなると地域の方々お客様が払う保険も安くなっていくそういったような世界観がやっぱり必要だと思うんですよね。 うん。やっぱりじゃあちゃんとそれができちゃってるわけだ。で、結果的にはそういう地域だよってのがおっしゃる通り、地方創生としては選ばれる地域になっていく可能性もいい地域だねっていう情報がこう外で出ていくっていうことで地方創生にも貢献してると言えるっていう。 うん。 そうか。本当にそんなにちゃんとできてるのか。 なんかこうそれぞれの立場と観点っていうのがもう非常にクリアになったなと思うんですが。 さあ、ここでちょっと最後のテーマに進んでいきたいと思います。持続可能な未来を作るために私たちができること。持続可能な未来を作るために考えるべきことは何なのかそれぞれお 2人のご意見を伺いたいなと思います。 あまりその事業や仕事っていうのとは関わりがない形で住みやすい地域をどうやって作っていくか。ま、こんなことやってるんですね。 仕事じゃないけどなんとか続いているものって何だったっけって、ま、自分の経験の中から見てみたら学生時代にやってた部活ってやつが はい。はい。 あれがなんで続いてんのかようわからんという気がしたんですよ。考えてみたら、ま、自分もあの部活やってたので自分の経験でやると 7つぐらいですね。 多分この7 つがあるから続いたんじゃないだろうかと思えたことがあったんです。 はい。はい。 でもそれで言うとそれを地方創生に当てはまるのはちょっと無理があるかなと思うんですが伺いたいです。 例えば はい。 地域の人たち集まった 1 番目の練習をやってるかっていうのはね、やっぱりちゃんと自分たちで定期的に集まって事例を集めてみたり、自分たちの活動を会議で決めてみたりすることってできるできてるのかどうかでそれができてるようになったらあ、 1 番目の日々の練習できてますねってことになるわけですね。試合ですね。 にの練ばっやっじゃなくて会議ばっかりやっじゃなくて町に出て自分の活動をやっぱちゃんとやってみるから社会実験してもいいし活動やってみて伝えかもしれないけれども反省会やるで 3つ目全国大会出てますかと 地域づり対象とかグッドデザイン賞とか同じ立場で他の人がどんなことやってんのかってのを大きく学べますから全国大会 1回出といた方がいいすよに1 回は出ましょうとかですね勧誘がこれは忘れがちなんです。 地域の人たち自分たちだけでずっとやってたら高齢化していくだけってことになっちゃうんですが、毎年 4月になったら新しいと完しましょう。 で、これの裏なんですけど、卒業の仕組みありますかと。 ずっと同じ人がボスになってませんかと。だから何年活動したら何歳になったらちょっとどいてください。え、いうことができてますか? 6番目。 役割自分たちで決められてますか?うん。 誰がまあそのお財を握ってる人で、誰がリーダーシップを取る人で、誰がサポートする人で、こういう自分たちで役割を決めるっていう力がついて、で、最後 7 番目ですね。自分たちで最小限でもいいから、ま、持続可能なめのその資金というのかな、お金をもちろん回避でもいいし、何か事業をやってもいいんだけれども、そういうお金をちょっとでも回す仕組みができてますか? うん。我々がま、大体3 年間ぐらい支援するんですが、この 3年間の間に7 つできるようになってくださいねって言って、 7 つできるようになりましたね。じゃあもう僕らなくていいすねとかね。で、我々が地域から必要とされなくなった時が、ま、僕らにとってはあの仕事の成果であり、嬉しくもあり、ま、若干寂しくもある時ですが、それで我々は地域から去っていくと、まあ、多分部活のように、大人の部活のように地域で活動が続いてくれるんじゃないかなと。 ま、こんな風に感じてますね。 ものすごく納得できました。う ん。 持続可能っていうのはやはりあの一性ではなくて地域にね指してで地域のこうプレイヤーの方々が事業として産業としてもうやり続けられる生活し続けられるようなことが 1 番大事だなと思っておりましてリスクのこう貸たなことはあの東京会場日ではあのいろんなこう地域で新しい朝鮮を得る時にはあのサポートと言いますか一緒に入り込んでいって不安がないように 地域の方々が生き生きと活動できるようにまそんな支えで入ってることがう 多いかなと思います。 うん。さあ、ということで今回はですね、 地域から持続可能な未来を作る地方創生 2.0の実践論というテーマに民間主導に よるこのサステナブルな地方創生の目指す べき姿というのは非常に本当今日お話を 通じて見えてきたなと思うんですが、この 後お2人がそれぞれ取り組みたいこと みたいな話を伺いたいんですが、目に見え ないことを取り扱ってる、ま、関係がどう だとかね、その結びつきをつぎ直すだとか やっぱこうパッと見える話じゃないので コミュニティデザインンってやっぱり なかなか知ってもらえないし心人も増えて いかない気もします。 ただ自分の中ではやっぱりこの手の仕事がそれぞれの地域に足りてないなという実感は仕事すればするほどあるコミデデザインということをやっていこうっていう風に思う人たちをま、ちょっとでも増やせていけたらいいしその人たちに我々が経験したことぐらいであればお伝えしたいなという風に思ってる点ではあります。 うん。 東京会場日だけできることてほんでもごくわかな領域なのでこういったようなこう取り組みを我々の東京に日の全国のこう社員がやるもしくはその先のお取引き先の方々と一緒にやることによって一緒になってこう新しいことをチャレンジする解決していくためにこう行動を動かすっていうことが現地のこう方々のやりがいにもつがってきますし 特に若者からすると課題解決とか世の中人のために立つう ってものすごいこう関心ある方々が増えて きてるなという風に思っておりまして、 そういったようなこう方々があの仕事で 司方にこう戻っても活躍できるこう場を たくさん作っていくやらされ感でなくて 自分たちでこう作んだっていったそんな形 をあのいろんなところで作う ありがとうございます。 なんか今日は本当に地方創生に関するその構造っていうのが非常にクリアになった上で何かこう持続可能な取り組みというところへの公明も見えたような気がいたしました。山崎さん、そして渡辺さん本日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。 ありがとうございました。
【Sponsored by 東京海上グループ】
「このままの未来か。つくりだす未来か。」をコンセプトに
全5回シリーズでお届けする「TOMORROW TALKS」。
第4回のテーマは「地域から持続可能な未来をつくる。地方創生2.0の実践論」。
都市の人口増加と地方の人口減少による二極化が課題となっている中、
政府は2014年に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し対策を進めてきたが、
十分な成果は出ていない。
そこで今回は、「地方創生」をテーマに地方の課題に向き合っているゲスト2人を招き、
地方が抱えている問題や実際に取り組んでいる事例を伺い、
日本経済再興のカギを握る“地方”のサステナブルな未来に必要なことを議論する。
〈ゲスト〉
・山崎 亮(studio-L代表/コミュニティデザイナー)
・渡部 真吾(東京海上日動火災保険株式会社 マーケット戦略部 地域連携室マネージャー)
〈MC〉
・大木 優紀(令和トラベル執行役員)
00:00 ダイジェスト
01:13 ゲスト紹介
03:45 地方創生2.0と地方の現状
05:38 地方創生の現実
08:24 地方に欠かせない活動人口
10:29 地方創生の答えは地域に
10:46 実例紹介1: 観音寺まちなか再生計画
13:22 実例紹介2:子ども笠岡諸島振興計画
15:35 保険会社と地方が手を組み進める地方創生の形
19:02 地域のハブとなる保険会社の新たな役割
22:53 持続可能な未来をつくるために
26:16 まとめ
#地方創生 #地域の力 #地域連携 #地域ヒーロー #地域課題解決
#保険会社 #サステナブル #共生社会
#コミュニティデザイン #人口減少社会 #持続可能な社会
#官民連携 #地方ビジネス #未来志向

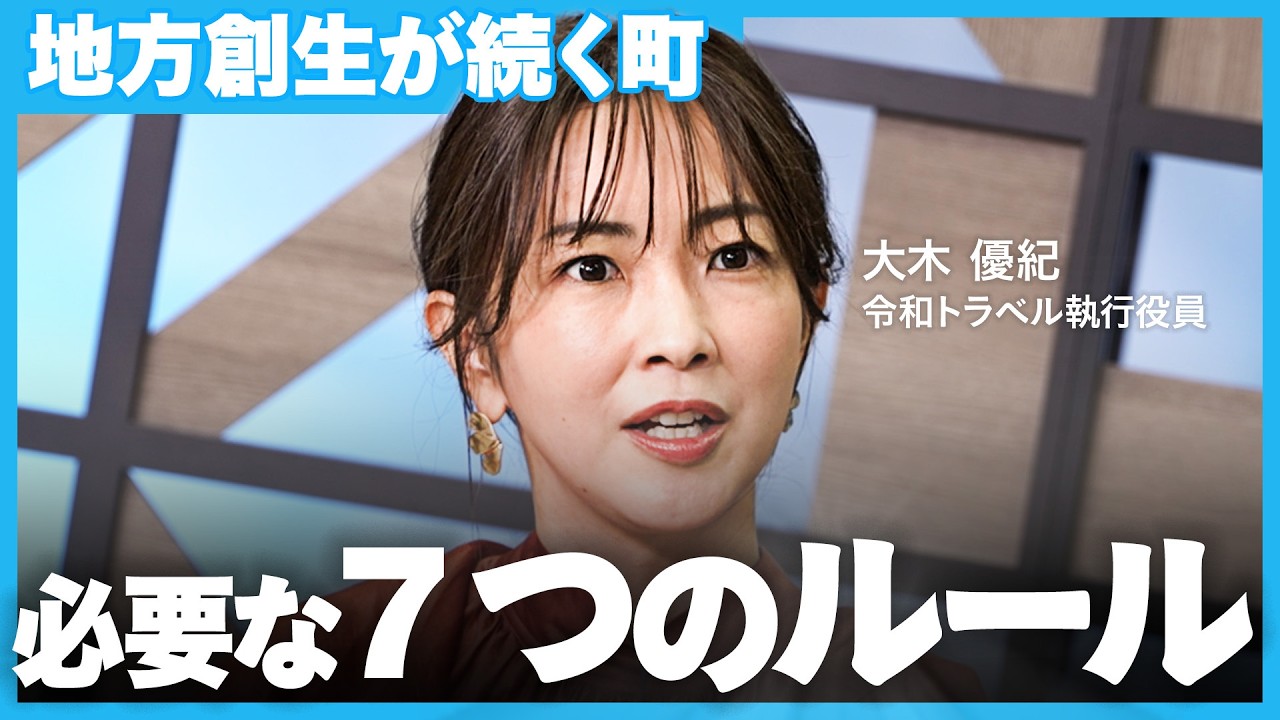
1 Comment
ダンビラの大原かと思ったわ