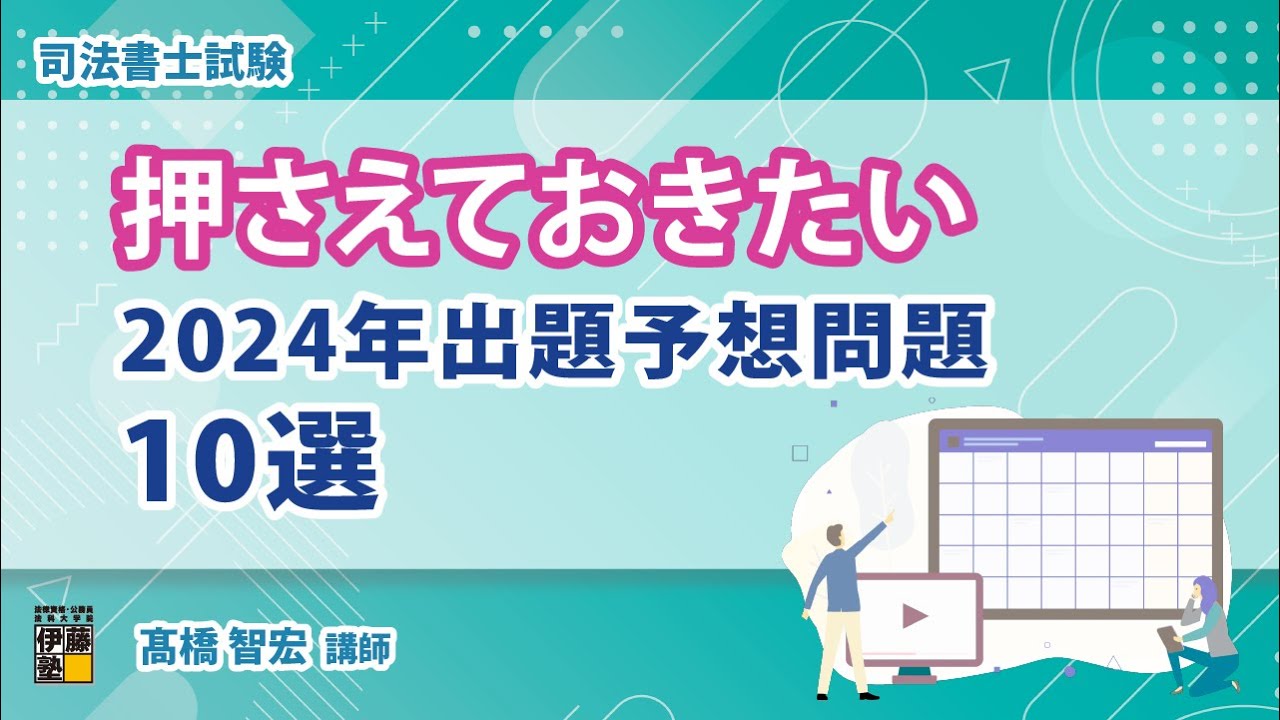【司法書士試験】押さえておきたい2024年出題予想問題10選
それでは始めていきます皆さん こんにちは伊藤塾講師の高橋です今回は こちら抑えておきたい2024年出題予想 問題10戦こちらの公開講座を始めていき ますどうぞよろしくお願いいたし ますそれではまず第1部として本公開講座 の狙いと講義方針についてお話をしていき ますこちらご覧ください今回の狙いは2つ あってまず1点目出題予想の学習戦略を 提示していくということです直前期学習で 強力な武器となる出題予想これを活用した 学習戦略を提示していきます加えて2点目 2024年の本試験で出題可能性が高い 知識こちらを習得していくということ です講義方針に関してはセール主旨え テキスト内ではこういったマークのところ で説説をしているものでありますがこう いったなぜそうなるのかといった制度趣旨 から説明をしていく理解重視の講義を行っ ていきます加えて注目すべき箇所に関して はマーク指定をしていきますこの後紹介 する直前講座受かる択一式と同じ容量で 進めていきますねマークの色は何色でも 構いませ んではテキストでありますが動画リンクの ところからこちら今回のテキスト印刷 できるようになっていますので各自ご用意 いただければという風に思い ますただ今回は画面の方に映し出しながら 講義を進めていきますですから印刷できる 環境にないという方に関してもまそのまま 画面の方を見ていただければ大丈夫ですよ ということ ですそれでは狙いの丸1番のところこの 出題予想を活用した学習戦略について少し お話をしておき ます出予想のメリットは3つありますまず 1点目が直前期学習のになるつまり予想に 基づいた直前期学習の優先順位が分かると いうことそして次にポイントの2つ目予想 論点に強くなる出るところを重点的に 取り組むことによって効率よく得点を 伸ばすことが できるそしてポイントの3つ目精神面で 優位に立つことができる予想がまさに本 試験で的中した時にやったぞということで 自信を持って問題を解くことができるわけ ですこのように出題予想っていうのは直前 期の学習効率を引き上げていくそのための 最適なツールになっているわけですただ じゃあ予想分野以外はやる必要はないの かって言うとそんなことはありません じゃあどういったバランスで勉強していけ ばいいのかと言うとこんなイメージです 正解すべき問題のイメージでありますが
予想分野に関しては言ってみれば攻めの 分野になっていきます正当率が高いA ランクの問題として取材された時は もちろん正当率が大体5050%とか 60%とかそういった差がつくようなB+ ランクの問題も取れるようにするつまり 出題予想の学習では発展知識も抑えていく ということですこのような差をつつける 勉強をしてここで効率よく上の点も含めて 取っていくんだということです ねそれに対して予想以外の分野に関しては 言ってみれば守りの分野になっていきます 正当率が高めのAランクの問題が来た時に 確実に取れていくようにするそのためには 基本知識を抑えていく差をつけられない 勉強をしていくということですこのように 出題が予想される分野に関しては攻めでB +ランクも取れるようにしていくそれ以外 の分野に関しては守りで最低限Aランクの 問題が取れるようにするまこういった役割 分担をすることによって効率よく直前期 学習として上乗せ点対策もできるように するということです是非こういった点を 意識してこれからの主題予想の講義聞いて いただければと思い ますでは第2部として押えておきたい出題 予想問題10戦こちらの解説をしていき ます今回問題としては10も用意している わけですがこちら10文解いてから力試し でえ演習をしてから講義を聞きたいよと いう方に関しては一旦画面を止めて テキストの1ページ目の問題を解いてそれ から聞いていただければと思いますただ まだ問題を解いていないという方であった としても随時問題部の読み上げをしていき ますのでそのまま聞いていただいても 大丈夫 ですでは中身の解説をしていきましょう テキストの2ページ開いてください テキストの2ページの大きな1番民法の 占有権について見ていきます民法の今年の 出題予想分野の1つ目は占有権であり ます出題予想の度合としては星3つかなり 確実性が高いのかなというところですでは コメントのところ見ていきましょう声優権 は平成27年度以降に2年に1回以上の ペースで出題されているわけですが令和4 年令和5年度においてそこの声優権の出題 がなかったわけこの2年間空いてるわけ ですねですから今年の出題可能性が高い ですよということです細かめの論点まで 手広くえ知識を抑えていくようにし ましょうそしてえこの戦友権の中でも今回 取り扱っていくテーマは戦友回収の訴と なります画面の方をご覧
ください戦友回収の訴に関する条文まず見 ていくことにし ます声優回収の訴えは戦友を信達したもの の特定証人に対して提起をすることができ ないただしその証人が診断の事実を知って いた時はこの限りで ない要点をまとめていくとすなわち声優 回収の訴えは善意の特定人に提起をする ことができないということになっていく わけ ですではこの制度趣旨を見ていくことにし ます2ページの下の補足問題のコメント見 ていきましょうこちらの指印のところ です200条2項本文の趣旨はマーク善意 の特定証券人のもで新たな戦友秩序が形成 されているここまで善意の特定証権人の元 で新たな戦友秩序が形成されているところ この新たな戦友を保護していくんだという ことなんですねこういった新たな戦友を 保護という趣旨から考えてこの趣旨を徹底 していくと絶対的構成が取られているその 判例の結論に行きつくわけであります あなたに善意の特定証権人のもで構築され ていった戦友秩序を保護するという観点 からこの善意の特定証権人に対して提起 することができないっていうのは絶対的 構成が取られているんですね 3ページの第1問のイラスト見ていき ましょう3ページの第1問のイラスト 例えばAが行動産後Bに盗まれましたで その高動産をBが善意の特定証券人である Cに売却をしてそしてさらにCがDにこれ を転売しましたそしてDが悪意であると この場合には一旦善意の特定証人が出てき ているわけなので点特者は保護されること になりますつまりは絶対的構成が取られて いるわけですね左側の本文のこちら絶対的 構成というところマーカーを引いておいて ください一旦全員の特定証経任を通せば その後転得者は保護されていくんだこの ような絶対的構成が取られているゆえに この場合にはAは悪意の特定証権人である Dに対して占有回収の訴を提起することが できないということになっていきます そしてそれが問われているのが第1問なん ですね第1問の問題見ていきましょう問題 文要約して述べていきますが本問で問われ てるのはbはaが占有する動産交互の済 その事実を知らないCに売却をしたつまり Cは善意であるとその後Cは知っていた つまり悪意であるDに対して売却をしまし たCが善意でDが悪意ということですこの 場合aはDに対し占有回収の訴えを提起を することができるということですが今回は 善意の特定証権に通しているわけなのでA
は占有回収の訴をDに対して提起をする ことができませんから本問の結論としては 誤りということになっていくわけ です次に第2も見ていきますね3ページの 真ん中の第2も見ていきましょうここで 問われている論点っていうのは1回条文 立ち返りますね条文見ていきましょう戦友 回収の訴えは戦友を診断したものの特定証 人に対して提起をすることができない ただしその省matter人が信達の事実 を知っていた時にはこの限りではない つまり悪意の特定証人であればこの戦友 回収の訴を提起することができるという ことになるわけですよね悪意の特定証権人 に対してはいけるわけなんですけれども この知っていたっていうのは半神反義じゃ なくて完璧な悪意が必要になりますこの 悪意の特定証権人に対して融回しの歌を 提起することができるこの知っていたって いうのは半神半疑レベルじゃなくて完璧な 意味での悪意が求められていくわけであり ますですからその観点から見ていくと第2 問の問題です本問で問われてるのはbはa が占有する動産候補のみCに売却をしたC は品である可能性があると認識していた ものの動産項が品であることを知ることは できなかったつまり半身反義の状態である とこの場合においてAはCに対し占有回収 の訴えをすることができるということです が本問は誤り今回Cは半身反義の状態で あって完璧な悪意ではありませんですから 戦友回収の訴を提起することができないと いうことになっていくわけであります従っ て本問は 誤り以上の点まとめていきますけれども 戦友回収の訴えは善意の特定証権に対して 提をすることはできませんそしてこれに 関しては絶対的構成が取られているんだ 一旦全の特定証人を通せば後の人は保護さ れるということ加えて悪意の特定証券人に 対しては提起をすることができるわけです がここの悪意っていうのは完璧な悪意が 要求されていく半神反義レベルではでき ないということであり ますでは続きまして4ページをご覧 ください4ページの民法の2つ目の予想 分野見ていきますね2つ目の予想分野は 物件法改正になっていき ますではこちら見ていきましょうコメント のところです民法改正え物件法に関しては 令和5年度本試験より出題範囲となって おり当時の本試験での出題数は計3月と 少なかったが今年の本試験において本格的 な出題がされる可能性は大いにあるま今回 はこの改正事項の中でも所在等不明共有者
の持分の取得これをテーマとしてお話をし ていきたいと思い ますでは5ページの下の表をご覧ください こちらの表で見ていきますねまず内容の ところ見ていくことにします共有不動産の 共有者の一部が所在等不明である場合には 裁判書は共有者の請求によりその共有者に 所在等不明共有者の持ち分を取得させる 裁判えこれをすることができるんだという こと です 例えばABBCの共有の高土地があったと しますABBCの共有の高土地があったと してCの素材が知れませんということです ねCが所在等不明共有者であるでそれぞれ え持分が1/3ずつあるわけですがここで Aが請求をすることによっ てこのCの素材等不明共有者の持分を請求 をしたAに取得させることができるこれが 素材等不明共有者の持ち分の取得という ものになっていきますただこれに関しては できない場合が2つあるんですねこの制限 のところに関して見ていくわけであります ではそれぞれ解説文のところで見ていき ましょう第3問の解説のところご覧 ください第3問の解説の部分見ていきます ね素材等不明共有者の持分の取得の裁判の 請求があった持分にかかる動産について こっからマークポイントです共有物分割 または遺産分割ここまで共有物分割または 遺産分割の請求がありかつ所在等不明共有 者以外の共有者が当該請求を受けた裁判所 に当該裁判をすることについてマーク意義 のある旨の届け出をした時には裁判所は 当該裁判をすることができ ないつまり例えばAからこの所在等不明 共有者の持ち分の取得の請求がありました という時にBがあ共有物分割を請求し そして意義のある胸の届け出をしたつまり Bから文句が言われた分割でやりたいから ダメていう風に意義の届け出があればこの 場合裁判所は先ほどあったような今初代等 不明共有者の持分の取得の裁判をすること ができないということになっていくわけ ですじゃあなんでこうなっているのかと いうとコメントのところ見ていきましょう 制度趣旨見ていきます ね所在等不明共有者の持ち分の取得の請求 があった不動産について他の共有物分割 遺産分割が行われておりその中で所在等 不明共有者の持ち分も含めてマーク共有物 全体について適切に分割されることを希望 する共有者にマークです共有物体について 適切に分割されることを希望する共有者が いる場合には共有者全員の関与の元で適切
な分割をするべきつまりベッド分割が進行 中ならそっちでやりたい人がいるでしょっ て ことこのように分割でやりたい人がいる 場合には所在等不明共有者の持ち分の取得 の裁判をすることができませ んではこれを踏まえて第3問の問題見て いきましょうか 第3問の問題本問で問われているのは所在 等不明共有者の持分にかかる不動産につい て共有物分割の請求または遺産分割の請求 が あり意義のある胸の届け出をした時には 裁判所は当該裁判をすることができないと いうことですが訪問は正しいということに なっていき ますこれがNGの1点目ということになる わけですではもう1つえNGの2つ目を見 ていくことにします第4問をご覧ください 第4問の解説の1行目から見ていきます ね素材等不明共有者の持分が相続財産に 属する場合共同相続人間で遺産の分割をす べき場合に限るつまりは遺産共有のケー スってことですこの場合に相続開始時から マーク10年後経過していないにマーク 10年を経過していない時には裁判所は 所在等不明共有者の持ち分を他の共有者に 取得させる旨の裁判をすることができない ということなんです ね例えばどういうことかと言うと画面の方 をご覧 ください例えばDが死亡してabBCが その共同相続人だとしますでその中のCが 所在等不明共有者ということになっていて この所在等不明共有者の持ち分が遺産共有 であるとでこの場合に続開始から10年が 経つ前に関しては先ほどのよう な初代等不明共有者の持ち分の取得の裁判 をすることができないということになって いくわけですなぜかと言うとコメントの ところ見ていきましょう指印のところ見て いきます ね所在等不明共有者の持ち分の取得があっ た場合相続人が持分を他社に上とした場合 と同様に当該取得の対象となる持分は遺産 分割の対象から除外されることになる ところつまり所在等不明共有者の持分の 取得これがされてしまうとこの真義が持っ ていたあこの遺産共有になっている持分 っていうのは遺産分割の対象外ということ になっていくんですねでこのような扱いを すると遺産分割上の権利つまり特別受益 だったり基分をその中で主張する権利が 失われるためこっからマークポイントです 特別受益基分を主張することができる続
開始から10年の間にマーク特別受益起用 分を主張することができる相続開始から 10年の間においては所在等不明共有者の 持ち分の取得ができないとして いるつまり相続開始から10年間に関して はその遺産分割内において特別受益だっ たり起用分を主張することができるわけ ですよねその利益を奪っちゃいけないよね ということでこの10年経つ前に関しては この所所在等不明共有者の持ち分の取得の 裁判をすることができないとしているわけ でありますで裏を返せば10年が経過をし ましたということであれば遺産分割による メリットってのが乏しくなるわけですよね 10年経てば特別受益基業分の主張をする ことができなくなる遺産分割による メリットが乏しくなるわけですから10年 を経過すれば持ち分取得の裁判をすること ができるようになるわけであります ではこれを踏まえて第4問の問題見ていく ことにします本問で問われてるのは所在等 不明共有者の持ち分が相続財産に属し共同 相続民間で遺産の分割をすべき時には裁判 所は持分後他の共有者に取得させる裁判を することができないということですが実は 訪問は誤り先ほど言ったように裏を返せば 10年経ったらできるって話ですよね年 経過していればばできるわけなので一律 することができないとしている訪問は誤り となっていくわけであり ます今回この10年っていうのは機械的に 覚えるんじゃなくてこれは特別受益基業分 の主張をすることができる10年この期間 に対応しているんだっていうことを抑えて いくと覚えやすいかなという風に思い ます話まとめていきますが今この制限の2 点を見ていきました1点目としては共有物 遺産分割の請求があって意義のある胸の 届け出がされた場合にはできませんよ そして2点目が遺産分割をすべき遺産共有 になっている時にその遺産分割内で起分 特別受益を主張する利益があるんだから これを奪っちゃいけないよねっていうこと でその締め切りになっている10年後経過 していないということであればえこれは 認められないということでありますこの2 点が所在等不明共有者の持の取得の裁判の NG種ということになっていくわけなので この2点押えておいてください ねでは続きましてえ6ページをご覧 ください審査請求について見ていきます不 動産登記法の予想分野は審査請求が硬いか なというところですこちら星3つになって いきますねコメントご覧ください審査請求 は4年の周期で出題される傾向にあるため
まこのようにま4年ごとにま綺麗に出題が ばらけているということになっいくわけ ですねですから今年の本試験で出題される 可能性が極めて高い発展的な知識まで含め てしっかり抑えるようにしていき ましょうではその下理解のポイントの コラムですね審査請求の処理はクレームを イメージして抑えるということです一旦 画面を止めてえこちらお読みいただければ と思い ますでは終わりましたら再開をしていき ますねでは今見ていただいた文章の中で こちらですね当期間を経由すするのがなぜ かという話をしていきますなぜ部下である 当期関を経由して審査請求クレムをつけて いくのかこれに関しては下の補足問題の コメント見ていき ます1行目マーク当期においてはその戦後 が重要な意味を持つので2マーク当期に おいてはその戦後が重要な意味を持つ つまり当期はスピードが命であるわけです ねですから事件を迅速に処理する必要が あるところ当期間を経由させることで当期 官に最高の機会を与えているのであると つまり当期はスピードが命ですから当期官 を経由してでえそれで理由があるとあそれ はそうだないう風に判断した場合にはそこ で迅速に相当の処分をすることができる ように経由をしているということなんです ねで一方でえ別におかしくないよ理由が ないと判断した場合に関してはこの当期官 の意見をふしてえ法務局長にえこのボスに 上司に送付をするということになっていき ますではこの構造を把握した上でえ7 ページの第5問見ていくことにします7 ページの第5問見ていきましょう本問で 問われてるのは当期間は審査請求に理由が あると判断した場合には事件を法務局長に 送付しその長の命令により相当の処分をし なければならないということですが本問は 誤りこれだと経由させた意味がないですよ ね当期官が理由があると判断したら スピーディーに相当の処分をすることが できるようにわざわざ経由しているわけ ですですから理由があると判断したら当期 関が相当の処分をすることになります本問 で問われているように法務局長に対して 送付をしてその長の命令により行うという わけではありませんそもそもなんで経由さ せているのかその構造を掴んでいればこの 問題は解けた判断することができた問題か というふに思い ますでは次に第6問見ていきましょう7 ページの真ん中の第6問先に問題の方から 見ていきます本問で問われているのは当期
申請の代理権の授与の意思表示を取り消し たにも関わらず既に交付していた異人上に 基づく申請により所有権遺の登記がされた 場合には審査請求をすることができると いうことですが実は本問は誤りですこれは 審査請求をすることができないケースに なっていくんですねでこれに関して右側の まとめで順を折って説明をしていくことに し ます審査請求の対象は当期関がすることが できる全ての処分例えば当期事項証明書の 交付に関する処分なんかに関しても審査 請求の対象になるわけですねえつまりこの 審査請求の対象っていうのはかなり広く 返されているわけですただしその下当期官 がした当期の実行行為に対する請求に関し ては当期官が職権で抹消できる売買に限り することができるとされています当期を 当期関が行ったこの実行行為に対する審査 請求に関しては直見抹消できるケースに 限定されているんですねじゃあ職権満所 できるケースってどんなケースですかって 言うとその下のそして当期関が職権満所 できる場合とは当期が無効であることが 当期記録上明白な場合例えば ですとか二重登記されている場合ですとか 無効であることが当期記録上明白な場合に は直見マシをごすることができるわけです が裏を返すと当期記録上明白でなければ 直見満所をすることができませんからだ から審査請求の対象外ということになって いくわけですじゃ本文のケースはどうか 代理権の重要の意思表示を取引したにも 関わらず当期の申請がされてしまった つまり当期申請の代理権の建設が感化され た期ということになりますがこれは向こう であることが当期記録上明白とは言えませ んよね代理権がないなんていうこと当期 記録を見ても分からないわけですですから 直見で抹消をすることができないわけなの で審査請求をすることができないという 結論になっていくわけ ですでは左側のコメントをご覧 ください直見抹消が可能な場合に限定され ているのは審査請求があった場合に当期間 自らの相当の処分をする関係上もはや当期 関がその誤りを訂正できないような場合に は審査請求を認める実益がないからである とつまり当期関が対応できないことに クレーム言われても困るよっってことなん ですね当期関が対応できないことに クレーム言われても困るよっって ことですから本文においては今回は当期 記録上明白なケースではありませんね 向こうでやることがですから当期関が直見
回しをすることができないつまり当期関が 手直しできない事例ということになるわけ ですゆえにこれに文句言ったってしょうが ないですから審査請求をすることができ ないという結論になっていき本問は誤りと なるわけでありますでは要点まとめていき ます ね当期間の下た処分に対して審査請求って いうのは広く認められていくんですけれど も当期官が行った当期の実行行為に関して は当期官が自分で手直しをすることが できるつまり職権で抹消できる場合に限り することができるわけですそしてそれは 当期が無効であることが当期記録上明白な 場合なので明白じゃないケースに関して 審査請求がされてもそれは受けつけられ ませんよという結論になっていくわけで あり ますでは審査請求に関しては以上です続き まして8ページの大きな4番会社法の新株 予約権を見ていきます会社法の出題予想 分野は新株予約権ということになっていき ますこちら出題予想度は星2 つメ見ていきましょう進化部予約権は発行 と行使の場面で正確に分けて抑える必要が ある問題部の読み取りでもどちらの場面が 問われているのかお意識するようにし ましょう発行の場面が問われているのか 講師の場面が問われているのかそれによっ て結論だいぶ変わってくるわけですから そこを普段の学習からしっかり意識すると ともに問題部の読み取りにおいても しっかり注意をするようにしておいて くださいでは発行と行使の区別といういう ことでこちらの表を見ていきます募集株式 の発行新株予約権の発行そして新株予約権 の行使の比較です ねでこれに関して理解のポイント見ていき ましょう上記の比較表の抑え 方総裁の過と検査薬の調査の用品に関して は株式発行の場面の規定なんだという風に 押えておいてくださいそのため株式を発行 しない新株予約権の発行では適用があり ませんが新株予約権の行使がされてそこ から株式の発行がされるわけですから行使 の場面ではその適用があるということなん ですねですからこちらの表の抑え方として はこことここはパラレルに同様に考えて いけばいいということ です例えば総裁をすることができませんし 検査薬の調査これが現物出資があれば必要 になっていきますさらには効力発生日に 関しても実質的には同じですつまり募集 株式の発このの効力発生日っていうのは 払い込み起立であればその払い込み起立
払い込み期間であれば出資の履行日要する に払い込んだ日にその効力が生じるわけ ですよねで新株予約権の行使に関しても 行使がされた日に払い込むれるわけです からこれに関しても払い込んだ日という 意味で同じになっていくわけですこのよう に募集株式の発行と新株予約権の行使に 関してはどちらも株式が発行される局面で あるわけなので結論が共通していくという ことですそれに対してま中の新株予約権の 発行に関しては株式が発行される局面では ありませんので扱いが異なりますつまり 総裁に関しては承諾があればすることが できますし現物趣旨があったとしても検査 薬の調査は不要でありますし効力発生日に 関してもその割当日とされているわけで ありますですからここのグループを イコールで抑えておいて残った発行に関し ては違う結論なんだという風に抑えていく とこの表は抑えやすいかなという風に思い ます今発行と講師を区別するというところ それを強調してお話をしましたこの観点 から抑えていただきたいのが第7問であり ます9ページの第7問をご覧 ください9ページの第7問まず解説の ところ見ていきます ね公開会社が株主に新株予約権の割当てを 受ける権利を与えずに新株予約権を発行 する場合にはその都度1募集進株予約権に つき金星の払い込みを要しないとすること が新株予約権を引き受けるものに特に有利 な条件である時または2募集進化部予約権 の発行における払い込み金額が特に有利な 金額である時を除きこの発行におけると いうところマーカーを引いておいて くださいでこれら丸1番丸2番の場を除い て取締り厄会のきによって募集事項を定め なければなりませんつまりちも有利発行と して位置付けられるのは発行段階で有利な 条件になるケースなんですねこの丸1番と 丸2番が有利発行のケースに当たるわけ ですがこれは有利発行ということで発行 段階で有利な条件になるケースこれに関し ては株相加の特別決議が必要になっていく ぞという風にされているわけです何も 難しく考えることはありませんつまりは ネーミング通り有利発行なんだから発行 段階で有利な条件になるケースこれ場合に え適用されるんだという風に抑えておけば いいわけですそうすると上の第7問の問題 見ていきます ね本問で問われているのは公開会社におい て募集進化部予約権の行使に際して出資さ れる財産の価格が特に有利な金額である 場合には募集事項の決定は株主総会の特別
決議によらなければならないということ ですが訪問は誤 あくまで今回は行使段階で有利な金額で あるにすぎませんですから有利発行には 当たらず株の相の特別決議は必要になら ないということですここでは発行と行使を しっかり区別した上であとは有利発行と いうネーミング通り発行段階で有利な条件 になるケースについてのみえその発行有利 発行としての適用があるんだということを 抑えておいて くださいでは次に第8も見ていくことにし ます第8問の先にコメント欄のところ見て いきますね前提を確認していきます募集 株式の発行の話ですが募集株式の発行の 場合にマーク募集株式が譲渡制限 株式募集株式が譲渡制限株式である場合は 定款に別なのめがある場合を除き株主訴の 特別決議取締り会設置会社であれば 取り締まりや会決議によって株式の割当て を化する関する事故をを定めなければなら ない割当てに関する事項に関してもマーク をしておいて くださいつまり譲渡制限株式の割当てを するにあたってはこの決議要件定款で別断 の定めがなければえ株の相会の特別決議 あるいは取り締まり厄介決議これが必要に なっていくということなんです ねそしてこれと同じ決議要件が新株予約権 の割当てでも要求されるパターンそれが2 つあるわけです解説のところ見ていきます ね第8問の解説 です募集進化部予約権のマーク目的である 株式目的である株式の全部または一部が 譲渡制限株式である場合丸2番マーク募集 新株予約権募集新株予約権が譲渡制限新株 予約権である場合にはま同様の決議が必要 になっていくということなんですねこの1 番と2番の区別よく分かりませんという 質問をよくいただきますが右側のイラスト ご覧 くださいこのイラストの意味としてこの 四角枠が新株予約権でそれを行使すると もらえるのが中に入ってる目的株式だと 思って くださいそして丸1番のところで言って いるのは目的株式に譲渡制限がふされて いるケースそして丸2番っていうのはこの 新株予約権の枠自体に譲渡制限がふされて いるよということなんですね丸1番が新株 予約権自体に上土制限をされてないんだ けれども中身の目的株式に譲渡制限がふさ れている一方丸2番の場合っていうのは 中身の目的株式には譲渡制限ふされてない んですけれども新株予約権の枠自体にえ
譲渡制限がふされているケースであると いうことですこの丸1番丸2番のケースに おいて先ほどコメントで見てきたような 譲渡制限株式の割当ての時と同じ決議要件 それが要求されているぞということなん です ねこの丸1番と丸2番の区別まだピンと来 ないよという方に関しては箱の中にある ボールに例えて考えてみてくださいつまり この新株予約権が箱であってそしてえこの 目的株式が中に入ってるボールだと思って くださいですからボールの方に譲渡制限が かかっているのが丸1番で箱の方に譲渡 制限がかかってるのが丸2番のケース そんなイメージを持っていただくと分かり やすい ですではこれを踏まえて第8問の問題見て いきましょう本問で問われてるのは募集 新株部予約権の目的である株式の一部が 譲渡制限株式である時に は割当ての決定は取締り厄介の質疑に寄ら なければならないということですが本問は 正しいとなっていきます今回は目的株式が 譲渡制限株式であるわけですからこの イラストで言と丸1番のパターンに当たる わけですよねですから先ほどの譲渡制限 株式の割当てと同じ決議要件が要求される つまり定款で別段の定めがなければ株の遺 かの特別決議あるいは取締り屋会設置会社 であれば取り締まり会決議になる今回は 取り締まり学会設置会社であるわけなので この取り締まり学会の決議によって割当て の決議を行っていく必要があるぞという こと ですでは新株予約権に関しては以上です 続きまして10ページをご覧ください 大きな5番の商業登記法解散生産の登記に 入っていきます商業登記法の予想分野は 解散精算の登記です出題予想度は星2つ コメント見ていき ます解散生産に関する登記においては出題 周期の観点からは令和4年度の本試験で 解散に関する登記が出題されているため 今年の本試験では生産に関する登記が出題 される可能性が高いですから特に生産人 関係についてしっかり抑えていただきたい ところ ですではこの生産人の登記に関してえ今回 は解説をしていくことにし ます下のこちらですねえ理解のポイントの コラム一旦画面を止めてお読みいただけれ ばと思い ます終わりましたら再開をしていきますね 話の出発点としてはまず基本知識として 株式会社の最初の生産2の登記では必ず
定款を添付するという話がありますよね これがなんでなのかっていうところからお 話をしていき ます画面の方をご覧ください定款で当期間 が最初の生産人の登記で何をチェックする かって言うとチェックリストが2つある わけなんですねまず1点目生産人会を設置 しているのかしていないのかそして2点目 定款で生産人が定められているのか あるいはそれがいなくて法定生産になって いるのかこの2点をチェックするために 定款を添付させていくということなんです ねでこの2つ目のチェックリストに関して はこのような順で生産人っていうのは就任 をしていくわけでありますが定款で定めて いた場合あるいはそれがいなくて法定生産 人が就任をするというケースに関しては これ定款絡みになってるわけですよね定款 の定めの有が関わってくるということ ですですから裏を返せばこの1位のB つまり株主総会の決議によって成人された 場合と丸3番裁判所によって成人された ものに関しては定款とは無関係ということ になっていくわけですこの1bと丸3の 場合に関しては定款規定とは無関係のこと になっていくですから例えば株主総会の 決議によって生産人が選任されましたと いうことであればこのチェックリストの2 番に関しては取っていくですよね定款は無 関係なのでチェックリストの2番が取れて いくわけですただそれだとしても結局定款 をチェックして生産人会を設置しているの かしていないのかこれをチェックする必要 があるわけだからこそ最初の生産人の登記 において株式会社の当期では必ず定款を 添付するという理屈になっていくわけで あり ますそうするとじゃあ例えば特例有限会社 ではどうでしょうか特例有限会社であれば 生産会はそもそも置けないわけですよねと なるとチェックリストの1番が外れていく わけです特例有限会社においてはそもそも 生産委員会を置くことができるわけでは ありませんからですからこれが取れていく ということなんですねとなると残るところ はチェックリストの2番だけである とですからそこでチェックリストの2番の 観点から定款に無関係な例えば株主総会の 決議によって選任されたということであれ ばこのチェックリストの2番も続けて取れ ていくわけなので結果定款をチェックする 必要がなくなるねということになるわけ ですではこれを踏まえてえ11ページの上 の方をご覧ください11ページの上の方第 9も見ていくことにし
ます本問で問われてるのは特例有限会社が 株主総会の決議によって生産人を選任し ましたこの場合に定款を添付しなければ ならないということですが訪問は誤り順を 追って説明をしていきましょう当期間の 低下のチェックリストとしてこちらの2点 がありますよということでしたねところが 特例有限会社においてはそもそも生産委員 会を置くことができませんからこの チェックリストの1番が取れていくさらに 今回は株主総会で選任されているわけです からこのケースだから定款の定めとは無 関係であるゆにこの場合にもチェック リストの2つ目を消滅をするとなると当 期間は低下をチェックする必要がなくなる よねゆにこの場合には低下の添付が不要と いうことになっていくわけでありますです から株式会社においてはこのような定款の 添付が必ず必要になるわけですが特例 有限会社においてはそもそも制裁認会を 置くことができないこれによってチェック リストの1番が取れていく関係で常に つつけるわけではないという結論になって いくわけでありますちなみにこれは 持分会社に関しても同じことが言えるわけ ですね持分会社も生産認会を置くことが できませんから常にをつつけるというわけ ではないぞということ ですではえ次の話に進みますがチェック リストが2つありますよという話をしまし た生産人会を設置しているのかしていない のかという観点から定款をチェックするん だという話をしましたよねこのような チェックリストの1番の観点から言えるの が生産人会設置会社のさめっていうのは セットでチェックするからセットでし なきゃいけないですよということなんです ね生産人会設置会社の定めに関しては生産 人の登記でセットでチェックする事項に なっているわけですからその時に定めが あるならばセットで登記を申請しなければ ならないということになっていくわけで ありますそれが真ん中の補足問題で問われ ているところなんですね見ていくと生産人 の登記において は生産人後億での低下のさめがある場合に は生産人会設置会社である旨も登記をし なければならないということです生産人の 登記の中でセットでチェックすることに なってるんだから当然その時に定めがあれ ばセットで登記もしなさいよという結論に なっていくわけでありますしってこの補足 問題は 正しいさらに言うとセットで申請するわけ なので家電区分も同じグループということ
になっていきますそれが問われてるのが第 10問なんですね問題のところ見ていき ましょう本問で問われてるのは生産 株式会社における最初の生産人の就任の 登記 と生産認会設置会社のさめの設定の登記を 1の申請書で申請をする場合の登録免許税 の額は金3万6000円であるということ ですがセットでチェックするからセットで 申請しなきゃいけないだから課税区分も セットなんですね同じグループの括りに なるわけなのでこの生産人員会設置会社の 定めに関しても最初の生産人の就任分の 9000円このグループに含まれていく わけですですから今回の登録免許税の額は どちらも9000円のグループということ でまとめて9000円になっていく別枠で 3万カウントされるわけではありませんの で注意をしておいて くださいこのように生産人の最初の収入の 登記では必ず定款をつけなきゃいけないっ ていうのは多くの受験生が引ている基本 知識ということになってていくわけですが なぜ必ず添付をするのかそのわけを理解し ていくと特例有限会社持分会社では常に 添付するわけではないよという知識だっ たりあるいは合わせて生産認会設置会社の 定めも登記しなきゃいけないよっていう話 だったり生産認会設置会社の定めも同じ 課税区分になるよって話だったりそこに つなげることができるわけなのでしっかり え先ほどお読みいただいたコラムのところ を理解をしておくと記憶の節約になるん じゃないかなという風に思います それでは第2部の解説は以上になっていき ますえ続きまして第3部として私が担当 する直前講座受かる択一式出題予想演習 こちらの紹介をしていきたいと思います今 皆さんが受けていただいたのはその体験 講義の位置付けにもなっていきますこの 講座のコンセプト一言で言うとこちら出 予想のアウトプットですつまり2024年 本試験で出題が予想される論点に特化をし て学習をしていくこれによって出題予想に 基づく優先順位をつけた学習が可能になる しアウトプット問題演習の形を取ることに よっ て本試験特典に直結をする学習をすること ができるまさらに定着度を確認しながら 進めることによって直前期のペース メーカーとして活用をすることもできる わけであり ます事項前後のイメージでありますが事項 前としてはこういった状態になってる方も 多いと思います直前期の学習をどこから手
をつけていいのか分からないあるいは基準 点周辺からもう1歩の伸びが欲しいまたは 最後の2択で自信を持って判断できるよう になりたいそういった方がこの講座を 受けることによって直前期学習の優先順位 が分かる加えて基準点から合格点まで点数 を伸ばすことができるその上乗設定の確保 の助けになっていくさらに最後の2択に 強くなることができる座が終わればそれが できるようになるそういった講座になって い ますではこの講座の流れですが知識完成編 と総子上げ編の二部構成になっています まず知識完成編のところでは基本的に1問 一等さらに行動しやすい論点に関しては2 択形式こういった形式の予想論点の演習で 知識を完成させていきますそして次に第2 部の総仕上げ編においては択の本試験形式 の予想論点の演習で総仕上げを行っていき ますこのように1択から2択そしてへの 流れでの演習が可能になっていくという ことです ねでは1つ目の知識完成編のポイントで ありますがポイントの1番1問一等を中心 とした問題演習これを通して予想論点を 習得していきますここでは丸バで知識の 確認をすることができるので確実に点数に つげることができできますし制度全体の 解説もしていきますのでインプットの不足 えこれを補えるようにもなっています次に 2点目として行動しやすい知識を2択形式 で比較整理をしていきますこれによって 決定力を高めて最後の2択に強くなること ができるんですねさらにこの知識完成編で は補足問題の記載もしていまして十分な 問題を確保していますですからこの出題 予想分野として扱った分野に関しては ベッドご自身ので過去問に取り組む必要が ありませんのでそういった意味では皆さん の直前学習の負担を軽減するという 位置付けでのお取り組みもすることが できるわけ ですそして第2部として総子上げ編の ポイントですポイントの 1本試験と同じ誤択一式の形式で出題形式 も含めて予想をすることができるつまり この論点に関しては当期記録問題で狙われ やすいあるいはここは横断的に問われ やすいんだそういった出題も含めて予想を した問題を解くことができるわけなので 応用的な出題形式にも対応することが できるようになるということ ですかつポイントの2番目午前午後35問 の問題を解くわけなので試験戦略の構築が 可能であるということです三角の使い方
だったり午後択一式を1時間で解き終える 方法このような解放の実践指導もしていき ますのでこれを通して特典力がアップを するこのような工夫を凝らした カリキュラムになっています ちなみに予想講座ということでま昨年度の 的中実績を出しておきますこちら2023 年合格目標の口座の的中実績表の出し方と しては3月以上適中した問題を掲載してい ますもちろん1足適中してる2足適中して いるそういった問題も入れればもっと多い ということになっていき ます3足以上的中した問題としては午前の 部が計13問トータルで63足の部に関し ては14問でトータル74 足2022年度の的中実績に関しては15 問で70足午後の部が14問で69足 さらに2021年の的中実績が午前の部が 計12問で64足そしてえ午後の部が計 19問で82足ということになり ます加えてえ実際に受行をして合格をされ た方の声を紹介していきます例えば実際の 本試験にもほぼ同じような足が出た時には 一緒の感動すら覚えました暗記の量を理解 重視の解説で減らすことができた適度な量 に絞り込まれれた教材によって直前期に しっかりやったという自信を持つことが できたありがたいことにこういった声を いいています口座検討されている方はその 時の参考にしていただければ幸い ですでは受かる択一式当座の対象者であり ますが2024年合格を目指す全ての方と なっていますのでどのレベルにある方でも 一通りの学習を終えた状態にあればレベル に分けてえメリットがありますのでえご 参考にしていただければと思います例えば 基準点に満たない初中級者の方であれば 直前期の優先順位をつつけることができる わけですしまで仕上がっていなかったとし ても予想を活用して効率よく力をつけて いけば一発逆転も可能になっていくという こと ですそして基準点周辺の中上級者の方に とっては予想論点は発展知識まで抑えて いくこういった勉強をすることによって 合否を分ける問題正当率がやや低くなる 合否を分ける問題も正解できるようになる なのでより合格を確実にすることができる ということですこのように初中級者の方で あっても中常級者の方であってもどちらも フィットするような講座になっていますよ ということ です最後にえ口座のカリキュラムについて でありますが4月2日のところから配信が 開始していきます回数としては知識完成編
が8回総子上げ編が2回分量としては知識 完成編が各回120問1問一等形式です 総子上げ編が各回35問で5択一式の形式 になっていきますちなみに知識完成編に 関しては補足問題もありますので直前期の 演習として十分かつ繰返せるような分量に なってい ますそしてこの講座は直前期学習の決定版 と言える直前パックの中に含まれています のでこちらも合わせてご検討いただければ と思いますそれでは今回の内容は以上です 是非今回の講義内容を今後の学習に生かし ていただければと思います最後までご視聴 いただきありがとうございまし た
司法書士試験の学習範囲は非常に広いため、本試験で戦える高い精度の知識を持ち合わせるためには、メリハリの付けた学習が必要です。そして、出題予想はそのメリハリ付けに当たり、非常に強力な武器になります。
そこでこの動画では、2024年本試験において出題可能性が高く、かつ差が付きやすい論点を問う予想問題10問の演習・解説を行います。これにより、予想論点に強くなるのはもちろん、出題予想分野も把握できるので、今後の学習のメリハリ付けに役立ちます。
また、択一式の出題予想講座として実施する「うかる!択一式~出題予想演習~」の体験講義も兼ねているため、こちらの講座を検討中の方もぜひご視聴ください!
【資料】
https://www.itojuku.co.jp/pdf/shihoshoshi/20240323_syutudaiyosou.pdf
【「2024年合格目標 うかる!択一式~出題予想演習~」の詳細はこちら】
https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihoshoshi/kouza/24C13001.html
【伊藤塾司法書士試験科ホームページはこちら】
https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihoshoshi/index.html
#司法書士 #司法書士試験 #伊藤塾 #2024出題予想 #択一式