【光る君へ】宇多源氏の家系が大爆発!源雅信の子孫たち
皆さんこんにちは小葉です今回の小葉 チャンネルの題名はこちら宇田源二の角で 源の政信の子孫は舞踏派今回のコバ チャンネルは源の政信とその子孫たちに ついて紹介したいと思います源の正信と いえば今年のタガドラマ光る君江に序盤 から登場している人物で増岡トルさんが 演じられているので分かりやすい人物かと 思いますそして同じく登場している黒木は さん演じるとこ林子が娘となり直近で紫 式部演じる吉孝ゆり子さんとの関わりが 印象的に描かれているかと思いますそんな 友子の父にあたる源の政信他にも色々な 側面を持つ人物となります今回はまた子孫 をたどるシリーズということでこの源の 政信の流れを見ていきたいと思いますこの 源の政信様々な角度で見ていける人物と なりますが最大の側面といえばやはり宇 源二という点ではないかと思いますう事が ここで登場するわけですが現地にも色々 ありまして世の中的には源の義友や足日 高内などの聖和源治が有名かと思いますが この宇源二もその名の通り宇田天皇を外 する名門の原子となります簡単に宇田天皇 から見ていきたいと思います宇田天皇第 59代天皇在位887年から897年宇田 天皇といえば本来行為を継ぐことはない ところから天皇になった天皇として有名 です元々父の高校天皇も55歳の時に時の 藤原北家の権力者藤原の元常が バックアップしたことによって即位する ことになった天皇となりますそして高校 天皇の後にはサヤ新王が行為につくと考え られていたことにより高校天皇の巫女たち は親戚降下することになりましてこの宇田 天皇当時定王も親戚降下し源のせとなって いますそして高校天皇の後に誰が即位する のかということになった際には先ほどの定 新王が候補として目されておりましたが その母藤原の講師と元は舟だったという こともありましてサダ王が皇族に復帰する ことになって第59代宇田天皇として即位 することになりますこの元は絶大な権力を 誇っている藤原家の中でも代表格の人物と なりますがこの元が存命中は宇田天皇は赤 事件で元を怒らせてしまいまして何かと 元常に気を使う必要があって政治がうまく できない期間が続ことになります891年 に藤原の元が亡くなると宇田天皇は申請を 行うことになりましてセシ関白を置かない 政治を行っていますそんなタイミングで後 の世で学問の神様と呼ばれる菅原の道も表 部隊に登場することになりますこの宇田 天皇の神聖は官平の地と呼ばれています そして宇田天皇は藤原北家と一定の距離を
置いて多くの人物を登用していくことに なります897年には交代使に上位し第5 天皇が即位することことになりましてこの 宇田天皇は大場天皇となりその後に出血し 法王となっていますそして宇法王は931 年に防御することになりますがこの宇田 天皇から宇田源子が始まっていくことに なります宇田天皇の巫女たちの子孫に源の せが与えられていくことになりますが中で も一際栄えた家系があり今回の動画はその 家系を紹介していくことになりますこの宇 天皇には先ほども登場した第5天皇の他に も多くの王子工女がおりましてその中に大 王子として誕生しているのが厚み新王と なります厚み新王は893年生まれで 967年に去している新王となりますこの 厚み新王の2人の子供たちは大きく出世を 果たしていくことになるわけです厚み新王 の3なには今回のタガドラマ光る君江にも 登場している源の正信そして4名には源の 茂信が誕生していますこの4男のしのも 光る君に登場する人物となります厚の子供 ということで樹位の下となり途中にアナの 変などもあり出世スピードが鈍ることに なりますが最終的には小2位まで登り宇 大臣そして兄の死後には謝大臣を務める ことになる人物ですそしてこのシゲノムの 子供たちからも広がっていくことになり ますそして今回の宇田源二の紹介は宇田 源二の中でもそのしのの兄政信から始まる 家計を紹介していくことになりますこの 厚み新王の三男本の正信今作ですでに黒木 はさん演じ娘の友ことなやり取りが印象的 な人物となります920年に誕生しており まして父は厚み新王母は藤原の時平の娘と なります先ほどの弟の茂信も母は藤原の 時平の娘となっています藤原の時平といえ ば大子天皇の美男において左大臣まで 登り詰めておりますが若くして亡くなって いる藤原ホッケの人物となりますという ことはこの正信も藤原北家の父が流れて いるということになりまして藤原北家より の図をまとめてみると藤原の時平の孫に 当たります藤原北家は時平の弟の田平の 家計が本流となって続いていくのですが この田平の子供がモスその子供が藤原の 金家ということになりますので源の正信 藤原の金家は鳩同士ということになります ということは後々に婚姻することになる 藤原の道長と友子は鳩の子供同士という ことになるわけですこう見ると光る君へも また別角度で見えてくるかもしません他の 光る君への登場人物との関係を見ていくと 関白として登場している藤原のヨタこのヨ ただも藤原の田平の孫に当たるので藤原の
元まで戻ると鳩ということになりますが この藤原のよりただの母も藤原の時平の娘 となりますので鳩と言いつついこにもなる という奇跡的な関係図が出来上がって しまいます源の政信は皆本のせを与えられ た宇源二とはなるものの藤原ホッケとの 関係は非常に濃いものとなりますこれは源 の正信と藤原ホッケとの関係を表したもの ですが新王の子供ということで天皇家側と の家計図を見ていくと第5天皇の子供たち は全ていということになってしまいますと いうことは第61代須天皇第62代村上 天皇謝大臣源の高明は従子ということに なりますちなみにこの村上天皇の巫女には 延雄天皇がおりまして光る君江では吉田 よさ演じる藤原の金家の娘が代しています この関係図だけですでにほとんどの人物が 光る君えに登場しているということになり ますそして藤原の道長娘の友子の間には後 に寄り道が誕生しておりましてこの家計は 藤原北家着流して続きご石家に別れていく ことになりますのでここにも正信の結 particularは続いていくことに なりますこの政信も父が厚み新王という ことで樹医の下となりう権の中将や クロードの塔そして参議となり苦行に列せ られることになりますそして9777年に は宇大臣978年には佐大臣となってい ます991年には先ほどの弟のしのが宇 大臣となり兄弟で謝大臣宇大臣を務める ことになります993年に亡くなることに なりますがこれより少し経つと娘友子の夫 である藤原の三永とその間に生まれた子供 たちが中心となる時代がやってくることに なりましてその足がかりを作った人物と 言えるかもしれませんそしてこの正信は 多くの子供たちに恵まれておりましてここ から宇事が大きく広がっていくことになり ます今回はマノの子供たちの中でも源の 時中スのり時方の家計を見ていくことに なりますまずは政信の長男となる源の時中 この時中の家計も太く後の世まで続いて いく家計の1つとなります時中が生きた 時代はほとんどが父正信と共に生きた時代 となりますまさに権力争いのまた中で大臣 のポストはもちろんのことを多くの養殖に は重要人物たちがついおりましてある種 渋滞状態となっていますそんな中一条天皇 の即位に伴い小3味まで登り3議となって います藤原の道長が権力を掌握している 時期には12位ダイナゴンとなっています そして時中の子供の源の成正この成正は 藤原の道長がより道の時代を生きている 人物で最高油は少子の女となっています やはり石間家と共に生きていく時代そして
陰性に切り替わっていく時代をこれから 迎えていくことになりまして以前のような 小心を果たすことはできなくなってきてい ます成正の子供の好道は参議となって苦行 に列せられることになりますがザの第2と なり最終的にはジュニ位まで進んでいる 人物ですそしてその子供の政長と続きこの 子孫から始まっていく2つの家計に たどり着くことになります1つ目の家計は 価格がウリンケとなる岩た水源のアスの孫 にあたる常助から鶏岳が始まることになり ますこの常助の父は藤原の金なとなります が母ははアリスの娘ということで容姿と なり岳の外なっていますこの庭田常助は小 に権の中名言となり時は鎌倉時代中期と なりますこの常助の子供にはじ3民のし方 そしてその子供には新茂助がいますこの 茂助に至ってはキーマンとなる人物です この庭田茂助は鎌倉時代末期に生まれ室町 時代を生きておりましてう中将クロードの 塔そして参議となり苦行に列せられること になる人物です最終的には小2位権の大 ナゴまで登っていますこの頃の誠意大将軍 は足吉明長底の関白左大臣は九条つのり宇 大人はこのへ満つとなりますキーマン子と 茂助には娘がおりましてスコ天皇との間に 吉一新王が誕生していますスコ天皇の第一 王子として誕生しているのがこの義仁新王 となっていますこの義仁新王自体は行為を 継承することにはなりませんでしたがこの 家計は現代の皇室まで続いていくことに なりますそれと同時にこの義仁新王から 伏見の三宅が始まるということになります この伏見の宮宅は1番古い三宅となります この義人神王の子供には伏見の宮サフ神王 がおりましてその第一王子にはご花園の 天皇が誕生していますこの家計が進んで いき現代皇室まで続いていくことになり ますそして伏見宮サフ新王の大二王子には 趣の宮サ新王が誕生しておりましてこの 家計は趣の宮宅として続いていくことに なりますそしてこの伏見の宮宅も現代皇室 につがるという流れを持っています源の 政信から始まり現代皇室まで進んできて しまいましたそして現在王というドラマも 放送されておりますがそこにも関連して いるということを紹介しておくと徳川将軍 家は伏見の宮宅から多くの未所を迎えて おりまして10代目伏見の宮宅投手の伏見 の宮定夫新王の王女の明子女王は4代将軍 イナの未来所となっておりまして13代目 伏見宮家投手の伏見宮佐幸新王の王女正子 女王は8代将軍義宗のご連中となっており まして14代目伏見宮家投手の伏見宮国長 新王の王女マスコ女王は9代将軍家茂のご
連中となっています話は再び新田茂助に 戻りこの茂助の子供には新田つあがおり ましてつあの娘幸子は先ほど登場した 伏見宮サフ新王との間にご花園天皇と 伏見宮サ新王をことになりますそれにより つあはご花園天皇の外祖父ということに なりますつあの孫にあたる長かったの娘 麻子は5土門天皇との間に5柏原天皇が 誕生していますそして庭竹は容姿を迎え ながら続いていくことになりますその中で も途中ウリン家の大町家に末姫が容姿とし て入って家計が続いたり同じく売り家と なる大原家が別れて続いていくことになり ます正信庭竹伏の宮宅から現代の皇室と いう流れは面白い流れになるかと思います そして先ほどの庭たと同じ時期に綾野工事 家も別れることになりますアリスの子供の 野を外するとされておりまして途中とい ますが仮名を最高することになります綾野 工事家といえば画学で有名な家計となり ますそしてこの彩の工事家も価格は売り家 となりましてゴの中ナゴやゴのダイナゴン を多くの子孫たちが務めていくことになり ますそして話はまた源の正信まで戻って いきます政信の子供の時正から続く家計は 子孫は5つ事件を称していくことになり ましてこの家計の価格は半径となってい ますそして後半のメイはこの家計となり ますまた先ほどの源の政信まで戻り ましょう政信の4男にはスケのりがおり ますが門上省となっている人物でその後は 地方官を務めることになって一条天皇に 使えることになります少子の下3議となっ て苦行にでせられています998年に 亡くなることになりますがその子供には成 よが誕生していますそしてこの成よについ ては諸説ある人物となりますが今回はこの ままこの説で進んでいきたいと思います それは何かと言うと大江の国佐々木の庄に 住むことになりあの大江源子佐々木市が大 爆発していくことになる家計となります とにかくこの大江源二佐々木市は大きい 家計を作っていくことになりますこのな よりは若くして亡くなったとされますが 軽風は子供ののりに引き継がれていくこと になりますこの乗りが生きた時代は藤の 道長や寄り道が映画を極めた時代となり ますそしてその子供には常方さらにその 子供のためとと続いていき平安時代を生い ていくことになりますそしてこの頃には 佐々木氏はすに武となっていますそして 平安時代末期1人の人物が登場することに なるわけです佐々木たとの子供のその名も 佐々木秀吉平安時代マキの大美源二といえ ばこの佐々木秀吉を思い出しますというの
もとある描写で人々のの心に刻まれている かと思います前前作の大雅ドラマ鎌倉殿の 13人で佐々木のじいさんという呼び名で 話題になっていたのがこの秀吉となります この秀吉は源のたよの娘向こになっていた と言われ川原地との関係が深い人物となり ます源の縁友にとっては叔母の夫がこの 佐々木秀吉ということになります鎌倉殿の 13人では癖が強めで描かれておりまして 実際に癖が強かったかどうかは置いておい て佐々木秀吉は相当存のあった武将となり ます時代は大きな変化を迎えておりまして 陰性期間を経て兵家も力を有するように なっていきます1156年の法原の乱では 小白川天皇方につくことになり源の吉友に 属して戦いますがス上皇方には義の父のた よがいるという状況になっていますその3 年後の平治のランでは吉友方に属して戦い ますがこの戦いで現時方は惨敗し吉友は 殺害され呼友は伊ルザとなりそしてこの 佐々木秀吉も本を追われることになります 欧州藤原市を頼り向かう途中に渋谷茂国の 日護を受けることになりましてここで生活 することになりますそしてこの秀吉の子供 には有名な佐々木4兄弟がいます後から5 兄弟目を紹介するのでまずは4兄弟から 紹介したいと思います長男さつ次男つた3 南森津4男高綱です1180年に義友が 伊豆で挙兵した際には4兄弟たちは呼友に 突き従い山金高の館を吸収した初戦で活躍 することになります4兄弟はその後も寄り とに従うことになりまして長男のサナは 大美沖岩美長の守護を任じられることに なります次男のつたは淡路土佐アの守護に 任じられることになりますしかしこの次男 つたの家計は非常に悲しい末路を迎える ことになりますつた高親子は1221年の 上級の欄の際には後葉条項型につくことに なりますやはり最極の守護ということも ありありまして長底型になびいていた可能 性があるかと思いますこの戦いは鎌倉幕府 方に圧倒的な兵力が集まることになって配 を喫することになります長年の厚労者で あるつたは幸福を進められますが自害して 果てることになり子供の高しも殺害された と言われています三南モツは多くの兵家と の戦いに参戦しよりとの森人も熱く鎌倉 幕府開封後に平が友正の討伐にも参戦する ことになりますよとより越後の国カジノシ や美前の国小島の書を与えられておりまし て子孫は家事を称するようになります息子 の信実は工藤スツの額を殴るという事件を 起こしておりますが1221年の上級の ランでは鎌倉殿の13人でも三浦吉村に じじいうるせえんだよと暴言を吐いて注目
を浴びた演出で登場していた北条友の北陸 道具に属して皇をあげることになります そしてこの皇により美前の国の守護となっ ていますまたこの信実の子孫には後に上杉 剣士に使えその後を継いだ上杉影勝に反響 を響すことになる柴田茂への柴田市を排出 することになりますこれも越後の国カジノ 章を与えられたことがきっかけの家計と なるかと思います他にもさっさもこのモツ に関連していると言われています源の正信 から始まった話を今回お送りしております がすでに越後の武将たちにたどり着いて いるということになりますやはり佐々木 秀吉の存在は非常に偉大であることが 改めてわかりますそして次は4男の高綱 佐々木4兄弟の中ではこの高綱が1番有名 かもしれません兄たちと共によりとも巨 Hold時から突き従い子を重ねていく ことになります特に有名なのが木曾吉中と 源の吉恒の戦いとなる宇川の戦い雪解け水 で増水していた宇川で高は梶原影時の子供 の影と先人争いをすることになります高は 影が乗っていた名馬ススの腹帯が緩んで いるので閉めなされと言って陰生が 締め直しているうちにこの高綱が右側を 渡り名乗りをあげて先人を切ることになり ます兵家滅亡後には長と美前の守護となっ ていますこの高津の子供には三綱がおり 高綱の弟のよきの勇志になったと言われて いますここまで佐々木秀吉の子供の4兄弟 について紹介しましたが実はさらに弟たち がおりまして今回はご兄弟として5人目も 紹介したいと思います佐々木よき佐々秀吉 の五男として生まれておりますが誕生した タイミングは兄たちとは異なり父秀吉がの 乱で破れ落ちのびる途中に渋谷し国の庇護 を受けましたがその際にし国の娘を秀吉は めとることになりましてその間に生まれた のがこのよきとなります4兄弟とは異なり 投獄で生まれたということになります そして大葉影近の娘を妻に迎えることに なりましてユ友の巨Hold寺には大葉 家地の元に存じることになるわけですこれ も今までの義理を果たすための行動となり まして4兄弟はよ友の元に感じることに なりますその後はこのよきも友型に加わる ことになりまして以降多くの戦いに参戦し 和田活線でも活躍することになります上級 のランの後にはいも沖の守護に任じられる ことになりまして西日本の地に根を下ろし ていくこととなりますそしてその子孫が 出雲源治となりここから多くの分流が別れ ていくことになりまして円もその一族の1 つとなります話は佐々木秀吉の長男のさ まで戻りたいと思います秀吉の長男として
多くの戦いに参戦し相当な皇を上げている ササは1205年に亡くなりまして子供の 広綱は強後人として活躍することになり ますがこれが運命の別れ道となってしまい ます五葉条項との関係を深めていくことに なってしまいこれにより1221年に勃発 した級のランでは言葉条項型としてはじる ことになりますしかし結果は周知の通りで 大敗をきし捉えられて処刑されてしまい首 をさらされることになってしまいますこの 戦いで同じくサの子供の野は幕府軍として 戦闘に参加し言葉女皇方を打ち破ってい ます妻には北条義時の娘を迎えておりまし て北条家とも近しい間柄となります大江の 神にも任じられておりまして佐々木家を 晩酌化させていくことになりますそして この野の4人の子供たちから家計図が さらに広がっていくことになります野の 長男には茂がおりましてこの家計は大原の 章より大原を称するようになりまして大原 氏として続いていくことになります次男と して生まれている高は子孫は高島を称する ようになったとされておりまして西大江に 広がっていくことになりますこの高島市 からも多くの分流が出ていくことになり ますがその中でも自党を務めていた靴のシ より靴種を称するようになり室町時代には 方向酒を務め足が将軍家に使えることと なりますこの家計で特に有名なのは靴元綱 この元綱は金ヶ崎の野口では信長の京都へ の機関を助け関ヶ原の戦いの際に小早川は 秀明と共に東軍に願えることになるなる 人物ですこの後の靴市は一時大名としての 身分を失うことになりますがこの靴元綱の 三難の種は徳川家光に使え故障組番頭所員 番頭となって1635年には若年よりまで 出世を遂げることになります1636年に は画像を受け1万国となって大江く班1万 国の大名となっています後に3万国まで 稼働されることになりまして容姿を迎え ながら続いていくこととなります今度は源 の政信から始まり島までたどり着いて しまいましたまた話は佐々木信の4人の 子供まで戻り続いてはヤツとなりますこの 安綱からはあの六角市が始まっていくこと となります京都の東の党員六角に屋敷が あったことが六角家の由来となったと言わ れていますこの六角形は宇源二佐々木市の 着流さです鎌倉時代には大江守護を務め さらには六原短大で表情臭を務めるなど 鎌倉幕府でも西において重きをなすことに なります室町時代には戦いに明けくれて いくことになりますがそれと共に勢力を 拡大していくこととなりますしかし戦国 時代になると観音寺騒動もあり六角家の力
が失墜しそして信長が上陸を開始する際に は逃亡することになり観音寺場を失うこと になります六角種は江戸時代には大名とし ては残っていないということになります話 は再び佐々木信の4人の子供に戻りますが 次がラストとなります野の四男とされて いる人物の宇をしたいと思いますそして この宇のはある有名な部の祖と言われて いる人物ですそれは強国家です今日の強国 高辻に屋敷があったことから強国を称する ようになったと言われている強国家この 過疎の宇のは引きつけ集や表情臭といった 鎌倉幕府のど真ん中でも活躍している人物 で北条特装家で表すと北条安時から定時が 失権だった頃を生きている人物となります 大御神にも人間し鎌倉幕府でも有力なご 家人となっています強国家も相当大きな 一族となっていきますが中でも有名な人物 をピックアップしていきたいと思います この宇野のひ孫には佐々木道陽で有名な 佐々木高うが出てくることになります バサラ大名として有名な道陽となります 個人的には佐々木道陽はやはりタイガ ドラマ太平器で陣内高さんが演じる道陽に はまってしまったのを思い出します ハンガンという呼び名が記憶に残ってい ます元々鎌倉幕府に使え足高につき鎌倉 幕府を滅亡させて室町幕府開封後に6カ国 の守護を務めることになりますそしてこの 同様の孫の高久の家系がアゴを称するよう になりまして子孫は出雲に下りそこから 戦国大名と貸していくこととなりますこの 高石のひが勢力を拡大させていくことに なるアゴ常久となりますアゴ氏の話は奥が 深いかと思いますので強国家着流さに戻り ましてこの同様の家計を進んでいくと六角 士が務めていた大御守護務めることになる 持ちそして戦国時代には強国高義に たどり着くことになりますこの高義の子供 の高津は信長に使え後に光秀に使えること になりるみとなってしまいますが妹が秀吉 の調いを受けて即しとなった松ノ丸殿と なり秀吉に使えることになりまして大名と なっていますそしてあ長正と大一の方の間 に生まれたあ3姉妹の地条の初を性質とし て迎えることになったのがこの高津となり ます関ヶ原の戦いの際には上に臨場し英軍 の一部の足止めに成功してこの甲により 画像を受けて天方が序盤にありながらも 佐木丸亀班として明治維新を迎えることに なります高津の弟の高智は関ヶ原の戦いで は本線に参戦し戦後に河により単語の区に 一刻を与えられていますこの高友の子孫は 大名が3期ありましたが着流さ班は海域と なっておりまして大名としては2家が続い
ていくこととなります北海道に強国町と いう自治体がありますがその由来はその ままで強国高津の家計で佐木丸亀班がある ことを紹介しましたがその子孫である強国 高が現在の強国町に農場を開いたことに より長明になっておりまして北海道の地で も強国家の歴史を感じることができます 平安時代の源の政信から始まり明治の 北海道までたどり着いてしまいましたと いうことで今回は光る君へでも絶賛登場し 友子の父として謝大臣となっている源の 政信の子孫たちのとてつもない広について 紹介させていただきました以前紹介した 藤原の信高の子孫とはまた毛色は異なり 違った子孫たちの形で広がりを見せていく ことになります庭竹から宮宅の不味の宮宅 につながり現代皇室につがったりですとか そしてやはり宇源二の武家の広がりや 佐々木秀吉や佐々木4兄弟バサ大名の道陽 強国家や六角家雨家など武としての広がり 方も相当なものがあることが分かります 是非源の政信が出てきたら宇田原を紹介し たいと思い今回企画させていただきました 次回以降もまた平安時代の有名な人物の 子孫たちについて触れていけたらと思い ますこの度は小葉チャンネル最後までご 視聴いただきありがとうございましたもし よろしければチャンネル登録高評価 よろしくお願いしますありがとうござい まし た です
源雅信とその子孫たちについて紹介したいと思います!
源雅信といえば、今年の大河ドラマ「光る君へ」に序盤から登場!
益岡徹さんが演じられているので、わかりやすい人物かと思います!
そしてその源雅信から宇多源氏の家系が大繁栄していくことになります!
今回は公家も武家も大繁栄した宇多源氏・源雅信子孫解説です!
#光る君へ
#源雅信
#宇多源氏
●画像引用
光る君へ公式HPより引用

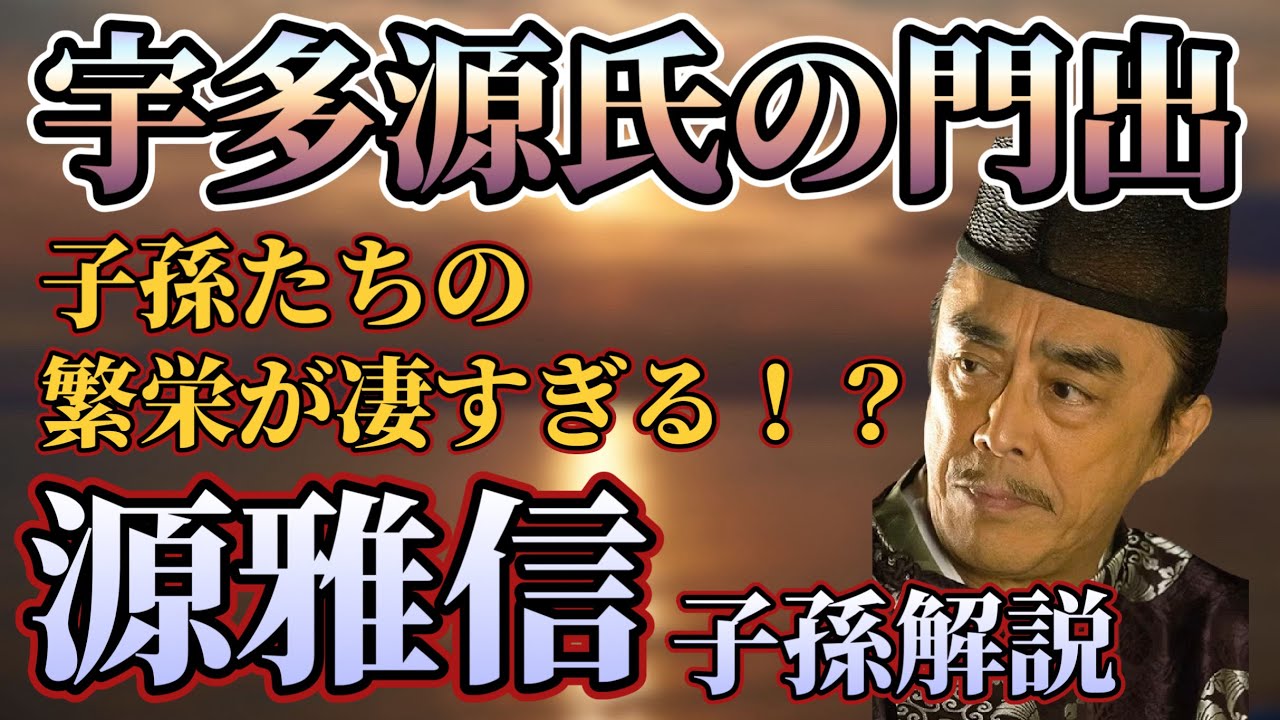
22 Comments
京はその後、私が知ってるだけでも保元平治の乱をはじめ、数多の戦乱が続いた。
おそらく、貴重な書物の殆どを滅失したものと推測する。
その結果、「史実」として扱われてる事実も、真実とは異なる事が数多あると思う。まあ、仕方のない事なんだけど。
宇多源氏は歴史に大して明るくない私でも聞いた事あるくらい、有名な武家を輩出した名門ですね。例:佐々木・京極・尼子 etc…
宇多源氏の家系について、いろんな人と、繋がっていな事がよくわかり、興味深かったです👍🥰
毎回思うのですが、昔は領地名に姓を変えていくので実に解りづらいですね。辿っていくととんでもない家系に繋がって行くのは面白いですが、これだけ調べるのも大変でしょう。日本人はみんな天皇の子孫なんて言いますが強ち大袈裟では無い気がしてきます。
すごいですね。
驚きました。
先祖が佐々木盛綱氏と関わりがあった?と聞くので(倉敷の児島のあたりで?)、彼の末裔についても興味があるので知りたいです😊
ありていに言えば「佐々木、お前は何を言っとるのかわからん!」と言われた人のご先祖。
コツバ先生、宇多源氏のお話しなかなか良かったです🐱
私の先祖である、村上源氏・具平親王と清和源氏・河内源氏をくどいくらいにご説明頂きたい😅
ただただ良く調べたなあと
感激するばかりです
記憶にある人物の家系が分かりました
いつもありがとうございます🙇
今回も楽しいですね🙌
たくさんありますが、陣内孝則の佐々木道誉、よく覚えております❤
(余談ですが、ドラマ【1リットルの涙】での父親役も良かったです)
コツバ先生、成頼の末裔は近江源氏ではありません
新羅系の古族で沙々貴神社の神主家であり、その末裔です
成頼は扶美の近江守になった佐々木野氏に系図を繋げたのです
扶美の家系に沙佐々貴氏が意識的に接ぎ木したのですよ😅
今回の大河ドラマに出ている益岡徹さんの源雅信の子孫も、多くの大河ドラマに出演されていますね。
最近では鎌倉殿の佐々木の爺さんが印象的でしたが、太平記の婆娑羅大名の陣内さんの佐々木道誉も個人的には好きなキャラクターでした。
その他、毛利元就の尼子家の人達も子孫でしたし、本当に子孫は多岐にわたって繁栄していますね。
堂上に泊まった公家は宇多源氏三家、村上源氏八家、この二つのお家は血筋が非常に高まる
大変良かったです。佐々木道誉、京極高次、お江与までつながっ話が面白かったです。頑張下さい。
三越の三井家も藤原道長の血筋とも源雅信を祖とする佐々木六角氏の血筋とも言われています。
とても興味深く拝見しました。
鎌倉時代に源実朝と共に鶴岡八幡宮で暗殺された源仲章も雅信の子時方に始まる子孫の一人ですね。鎌倉殿の13人で生田斗真さんが演じた印象深い人物です。
島耕作を描かれた弘兼拳史さんも佐々木源氏(尼子氏)を先祖に持つそうです
母方の祖先が六角氏の被官を務めた川村氏で、主家没落と共に帰農しようにも土地が無い近江を離れ京や大坂や江戸にでて商人となりました。
名字の由来が越後の加地の荘で、宇田源氏からの佐々木四兄弟の三男からとは知っていましたが、今回の大河の雅信からとは不勉強で知りませんでした。ありがとうございました。
とても面白いですが、こういった家系紹介するなかに時々出てくる、私の家系も~みたいな家系自慢が鬱陶しいです。
説明によると、佐々木家の出所が宇多天皇と聞かされていたのが、本物だったことが理解できました!先祖の顔に泥を塗ることなしに、清廉潔白な生き方をしていきます!!79歳🥰😄😅
先祖の解説動画を見るってなかなかに無い事で光栄なことです。
ナースのお仕事の永島先生のイメージが強い
宇多源氏と言えば、尼子経久?